

 バックナンバー(08年10月~09年01月)
バックナンバー(08年10月~09年01月)
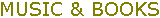
| >HOME >BOOKS |
| P.G.ウッドハウス 『ユークリッジの商売道』(文芸春秋) |
| ウッドハウス選集Ⅳとして、ユークリッジものを修正。前に書いたが、このユークリッジというキャラクターは、私だったらちょっとお付き合いは遠慮したいタイプである。語り手のコーキーは、よく鷹揚に付き合っていると思う。ユークリッジものが苦手なのは、一人称のコーキーに入り込めないせいであろう。ただ、道具立てとしては、コーキーと大家がバーティーとジーブズの原型ともいえる。このシリーズでもっとも愛すべき人物は、ボクサーのビルソンである。荒くれでユークリッジは彼のマネジメントでひと稼ぎを考えるが、ビルソンの人のよさでいちいち失敗する。ユークリッジの人物像からモデルを探す研究者のエッセイは面白い。あとがきにもユークリッジは好き嫌いの分かれるキャラクターとあるから、私のような者も珍しくないのだろう。 |
| メアリー・C・ブリントン 『失われた場を探して』(NTT出版) |
| 本書は90年代以降の若年者労働市場の問題点を扱った研究だが、日本社会を研究しているハーバードの社会学者が、日本人読者向けに書き下ろしたところがユニークである。調査は念入りで、高校の進路指導についての研究は特に緻密と思われる。インタビューとデータを組み合わせて説得力が高い。そして中程度以下の普通高校卒業生に特に深刻な状況が生じていて、それが日本のストロングタイズに維持されてきた雇用関係の崩壊によるものであることが明らかにされ、学校・職場という「場」の崩壊状況の中で、ウィークタイズの活用のための信頼醸成、対人関係能力の育成と評価が重要になっていることが示される。読みやすいが、内容は重厚な研究書である。 |
| 内田樹 『街場の教育論』(ミシマ社) |
| そろそろ教育論議の新鮮味が廃れてきたところで、中山ナントカ大臣の日教組亡国発言みたいなのがあって、同調する議員が群れたりしているようだが、まあそれでも不景気に推されてたいして議論が盛り上がっているとも思えない。まさにこの盛り上がらない実態こそが、世間の教育観を物語っているというべきであろう。中山ナントカやこのところの総理大臣の体たらくこそが戦後教育の結末だとすれば、なかなか面白いパラドックスかもしれないが。さて、まさにそんな時勢で内田樹の教育論は怪気炎を吐くというべきものだ。教育者は社会的にねじれた位置にいるのがつきづきしい、と彼は言う。教育改革の方向が、もし教育という観点から考えれば、根本的に絶対に間違っている確信を持っていない教育者がいないとは思えないのだが、それが加速するばかりでとどめようがないのは、教育の外の問題だからだろう。ネカフェ難民の取材を通じて、そんなに「難民」がいるのなら何故、何人かでまとまって安アパートの一部屋を借りないのだろう、という指摘こそ重要だ。インフォーマルなコミュニケーションの場を学校から(だけじゃないが)どんどん削除して行きながら、コミュニケーション能力がないとなげき、あるいはその養成を学校に要求し、そのための「授業」を体制化する(またはそれをメシの種にする)愚鈍な、あるいは悪辣な連中が、行政や学校にたかっている。一番絶望しているのは教育者である。読んでいると自分の思いがどんどんわきあがってきてしまうが、とにかくこの一冊、教育者が読めばひと時の安らぎとはいえ溜飲は下がる。その他の方々は、前書きにあるとおり、読まないほうが良いかもしれない。 |
| ジャック・マクデヴィッド 『探索者』(早川書房) |
| 舞台ははるか一万年の未来で、主人公は若き古美術商とコンビを組む女性パイロット。初期の宇宙開発時代の遺物を見つけては売買するのだが、失われた植民惑星の謎に迫るプラスチックのコップが持ち込まれたところから、ライバル商人や遺物売買に批判的な学者、諜報機関が絡んで、命がけの冒険が繰り広げられる。舞台設定の時空的スケールの大きさに比べて、生身の活劇や男女のやり取りなどは今と変わらないので、要はSF冒険活劇である。SFの仮想テクノロジーとしてはサイバーパンク以来の万能情報ネットワーク的な舞台装置が不釣合いなほど貧弱なところに成立する筋立てなので、そこに違和感を感じないでもないが、でもまあ、遠未来SFなんだからお膳立てはいかようにもできる。むしろこの不釣合いさが新しいかもしれない。一気呵成に読んでしまう面白さは保証つき。 |
| 國分康孝 監修 『カウンセリング心理学事典』(誠信書房) |
| わが師匠國分康孝先生監修の、画期的なカウンセリング心理学事典。事典としての項目の充実もさることながら、分野別の項目立てやカウンセリングの歴史や教育まで、カウンセリング心理学の全体像をつかむ学習事典でもある。ワタシも4項目ほど、哲学・思想的背景に関してお手伝いさせていただきました。カウンセリング学徒には必携、ぜひ座右にお備えを。 |
| ロバート・チャールズ・ウィルソン 『時間封鎖(上)・(下)』(創元SF文庫) |
| 聞いたことある名前だとは思ったが、ここで感想を書くのも3作目だった。突然地球が何かに覆われて、外の時間が早くなる(というか中の時間が遅くなるというか)。何者が何のために、どのようにしてそうしているのか、まったく分からない。その覆いは外からの物質やエネルギーの流入をコントロールするが、このままでは太陽の死まで行き着いてしまう。そこで火星をテラフォーミングして移住を計るが・・・。しかしまあこのスケールの大きさというか、設定の突拍子のなさはどうだ! 主人公を取り巻く人間関係の葛藤も普通小説並みに書き込まれていて、こっちのどんでん返しもなかなかのもの。しかし火星がどうなるか、そしてその先は・・・と、大技を次々と繰り出す、あっという間に上下読み終えてしまう展開の大胆さがすごい。しかし、終わりに近づくにつれて、イヤーな予感が・・・そう、やっぱり、この謎は、この上下二冊では終わらないのだった! まあそれにしても、めちゃくちゃ面白いですぜ! |
| フィリップ・エリアキム 『禿頭礼賛』(河出書房新社) |
|
たいへん申し訳ないのだがワタシは毛髪が濃い。行きつけの床屋によれば単にくせ毛というだけでなく、毛量が多いそうである。だから著者のような悩みが全く存在しない。いずれにせよワタシももう50なので、これから薄くなってもどうということはない(ような気がする)。 誰もが何らかの劣等コンプレックスを持っているものだし、身体的な障害のつらさとは比べることもできないと思うが、それだけにかえって、若くして髪が失われつつある当事者の深刻さと、周りの印象とのギャップが、どんどん滑稽さを増していくことになる。著者の世代はたぶん私と同じくらいのはずで、となると確かに長髪が普通の時代であるから、思い切ってボウズというわけにもいかなかっただろう。怪しげな注射を打たれて思わぬところに毛が生えたり、大金を投じたアスファルトのようなパックを剥がすときにさらに毛を失ったり。出始めのミノキシジルは著者には効果はなく、挙句の果てに、ハゲが原因で振られたと思ったガールフレンドの新しいボーイフレンドがハゲだったり。やはりつい笑ってしまう。 結果的にはジャーナリストとしての仕事や、妻子にも恵まれて、充実した幸せな人生を送っているようだが、考えてみれば禿げないためにあれこれ試したり、禿げ切ってしまったら得られないと思いこんでの女性との積極的な交際などの行動力はものすごいものがあったわけで、それがもしかすると禿げという動因に突き動かされていたのだとすれば、まさにこれは禿げの力であり、ということは禿に限らない、コンプレックスをバネにした生き方に(結果的に)なっていたということだろう。 皮肉の利いたユーモアだけでなく、古典からの引用やら歴史の蘊蓄やら、ジャーナリストらしい政治や文化への言及など、知識欲をくすぐるエピソードもちりばめられた中に、誰もが持っているそれぞれの自分の劣等コンプレックスとの向きあい方を考えさせられもする。 |
| テンプル・グランディン、ケイト・ダフィー 『アスペルガー症候群・高機能自閉症の人のハローワーク』(明石書店) |
|
経産省の「社会人基礎力」がクソだと思うのは、何ら統計的な根拠がないのだからそれだけで話にならないのだが、このような規格化が、現実に存在する様々な才能を企業が生かしていくにはあまりにも粗雑だからである。アスペルガー症候群や読字障害などがあっても、特定の分野に優れた(あるいは少なくとも水準以上の)能力を発揮する人はいくらでもいる。だからそういう人々を適材適所でうまく使えれば、お互いに悪いことはないのである。今度は文科省がらみで「学士力」なんていうものまで出てくるらしいが、もういいかげんこういう規格化はやめてもらいたいものである。学歴に代わるものがこんな規格や資格の型にはまった物差しだと言うなら(まあ社会人基礎力なんて物差しにすらならないが)、実力主義とか人物本位とか、いったいどこへ行っちゃったんでしょうかね。 読み始める前には、海外の事例であるし、グランディン博士のように特に成功した人物の書いたもので、どれだけ一般の、しかも日本人に役に立つかと予断を持っていたのだが、実際に目を通してみて、これはたいへんすばらしい本であることがわかった。自閉症スペクトラムの人自身に、どのような工夫ができるのかを、自閉症者であり社会的に成功を得た人の目から、わかりやすく整理して取り上げているので、非常に説得力があるのである。怒りの感情を泣くことに転換するとか、ビデオゲームの技能は役に立たないとか、同じ立場から発するからこその説得力がある。おそらくこの整然としたまとめ方と、正直な事例という書きぶりも、自閉症スペクトラムの人だからこそのもので、同じ障害を持つ人にも読みやすいものであろう。 日本における就労支援の窓口の資料も増補されているのは親切であるが、本書が本当に役に立つといえるのは、やはり日米の違いにかかわらないアスペルガーの人らしい生き方のアドバイスであろう。 |
| コニー・ウィリス 『マーブル・アーチの風』(早川書房) |
| 絶対に期待を裏切られないコニー・ウィリスの、プラチナ・ファンタジー独自編纂のアンソロジー。出だしの『白亜紀後期にて』は、身につまされる話ではあるが、ちょっと肩透かしを食った感じもあるが、あとはどの作品もすぐにはまる、文句なしの面白さ。『ニュースレター』と『ひいらぎ飾ろう・・・』は、ほほえましい風習や暖かな人間関係にSFのストーリイが見事に組み合わさった、おそらく典型的なウィリス・ファンが大喜びする傑作だし、タイトル作のシニカルな不条理、『インサイダー取引』のパラドキシカルなスリルとユーモアと、5編とも程よい長さで満足な読み応え。絶対のお勧め本です。 |
| 横山征次 『紙飛行機が会議室を舞った』(講談社) |
|
たとえばダイエット本にもいろいろあって、もうどう考えてもとんでもないと思えるものから、芸能人がこうしたらうまくいったとかいうもの、そして医者や栄養士が書いた説得力のあるものまで、さまざまである。トンデモ本は別として、説得力のあるものも多いが、もしこれで決まりというものがあれば他は淘汰されそうなものなのに、結局そういうものは存在しない。ダイエットの真実は単純である。私が検診のついでに相談した医者が言い放った通り、「食わずに動けばやせる」。これに尽きることは誰でも知っている。摂取カロリーよりも消費カロリーの方が多ければ痩せるし、少なければ太る。バリエーションが必要なのは、どうやって飢餓感を紛らわせるかの方法の工夫だろう。 それが経営指南書のようなジャンルなると、単純な真理はどこにあるのだろうか。「必要なものは売れる」ではだめなのか、と言いたくなるが、大体そういう本は、作った製品が売れないとか、会社の利益が上がらないから読まれるのであって、つまるところは「本来必要ではないものをなんとかして売りつけるにはどうするか」、「本来存在しなくてもよい会社を、いかにして存在させ続けるのか」といった話で、基本的に胡散臭い話にならざるを得ないのではないか。 さて、そもそも「社会人基礎力」というのは、経産省の審議会でまとめ上げた概念のようで、公開されている審議過程を見る限り、いかにも審議会形式で役所がまとめた図式の典型、下位概念もたとえばスキルと人格特性がごっちゃになっているけどいいの? というような、役所の審議会答申におなじみの「根拠らしい根拠がないのに形だけもっともらしく整えた」いたって粗雑なものである。作り方がいい加減なのに、これをもっともらしく評価させて効果測定をしたことにするようで、社会調査法の授業なんかで絶好の「悪い例」にできそうな(やっちゃおうかな)しろものである。 それにしてもこれが恐ろしいというか「何企んでるんだこいつら!?」と思うのは、これを次のように位置付けている点である。 ①育成・評価が可能な能力である ②自己の強みを伸ばしアピールするための土台である ③各成長段階を通じて一貫した育成が必要である ④学校教育の中で育成が可能である ⑤家庭・地域社会における取組が可能である もうこのたった5つの項目ですらきちんとカテゴライズできていなくて、こんな文書をネットに曝して大丈夫なのかと思うほどぐちゃぐちゃだが、つまり家庭も学校も産業界が今要請しているらしいこのセンで子育て・教育して、評価しろと言っているのである。ただ、もちろんそんなことはそもそも不可能であるし、私自身こんな(・・・どんな?)子育てや教育を行うつもりなどは毛頭ないのだが、現実に学校で仕事をしている限り、こういう愚劣なプロジェクトが決まって上から降りてくるので、いやいやながら従わざるを得ないこともしばしばなのである。しかし、私自身もそうだが、これだけ総花的に下位概念が並んでいれば、自分が行っている授業実践の中に必ず引っかかってくるものがあるので、ちょこっと手直しなり作文をすれば、おいらも社会人基礎力教育やってます! てなことになるのである。だいたいPBLだなんだというが理工系の卒研なんてフツーにPBLじゃないのか? そんなこんなの寄せ集めで、立派な作文が出来上がる。まあ、役所主導のプロジェクトのつじつま合わせ、毎度毎度のことである。 だから肝心なことは、学生なり生徒なりの利益を考えて何かをするということで、例えば著者たちが山梨学院大学で行った学生グループでの商品開発競争などは、面白い授業だったと思う。でもこれはもちろん、経産省のプロジェクトでなくても、ぜんぜんかまわない。経産省の肝入りであれば企業が出てくるというだけである。逆にいえば、(文科省ではなく)経産省の肝入りですよ、という事情がないと、学校が何か思いついてやろうとしたときに企業はそう簡単には乗ってきてくれないということである。産学協同とは、まあそういうことである。 さて本書である。どこを見ても決まり文句だらけの「社会人基礎力」を斬新な切り口で取り上げるには、極度に胡散臭い設定に当てはめてみることで成功しているのかもしれない。舞台が芸能プロダクションで、オチが北海道の村の観光プロジェクトというのは、大冒険と言うべきだろう。話としては面白いので、例えばこれを月9のドラマなんかにしたらいいんじゃないかなとは思ったが、帯にあるようにこれが「心を打つ物語」というのは、ちょっと普段いったいどんな物語に心を打たれているのか疑ってしまうし、ポラリス何とかの観光プロジェクトに至っては、こんなふうにして夕張はひどい目にあったんじゃないの、と勘繰りたくもなる。それにしても帯の文句はすごい。「これ一冊で、社会人に必要な「12の能力」が身につく」・・・ああこれじゃあやっぱり、ダイエット本だ・・・。 |
| P.G.ウッドハウス 『ジーヴスと封建精神』(国書刊行会) |
| 今回もフローレンスと結婚したくないバーティが、間抜けなドタバタにはまり、ジーブスが見事に窮地を救うといういつものパターン。割と読みやすいのは今回は登場人物が比較的整理されているからで、そのぶん魅力的なお嬢さんたちの登場が少なく、ちょっと物足りない感じもする。フローレンスはやっぱりちょっと、これはバーティでなくてもかなわないかもしれない。 |


