

 バックナンバー(08年07月〜9月)
バックナンバー(08年07月〜9月)
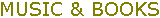
| >HOME >BOOKS |
| 森絵都・文、荒井良二・絵 『あいうえおちゃん』(文春文庫) |
| 2001年に出た絵本の文庫版のようだ。「いんどにいったらいんどかれー」といった、4・4・5字で(リズム的には3・3・7拍子のアレ)で、森の言葉遊びと荒井の崩れた絵が跳びはねる面白さ。ちょっとした毒があってかえって子供が喜ぶだろうな、と思う。もともと大判であったはずの絵本の文庫サイズというのは、おそらく絵本を見た人には物足りないかもしれないが、通勤にちょっと鞄に忍ばせておくとか、長引きそうな会議に持っていくファイルに入れておくとかする使い道がある。 |
| 高世えり子 『理系クン』(文芸春秋) |
| 職場にも家族親戚にもけっこういる理系のヒトビト。このN島クンは理系でも情報系の、昔で言うラジオ少年のタイプだろうか、元祖高等オタクとでも呼ぶべきヒトビトの典型かと思う。あまりにも時間が取れなくて彼女に振られたという話は身の回りにもあふれているが、N島クンのように研究室デート?はなかなかできないだろうし、何よりも彼女が「理系が好物」と断言する(それでも研究室デートの空気はかわいそうなくらいだが)からこそ結婚までこぎつけたのでしょう。身の回りの若い理系クンたちにも、彼女のようなパートナーがあらわれることを祈念します。 |
| 横山浩之 『ADHD/LD指導の基礎基本』(明治図書) |
|
本題ではないが、明治図書の本の作り方が私にはなじめない。まずは装丁のセンスやタイトルの付け方であるが、これは人によるかもしれない。もう一つは、同じ内容が複数の本でダブることである。同じ内容の原稿を使いまわしたらこれは著者の良識が疑われるが、横山浩之の一連の著作でいえば、発達障害についての講演、シンポジウム、セミナーなどを、まとまりをもって伝えるように編集しているので、たとえば導入の解説が異なった本でも同じ内容になっていることがある。そこを割愛してしまうとわかりにくいし、整理する暇があったらどんどん出すべきだという考え方もあるだろう。しかし、もう少しうまく編集できないか、という気はする。本書も、2か所で行われたセミナーのまとめで、臨場感があってわかりやすく、たとえば研究会の紀要であったらわかるのだが、一般書としては、同じ図版も繰り返し出てくるので、やはり釈然としない感じは残る。 しかしそれでもなお、本書はADHDの子供を教える教師には、大変参考になる一冊と言える。模擬授業の記録も収められているので、ライブ感もあって、わかりやすい。ADHDの子供がいる学級で、具体的にどうしたらよいのか、というヒントがたくさんある。それらは医学に裏付けられ、体系づけられているので、なぜそうするとよいのかがよく理解できる。しかもそれは、発達障害のことに限らない。たとえば、94ページの就学指導委員、担任、保護者の座る位置などは、一般的な生徒指導でも重要なポイントである。著者が言うように、ADHD児の教育は、普通の子供に使う教育のテクニックで十分なのであるが、その子に合った方法を見つけるまで、手を替え品を替えしなければならない。もともと、教師がそういったテクニックを豊富に身につけているかがそもそも問われるのである。 |
| カート・ヴォネガット 『追憶のハルマゲドン』(早川書房) |
| もう出ないだろう、と思っていた、故ヴォネガットの作品集である。息子マークによる序文、ドイツ軍の捕虜になっていたヴォネガットが終戦後家族に送った手紙、生前用意されていたスピーチ原稿、未発表短編11篇が収録されている。未発表短編といっても皮肉なユーモアに満ちた作風はどれもヴォネガットならではのもので、発表された作品とくらべて遜色はまったくないように思える。ただし戦争、特にヴォネガット自身が体験したドイツ戦線や捕虜生活に題材をとったものが多く含まれていて、現実の出来事や実在の人物との関係もあったのかもしれない。若きヴォネガット上等兵の手紙は、家族に無事を知らせる手紙でありながら、実にヴォネガット作品らしい文章になっている。淡淡といきさつが綴られ、その段落ごとに「僕は死ななかった」「僕は無傷でした」で結ばれる。生死の分かれ目ごとに圧倒的に多くの命はもう一つの道をたどっていったことを、実は雄弁に語っている。この時代、この季節に読むものとしてはまことにふさわしいというべきである。 |
| ジャン=ドミニック・ボービー 『潜水服は蝶の夢を見る』(講談社) |
| フランスでもっとも権威あるファッション雑誌の編集長が、わずか43歳で脳出血のため倒れる。一命は取り留めたが、わずかに左まぶたを動かす以外、まったく体が利かなくなる。しかし、意識や思考は正常なまま。本書は、アルファベット表と片目の瞬きでつづられたエッセイ集。もちろん、病気にまつわる話も多いのだが、そこにはちょっとした皮肉やエスプリが効いていて、境涯を嘆くよりは不自由だからこそ体験される世界があえて言えば生き生きと映し出されるのである。そして過去を振り返る時のこまやかな描写や情緒は、さりげない話でも一つ一つの粒立ちが感じられるようだ。本書が出版されて二日後に他界した著者の、ことことと煮詰められたような深みとほのかな苦みをゆっくりかみしめよう。 |
| ミシェル・クラン 『パリの獣医さん(上)・(下)』(ハヤカワ文庫NF) |
| 13年飼っていた愛犬の最期を看取って間もなく、何となく手に取った一冊だった。晩年ほとんどの時間を眠って過ごしていた老犬は、最後に大きく伸びをしたかのように見え、荒くなっていた息を引き取った。摩っていた手に伝わる心臓の鼓動が弱まり、動かなくなったのを感じた私は、彼女の瞼を閉ざし、口と鼻を拭い、段ボール箱にタオルをしいて亡骸を納めたのだった。病院にいれば、強心剤を打ったり、心臓マッサージを受けたりできたのかもしれない。でもこれでよかったと思うのは、まだ子犬だった頃に近所の獣医に連れて行ったときに抱いた不信感の名残だったかもしれないし、飼い主の勝手な思い込みだったかもしれない。今傍らには、彼女亡き後に新たに家族に加わった仔犬が、妻と一緒に丸くなってすやすやと寝息を立てている。たぶん、犬のいない我が家というものはもうありえないだろう。フランスの有名な獣医師は、人間と暮らす動物、動物と暮らす人間に、等しく目を向けているように思う。とりわけ印象に残るのは、小さなアパルトマンで50匹以上の猫を飼う夫人の話である。日本でもしばしばニュースになる近所迷惑な猫屋敷の話をイメージすると、これがまったく違うのだ。スマートな暮らしぶりで夫も独立した子どももいる。休暇には猫たちを連れて郊外へ出かけ、想像を絶する嫌がらせにも危険を冒しても立ち向かう。動物たちは生かしてくれる人間にはその暮らしにうまく順応していく能力を持っているのであって、そこにまさにともに生きる知恵も力もあるのである。無論、失敗や安楽死の現実も隠さずに語られて、あるべき関係の模索は続けられる。常識だと思っていたことがいくつも覆させられるのに驚く。そして長年の仕事のパートナーでもある奥さんに、結局動物たちがなついてしまうのはなぜかと、ちょっとやきもちも焼いてしまうのは、いかにもフランスらしい愛妻の表現でもある。盲導犬の訓練のお国柄も面白い。それ以上に、獣医師という人種の見方や考え方にも触れて、少しは誤解も減ったかもしれない。 |
| むのたけじ 『戦争絶滅へ、人類復活へ 九三歳・ジャーナリストの発言』(岩波新書) |
| 戦前戦中と新聞記者を務め、終戦の日に戦争責任を取り退社、秋田県横手市で週刊新聞「たいまつ」を30年間発行し続けた。本書は目を悪くした著者からの聞き書きとなっている。著者の凄みは、このあまりにも直截なタイトルに引いてしまうのではなく、この時期にあえてこのタイトルは何故と、いささか怪訝に思い本書を手に取る者に伝わる。従軍記者として見たことや聞いたことは、勝ち負けを超えた人間の姿であり、新聞社をやめないでやるべきことがあったという後悔、憲法九条の解釈、反戦運動で戦争はやめさせられないなどの洞察からは、気づかされることが非常に多い。都合の良いところを引くのではなくて、丸ごとのむのたけじを読みとりたい。 |
| 横山浩之 『軽度発達障害の臨床』(診断と治療社) |
| 医療と教育と親子関係。発達障害はこの3つが巧くかみ合わないと対応できないのだが、どの立場であれ良心的に対応しようとした人は必ず壁にぶつかって、その困難を思い知らされているはずである。著者は専門医であるのみならず、軽度発達障害児の親でもあり、教育に深くかかわり続けてきた。いわばこの三つの立場を同時に体験してきたわけで、本書は専門書であるが(したがって価格も少々お高いが)その分多くの症例が取り上げられていて、さらにこれらの連携に主眼を置いているから、教師や親にもむしろおおいに参考になる一冊である。とはいえ著者は明治図書から教育者向けのガイドや講演集、ドリルブックなども出していて、教育者との共同作業も多く、そのどれもがたいへん実際的で役に立つので、その中からまずは読み始めても良いと思う。小学校低学年で専門医に出会い、親がよく理解し、連携の取れる教師に出会うことは、軽度発達障害児にとって決定的に重要でありながら、それは今でもまだほとんど幸運といわざるを得ない状況である。十分な対応を得られてこなかった軽度発達障害者へのよりよい対応を模索する立場としては、今後にどれほど期待できるかはあまり考えないようにしているが、本書はそれでもなおありがたい手がかりになりえる一冊である。 |
| 波平恵美子 『日本人の死のかたち』(朝日選書) |
| われわれが「死とは何か」と問うときには、それは単に生物的な死、自然的な死を問うているのではなく、すでに経済的、政治的、倫理的な死を問うことになるのが、ヒトという種に特異的な出来事であるといってよいだろう。著者は本書において「死が政治性を帯びることの日本的なありよう」を論じている。おもに病や死をテーマにしてきた文化人類学者として、緻密なフィールドワークの視点は文献研究においても生きていて、特に戦時における「遺体」の扱いがどのように移り変わり、それが遺族にどう受け止められているかを丹念にたどることによって、「死が政治的であること」からは、一見戦争のない現代にあっても逃れられないことに気付かされるのである。もう4年前の本であるが、暑い敗戦の夏の読書にふさわしい一冊であることに変わりはない。 |
| 桜井哲夫『増補 可能性としての戦後』(平凡社ライブラリー) |
| 1993年に出版されたものに、短い増補が加えられて2007年に平凡社ライブラリー版として出版されたものであるが、増補版のあとがきにあるように、本書が早すぎたものだったというのは決して著者の手前味噌ではない。杉浦明平や花森安治や松田道雄が身をもって示した戦後社会へのそれぞれの警告は、おそらく世紀を跨いだ今こそ深刻に響くように思う。圧巻はやはり渥美半島の移り行きの中で生きた杉浦の姿だと思うが、花森の人物像に感じていたつかみどころのなさのようなものが何だったのか、著者の分析から腑に落ちたところがあったし、松田道雄の言葉に子育て時代の自分が感じていた温かさや頼もしさがどこから来るのかについても、よりしっかりと受け止めることができたように思う。繰り返し言うが、これはまさに今読むべき本である。 |
| 神永正博 『学力低下は錯覚である』(森北出版) |
| 著者は数学が専門で、「学力低下」や「理系離れ」を理論的に検証している。といっても、難しい数式が羅列されているのではなく、読みやすく書かれている。理科大、京大院を経て企業に入ってから、東北学院大で教鞭をとるようになって、学力低下問題を数学的に検討しなおしていて、きわめて説得力がある。結局のところ、学力低下を決定付ける証拠はない。大学で学力低下が騒がれるのは著者の言う「縮小のパラドックス」のせいに過ぎない。学力低下と並んで常識のように言われる「理系離れ」も、学力では数学や科学より読解力に劣っていて、工学部の男子学生の比率には驚くほど変化はなく、理学部や医歯薬の志願者はむしろ増えている(ただし理系全体で見れば工学部の志願者数は減っている)ことから、これも錯覚である。結局、小中で国語と算数をじっくりやらせて、勉強の成果が現実のメリットに結びつくことでインセンティヴを高めるのが良いということである。教育問題を語るときに必ず参照すべき一冊といえる。 |
| 高橋秀実 『素晴らしきラジオ体操』(小学館文庫) |
|
新入生をオリエンテーション合宿で青年の家に引率していくと、「朝の集い」でラジオ体操をする。はなから運動が大嫌いで、今や年に一回だけしかやらないというのに、体がラジオ体操を覚えてしまっている。もっとも、この体では前曲げ後ろ曲げなんてほとんど曲がっていないが。 著者がラジオ体操のことを知りたいと思ったのは、新興宗教の潜入ルポルタージュで、信者たちの「万歳!」があまりにもだらけていたからだ、というのがまず面白い。ラジオ体操の起源はアメリカの保険会社にあったり、わが国では修養団体や霊能者と連なっていたり、意外なつながりや派生がわかってそれだけでも興味深いのだが、やはり圧巻は現存するラジオ体操人たちの取材である。戦前からやっている人たちというのは当然老人なのだが、このインタビューのやりとりがめっぽう面白い。そして、「なぜ毎日ラジオ体操をやるのか」「ラジオ体操は毎日だからだ」という同語反復の中にラジオ体操の真相が潜んでいる。戦前は健康の向上のため、戦中は国威高揚のため、戦後は民主主義のためと理屈をつけながら、ただひたすら体操する体操人のなかに、実は笑えないわれわれの鏡像を見出してしまうことになる。ものすごく面白いのでかえってものすごく恐ろしいルポである。 |
| クリストファー・プリースト 『限りなき夏』(国書刊行会) |
| プリーストの傑作短篇集。イギリスらしい陰影のある筆致をいつも堪能させてもらうが、時空の不思議に愛の幻想を組み込んだ作品は持ち味がいかにも生きているし、ミステリ仕立てのどんでん返しに驚かされたりもして、この作家の奥深さ、多面性がひとつひとつ楽しめる短篇集である。謎が謎のまま放り出されるのもうれしいところ。読み終わるのが惜しい気にさせる。 |


