

 最近の更新(09年02月〜7月)
最近の更新(09年02月〜7月)
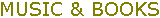
| >HOME >BOOKS |
| BOOKS |


 最近の更新(09年02月〜7月)
最近の更新(09年02月〜7月)
|
|
春日武彦 『援助者必携 はじめての精神科』(医学書院)
春日武彦 『「治らない」時代の医療者心得帳』(医学書院) |
| おなじみ春日先生の2冊を続けて読んだ。医学書院からの出版ということで分かるように、大判の『はじめての精神科』はパラメディカルの教育向けテキスト、ハンディで友人の吉野朔実のイラストや内田樹との対談も彩を添える『「治らない」時代・・・』は研修医対象のQ&A本といったところだが、そのいずれでもない私にも非常に参考になる、というか福祉や教育の分野で仕事をしている人にとって、ちょっと違った角度から自分の立ち位置や対象を見直すのにぴったりの本といえる。医療の世界では患者は選べない。そういう意味では、福祉や義務教育の世界と似ている。福祉との関わりも深い精神科となると、そうとう困った相手を前にして仕事をするのだから、自分のメンタルヘルスにダメージを受けることを防ぐ知恵は欠かせないはずである。これらの本で、もっとも参考になるのが、相手や自分の処し方というべき部分で、教育のノウハウ本よりもずっと腑に落ちる部分がある。医療のみならず福祉、教育の仕事に疲れている人には、おすすめの2冊である。 |
| ヴァーナー・ヴィンジ 『レインボーズ・エンド(上)(下)』(創元SF文庫) |
| これは話題作だしローカス賞ヒューゴー賞受賞作なので、期待して読んだが、意外にてこずってしまった。いつもみんながオンラインという社会で世界的な陰謀が進行する一方、アルツハイマーから復帰した老詩人を取り巻く家族や友人や若者がそれと戦う。81年作ですでにサイバースペースを舞台にした作者だけに、その発展形の、リアルとバーチャルが一体となった世界作りは見事だが、どうもこちらの意識が追いつけないようだ。物語りもどんどん拡大していって、嫌な予感はしていたがやはり・・・。 |
| ミルトン・メイヤロフ 『ケアの本質 生きることの意味』(ゆみる出版) |
| 最近は「ケア」という言葉がずいぶんと垂れ流されるようになってしまったので(特に「心のケア」という言葉が決まり文句で使われるのが気になって仕方がない)、あらためて本書のタイトルが「ケアの本質」であることに気づくと、普及したがために誤解されるこの「ケア」という言葉が使いにくくなったことを思う。哲学者メイヤロフのこの本を、医学者の立場から翻訳した訳者の思いにうかがえるように、目の前のこの人(に限らないが)に、その人として尊重するかかわりをしようとすることが、すべての人間的な活動の原点であるという、いわば最後の原点立ち返り論として、広く共感を呼んだことは確かである。あるきっかけから応用倫理学がケアの倫理学に立脚できないかという視点から本書を読みなおしてみたのだが、倫理学的な体系よりは、ケアのまさに本質を突くキーワードをじっくりと読み込んでいく構成は、圧巻ともいえるもので、ギリガンやノディングズの著作に比べれば、とてもシンプルだが、じつは雄弁な一冊であると再認識した。 |
| ロバート・M・パーシグ 『禅とオートバイ修理技術(上)・(下)』(ハヤカワ文庫NF) |
| なかなか感想を挙げる踏ん切りがつかない本がたまにあるが、これはその最たるものだった。そして結局、わたしにはこの本の面白さが全く分からない。十一歳の息子とバイクの旅をする父親の物語なのかな、と読み始めると、この父親はもと修辞学の大学教授で、鬱病にかかり電気けいれん療法を受けたところ記憶を失ってしまったという著者なのである。パイドロスという、記憶を失う前の名前にも混乱する。わたしにはプラトンの対話篇の登場人物を思い出させるからである。もっともそれは、クライマックスに近づくと重要な意味を持ってくるのだが。著者のいう「クオリティ」は、禅にも心の哲学にもつながるテーマとして読めるし、長大なロードノベルとの組み合わせは画期的である。しかし、どうしても私は、記憶障害や鬱の予後としてどうなのかとか、親子関係はどうなのかとかいったところで反応し、突き放して見てしまい、クオリティどころじゃないのではないか、と気もそぞろになって疲れてしまうのだ。なんとか最後まで読んで、パーソナリティはこれで本当にうまく統合されたといえるのか、長じて訪れる息子の不条理な死を知った上で読んでいることもあって、どんどん不安になってしまう展開だった。この本がベストセラーになるとは、いったい何が共感を呼んだのか、いまだに高い評価を得ているのはどのあたりなのか、私には腑に落ちないのである。 |
| 岡康道、小田嶋隆 『人生2割がちょうどいい』(講談社) |
| ワタシとほぼ同世代、都立小石川高校の同級生の、CMプランナー岡とコラムニスト小田嶋の対談で、日経ビジネスオンラインに最初はコミュニケーション論としてスタートしたはずが、結局は紆余曲折をへた親友同士の四方山話が爆発。あの時代の都立高校の雰囲気を思い出させてくれるむちゃくちゃな大学受験の話や、会社勤めをやめるいきさつなど、大笑いしながら読んでいるが、とにかく破天荒な二人のあけすけなプライベート話が、結局はコミュニケーション論に落ち着いていくところが面白い。二人だけでもいくらでもしゃべりそうだが、要所で鋭い舵取りをするナビゲーターは誰かと思ったら清野由美だった。タイトルは、確かにそう言ってはいるのだけれど、ちょっといかにも人生論っぽくてどうかなと思うのだが。でもまあ、これを読んだおかげで相当気分が晴れたことは間違いない。 |
| 郷原信郎 『思考停止社会』(講談社現代新書) |
| コンプライアンス問題の第一人者といわれる著者の、「遵守」に蝕まれる日本と副題が付されたベストセラーを読んでみた。東大理学部出身で東京地検特捜部など法曹界を経て大学教授、弁護士という経歴。法律の専門家が世の中に大勢いるはずなのに、このような本を読むと、そういう人たちはいったいどうして、食品偽装や経済司法や年金不祥事や裁判員制度などに対して、世論形成に影響力がないのはなぜなのだろうか、と思う。著者は不二家問題ではTBSの捏造に厳しく抗議しているが、マスメディアの不祥事はもののみごとに誤魔化されてしまっている。途中のケーススタディを読んでいるうちは、ではどうすればよいのだろうかというところがなかなか見えないのだが、7章から終章にかけての論考は説得力がある。つまり、アメリカ的な法化社会化が、本来法に対する態度がまったく異なった日本に不用意に取り入れられていったために、無批判に法令遵守するという思考停止が起こっているのである。そしてここに、社会的規範の意義が立ち現われてくるのである。しかしそれにしてもマスメディアの構造的などうしようもなさが、なんともやっかいだ。 |
| ナンシー・クレス 『ベガーズ・イン・スペイン』(ハヤカワ文庫SF) |
| プロバビリティ3部作どうしようかなと思っていたらこの短篇集が出たので読んでみた。遺伝子改造で不眠となった人々をはじめ、ひとつひとつのアイデア自体にはそれほど目新しさはないが、構成と書き込みが緻密なのと、人間(だけではないが)の罪深さや愚かさがねっとりと絡み付いていて、どれもなかなか読み応えがある。さてこれで、プロバビリティ3部作の面白さは十分に期待できることが分かった。あとは体力を付けておかなくては。 |
| 石田誠 『公務員がクビになる日』(都政新報社) |
| これは普通の人はあまり目にする機会のない本だと思うのだが、自治労都庁職の人が書いた「事業譲渡と雇用保護法(TUPE)」の研究書である。ワタシがなぜこんな本を読んだのかといえば、小さな労働組合の幹部を引き受けざるを得なかったからである。他のところにも書いたが、いきなりここを見た人が勘違いしないように説明しておくと、ワタシの勤め先が唐突に法人化され、いきなり任期制が導入されるなど強引にむちゃくちゃやられ放題になり、いっぽうでそれまでちんたらと惰性で公務員の組合員だったのが、急に本体から切り離され、正真正銘の労働組合を作らなければならなくなったものの、それ以前のX政党系とY政党系の組合員を、とりあえず分裂させないために、ノンポリのワタシが副委員長とか委員長とか、まあそういうことになったのである。X党もY党もついでにZ党も何も大嫌いなだけなのに、しんどい話である。それで、まあこういうことをやられ放題でよいのか!と戦おうとしたけど・・・壁が厚いんですねこれが。あまり内情はばらせないけど、公務員であれ大企業であれ、組合は多かれ少なかれ御用組合「的」なところはあって、そういうやり取りはホントいやですねっ!!! 閑話休題。ワタシらも要するに「イヤだ」といったらどうなるのか、というと、それは事業所がなくなるんだから分限免職でしょ、という理屈なのである。もちろん事業所はあるのだが、法人化されるだけで、その理屈が通るか、と専門家に聞いても、そりゃ通らないよ、というのに、通っちゃったのだ! で、本書では海外の事例に基づいて、規制緩和で民間に事業譲渡されても雇用は確保することを、制度的に確立しようという提案で、関連資料も豊富で小冊子だが参考になる。でもそうはいかないいんだよな、実際には。交渉でなあなあで、まあクビにできるようにはなってるけどしないからさ、そこんとこ酌んでもらって、ネ・・・という感じでしょうか。そういうスタイルはきっと変わらない。結果的に、無茶な自治体や中小の民間は救われないままだろう。 |
| 西原理恵子 『この世でいちばん大事な「カネ」の話』(理論社) |
| 理論社の意欲的なシリーズ、よりみちパンセの一冊で、中学生以上が対象だから、全部振り仮名がついて、文章もかなり練られているが、中味はいつもとかわらない西原である。子ども時代から大人になる頃の「貧乏」がどんなことなのか、リアルにわかる。ギャンブルやセックスのことも生々しく、説得力がある。そういえば養護学校の性教育にクレームをつけた教委や議員が地裁で負けたが、これは人権とか不当介入とかいう問題ではなくて、たとえば発達遅滞の子には即物的な教え方をしないと、健常の子と同じ性教育は通用しないという、ごく当たり前の文脈を読まない連中は救いようがないという話である。だから本書の中に出てくるギャンブルやセックスは、格好の教育になる。最後は鴨ちゃんとの物語になる。要は、愛の物語である。ぜひ子どもたちに読ませたい。 |
| 山口仲美 『ちんちん千鳥のなく声は』(講談社学術文庫) |
| カラスの鳴声は「カアカア」だけではない。全国各地にさまざまな鳴声がある。野口雨情の「七つの子」で「かわい、かわいと啼くんだよ」というのも、兵庫や広島などではそういう声で聞かれている。このような話を、方言や古典から丹念に拾い上げながら、鳥の声を愛でる人と、鳥とのかかわりに気づかせてくれる。ウグイスやホトトギスやカリの名が鳴声からきたとか、かわいいトラツグミの呼び名のヌエがなぜ不吉な鳥になってしまったかとか、面白い話がいっぱいで、別に鳥が好きでなくてもついつい引き込まれる。 |
| S・フォン・ロー 文、T・クロケンブリンク 絵 『小さい"っ"が消えた日』(三修社) |
| 日本好きで20歳から日本語を習い、上智大学を卒業、現在は証券会社に勤める著者が書いた、日本語についての御伽噺。五十音村で「あ」や「の」や「し」さんたちが自慢話をする。そして、小さい「っ」は音がないのでいちばんえらくないといわれて、家出をしてしまう。そのとたんに、日本語がおかしくなってしまう。かわいい挿絵は絵が達者で日本の木版画好きの生物学者。日本語を学んだ外国人らしいひらめきから生まれた、かわいらしいお話で、絶版後も人気がじわじわと高まり、復刊されたもの。自分の母国語の面白さに、外国人から指摘されて気づくのは、決して情けないわけではなくて、ありがたいことである。ほのぼのとした楽しいお話。 |
| 池田清彦 『がんばらない生き方』(中経出版) |
| 著者の『さよならダーウィニズム』は面白かったが、『正しく生きるとはどういうことか』でちょっと躓いていた。今度はどうか。著者名の横にわざわざ〈構造主義生物学者〉とあるのと、たまたま開いたページがT細胞の「無駄」の話で、「無駄」がないと生き残れないという生物の仕組みから、無駄をなくそうとする社会や組織のマチガイを指摘するあたりで、面白そうと買ってみたが、面白いのはそこだけだった。あとはほとんど使い古された軽い話で「がんばらなくてよい」という聞き飽きたテーマ。身の回りの世間話のレベルでガッカリだった。〈構造主義生物学者〉独自の視点や、せめてT細胞の話のような〈構造主義生物学者〉ならではのエピソードが満載であれば楽しめるのだが。それにしてもよほど「正義」が嫌いなのだろうなと思わせるが、あらかじめ持っている「正義」の概念を前提として話を進めるので、その「正義」の概念そのものの批判に向かわないところがあまりにも薄い。執筆とあるが流れの軽さと(笑)の多用から、やはり聞き書きなのだろうか。 |
| ジョー・ホールドマン 『ヘミングウェイごっこ』(ハヤカワ文庫SF) |
| これはおもしろかった。言わずと知れた『終わりなき戦い』の著者は、ヘミングウェイ研究者でもあって、その趣味が高じて気の利いたパラレルワールドSFを仕上げてしまったという趣である。話のきっかけは、大学で文学を教えるヘミングウェイ・マニアが、詐欺師に声をかけられて、失われたヘミングウェイの初期原稿を偽作しようとすることである。そのための資料やタイプライター探しなどにからむ蘊蓄がまず面白くて引き込まれるのだが、このヘミングウェイの原稿紛失が、並行宇宙的にみれば、宇宙の存続にかかわる重要な出来事であるという設定で、とんでもない方向に話は展開する。犯罪サスペンスとしての描写も凝っていて、著者が通り一遍のつくりにしたくなかったであろう思いが伝わってくる。 |
| 土野研治 『心ひらくピアノ』(春秋社) |
| 土の字は正しくは右上に点がつきます。著者は長らく養護学校に勤め、声楽家としても活躍しながら、音楽療法の研究を続けてこられた。それはすごいことで、身体を悪くされたこともあるほど、たいへんな労力のいることだし、すべてに熱意を持って取り組むことは並大抵ではない。もちろん本書の本筋は自閉症者の理樹君にピアノレッスンを続けた14年間の記録なのだが、並行して著者の14年間にも触れられるから、その大変さがわかる。もちろん本筋のほうも、著者の誠実さがひしひしと伝わってくる。自閉症者といっても、一人一人、症状の違いには大きな幅がある。音楽療法といっても、自閉症にたいしてはこう、というマニュアルがあるわけでもない。著者は一人の青年とともにピアノに向かい、試行錯誤を繰り返す。詳細な観察、譜例、エピソードの記録が綴られる。感動的であるが、それは誠実な記録によってのみ生まれる種類のものである。今のところ、自閉症が「治る」ということはない。その上で、音楽療法を含めて、自閉症者のQOLの向上にみな取り組んでいるのである。その現実に気付かされる重みを通じて、折々の気づきが音楽療法の手立てにつながる可能性をあらわにしていく。 |
| ジェフ・ライマン 『エア』(早川書房) |
| いろいろ受賞した長編SFだが、私はこれ、読み始めて間もなく、いったん頓挫していた。再挑戦して読み切ったが、なんとも奇妙な小説である。舞台は中国辺境の山岳地帯、少数民族と異なった宗教と中国との微妙な関係の中にぶら下がったような地域だ。そこの村で暮らす貧しい農民の主婦が主人公のメイである。村にも例外なく、人々の脳をネットワーク化するテクノロジーがやってくる。その実験中に、事故死した村の老婆の意識が自分の意識の中に一体化する。一方で、村のファッションアドバイザーをしていた彼女は、ネットワークビジネスにも乗り出すことになるが、そこに夫婦の不和やら新旧世代の対立やら村の有力者のさや当てやらがごちゃごちゃとからみつき、一方で愛人の子供を胃に(!)身ごもり、さらに一体化された老婆の意識が次第に彼女を支配し、また迫りくる洪水の危機を村人に訴えるが信用されず・・・とまあ、これでもかというほどの構成要素が詰め込まれている。訳者あとがきにもあるが、まずはこのヒロインに感情移入するのがなかなか難しい。流れに乗ってしまえば、後は次々と起こるエピソードの奔流に巻き込まれていくばかりなのだが、男女や親子の感情の軋轢が次々と並行して起こるのと、民族文化とテクノロジーの強引な接合が渦巻くので、読み手としての物語の中の居心地の悪さは格別である。というのは面白くないというのとは明らかに違う。たぶん落ち着く場所を求めて読み進んでいく。でも決して落ち着かない。翻訳では『夢の終りに・・・』があって私も確か買い求めていたはずなのだが、読んだ記憶がないのは、途中放棄したのかもしれない。後で探しだして、再挑戦したいものだと思っている。 |


