

 バックナンバー(07年4月〜6月)
バックナンバー(07年4月〜6月)
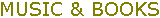
| >HOME >BOOKS |
| ベン・シャーン絵・アーサー・ビナード構成・文 『ここが家だ ベン・シャーンの第五福竜丸』(集英社) |
| サッコ&ヴァンゼッティを取り上げて以来社会派の重厚な連作で知られるベン・シャーンであるが、我々にはなんと言っても第五福竜丸 Lucky Dragon シリーズで馴染み深い画家である。この絵本は詩人のアーサー・ビナードがシャーンの連作を構成したものである。もともと絵が語っているメッセージは明快で(しかもシャーンは敢えて久保山にメッセージを持たせるという禁じ手すら用いているーーーただしこの作品は絵本の本編には使われていない)、文章が加わることでアートとしてもメッセージとしてもそれ自体に何か新しい創造性が感じられるのかどうかとなると、私には疑問である。むしろ冗長に感じる。しかし、メディアとして「絵本」という形態に再構成されたこと、そこには確かに新しい価値、可能性が見出される。絵本を手に取ることでこのシリーズの存在を知る人は増えるだろうし、そこからシャーンのメッセージはさらに広がるだろう。それでもなお、映画のセリフの無いシーンに字幕や吹き替えをつけてしまうおせっかいのようなむず痒さをどうしてもおぼえてしまうのだが。 |
| 武田徹 『「核」論 ― 鉄腕アトムと原発事故のあいだ』(中公文庫) |
|
初代防衛「大臣」が「しょうがない」発言で辞任した。原爆投下について語るべきポイントは三つあったはずだ。ひとつは、民間人の無差別大量殺戮という意味では、東京大空襲もふくめてそもそも許されないということ。これは勝ち負けにかかわらず負うべき責めは負うべきである。そのうえで、さらに核兵器の実使用という空前絶後の事態であるということ。核廃絶の主張は、被爆国として当然である。そして最後に、戦況判断をまともにつけられず、ポツダム宣言の受諾にモタモタしているうちに、ソ連の侵攻と原爆投下という事態を(いずれも国際的に正当化できるとはいえない行為であるにせよ)招いて多大の犠牲を国民に強いた帝国指導者層の無能無責任。 「しょうがない」発言があまりにも長引くと、単純に選挙に響くからということだろうが、さっさと選挙を済ませて改憲に突っ走りたい向きは戦争責任論に言及が広がることを嫌ってさっさと幕を引きたかっただろう。マスメディアの取り上げ方の深みの無さも情けない気はするが、これはまあ言っても何をいまさら、ではある。 「核」は「平和利用」も含めてひとつの巨大な思惑のフィールドである。政策文書、かかわりのある人物、現地取材、さまざまな観点から「核」の核心に迫ろうとすることで、ようやくその広がりが見えてくることを思い知らせてくれる一冊である。原発は過疎立地に作らなければならないことになっているので、原発の見返りの過疎「対策」は矛盾している(そして実際に成功しない)ということなど、気づかなかったことを気づかせてくれるというよりは、その気になればいくらでも気づけたはずのことから、自分自身が目をそらせていたことに気づかされるのである。 |
| 水島広子 『自分でできる対人関係療法』(創元社) |
| 対人関係療法というと一般名詞のようだが Interpersonal Psychotherapy(IPT)というブリーフセラピーの一流派である。短期療法らしくセラピーの手順も明確であり、効果の研究も揃っていて、うつ病をはじめ対人関係に起因しうるさまざまな障害に有効である。本書は、日本人のクライアントが立たされやすいであろう、十分に豊富な事例を挙げながら、それに対応したセラピーの技法を、順を追ってアレンジしてある。著者の柔らかい、しかし明快な語り口が、自分でできるというタイトルを偽りのないものにしている。 |
|
ダン・シモンズ 『イリアム』(早川書房)
ダン・シモンズ 『オリュンポス(上)・(下)』(早川書房) |
| 去年の夏に『イリアム』を読みそこなっているうちに、続編の『オリュンポス』上下巻が出てしまった。だいたい贔屓の作家の翻訳ものは続編の翻訳をじりじりと待っている状態になるものなのに、今回は何とも贅沢な一気読みになった。さて、この超大作、どこから語るべきなのか。まず、よくわからないがホメロスの「イリアス」の世界が現前していて、それを観察しているというかさせられている古典文学の博士が出てくる。それから、なんだかずいぶんと様変わりして人口も少な気で、なによりも文字すら失ってしまったが高度なテクノロジーには支えられているというか囲い込まれている人類が出てくる。さらに、小惑星や外惑星の世界から、妙に文学に造詣の深いヒューマノイド(でもないのだが)みたいなものたちがやってくる。・・・これでは何だかわかりませんね。でも読み始めた時は、本当に何だかわからないのだ。これらのエピソードが並行して進んでいくうちに、ギリシア神話の神々やシェークスピア文学のキャラクターに起源する存在が絡み合い、風前のともしびの人類の存続がかかってくる。なにせスケールがでかすぎるので、手短にストーリーを紹介するのが難しい。破綻も少なくないらしいのだが、正直、読んでいて何度もわからなくなるワタシには関係ない。戦闘シーンの描写の迫力は言うまでもないが、それが文学の蘊蓄と量子論のアイデアが縦横無尽に飛び交う世界に展開するので、圧倒されっぱなし、恍惚である。溢れるSFアイデアのめまぐるしさも相変わらずの魅力で、アキレウスが特異点だとか、エッフェルバーンだとかっていう小ワザにもうならされっぱなし。セテボスの不気味さ、キャリバンは『ハイペリオン』のシュライクを思わせるキャリバンの凄惨さなど、作者の持ち味がよくにじみ出る異形のキャラクターも多数。万人向けとは言い難いが、海外SFファンでこれを読まない人はいないだろう、という定番には違いない。もしかすると、『ハイペリオン』にとっての『エンディミオン』のように、「後半」が書かれるかもしれないとか。すごいことになりそうだ。 |
| 中田基昭 『教育の現象学』(川島書店) |
|
教育の世界はいつも取り残されている。政治に取り残され(票にならない)、経済に取り残され(金にならないばかりか、金がかかる)、学問に取り残される(いっこうにまともな理論にならない)。受験産業は儲かっているようだが、公立のみならず私立学校も一部を除けばあまり儲かっているようには見えなくて、それも結局人件費がどうしても経費の大部分を占めてしまうから、仕方がないのである。競争原理を持ち込めば帰結がどうなるかというのは、単純な問題だろう。 何が言いたいのかというと、教育に関する言説が飛び交っているけれども、教育の研究というのはもともと、教えるものと教わるものとの関係についての研究がまずあったうえでの話である、ということである。現象学的に教育を、というか教室や児童生徒と教師たちを見るところにいれば、遠い議論はすべて空しいが、いっぽうで粗末なゲンバ主義に陥らないためには、教師にも研究者にもよって立つべき豊かな理論の素養と実際的な応用力は必要だろう。そういう意味で本書はじめ東大の現象学的教育学の仕事は重要である。 |
| デビッド・D・バーンズ 『いやな気分よさようなら』(星和書店) |
|
先日、通勤電車の中でサラリーマンらしき若者が手書きのレポートを読んでいる。目の前なのでどうしても見てしまうのだが、「自分が変われば相手も変わる」とかなんとか、新人研修のノートなのだろうか、自分を奮い立たせるためのスローガンの羅列のようだった。丸暗記でもさせられているのだろうか。しかし彼はそれをやけに目立つディズニーキャラクタのクリアファイルに入れていたのだが、普通の社会人としてはまずそこから変えたほうがよくはないか、ちょっと気になったのである。 気の持ちようとか、考え方次第とか、よく言われるわりに、どうやってそれを変えるのか、具体的な方法を私たちは知らないし、たいていの場合は「無責任なこと言って・・・」という受け止め方になるだろう。そうでなければ、あやしい販売会社の新人特訓のような「洗脳」か、あやしい宗教団体の「マインドコントロール」のようになってしまう。認知療法は、そのどれでもないが、しかし認知(気といってもよいし、考え方といってもよいが)を変えることによって、実際にうつを良くすることもできるのである。認知療法は考え方を変えるのに合理的で意識的な方法を使うところが特徴である。つまり誰かから操作されたり強制されるのではなく、また無理に暗示にかけたりもしないのである。 本書は、特に抑うつの克服に焦点を当て、理論的な根拠についてもかなり詳しく触れながら、語り口調でつづられ、その効果も確かめられている。しかも、生化学や薬物療法についても、最後にかなりのページを割いて扱っていて(こっちは横書きになるのも変わりダネ)、認知療法のみならず抑うつについての幅広い病理・薬理のガイドにもなっている。結果的に4000円近い分厚の本になって、気軽に手に取れる本ではなくなっているが、特に認知療法をまだ一般的に受ける機会が少ないと思われる日本の患者さんにとっては、丁寧に読むだけの価値はある。 |
| ジョン・R・サール 『マインド 心の哲学』(朝日出版社) |
|
正直に告白してしまうと、心の哲学にはあまり関心がない。なんだかみんなチャーマーズあたりに煽られているだけなんじゃないの、という気がしないでもない。哲学的ゾンビなんて心身二元論の戯画に過ぎないように思うし、意識が必要ないのに何のためにあるかという問いも、意識(べつにクオリアでもいいんだけど)を物理的現象と切り離して問う意味がそもそも全く分からない。もともと哲学のたとえ話は、面白いだけで、いつも雑すぎて納得したためしがないのだが、こういう寓話を考えることが楽しいだけではなく、その難点や疑問点を限りなく議論のネタにしていけるようなタイプでないと、哲学にのめりこむことは難しいのだろうか。物理学の前提が禁欲的だからといって、それが意識の問題を解決しないというのは、自然科学の成果を買いかぶりすぎているだけじゃないのか。まだまだわからないことだらけの世界において、突出して意識やクオリアを扱いたい気分はわかるけれども・・・。 ・・・などとほざいている私のような人はむしろ、いきなり部厚いとはいえ、問題をよく整理してあるこのサールの名著に触れるとよいかもしれない。諸学説(といえるかどうかわからないものも含まれているが)をていねいになぞって説明し、対比させ、おおむね納得のいく整理をしていると感じられる。なにはともあれ、本書の最終章を読んで、「当たり前じゃん?」と思う人は、心の哲学に深入りする必要はまったく感じないばかりか、心の哲学者(という言い方があるかないかはわからないが)たちの多くとはあまり親交を結びたいとは思わないであろう。 |
| クリストファー・プリースト 『双生児』(早川書房) |
| SFではさんざん使いまわされたテーマであるパラレルワールドもの、しかもこれもまたよくある第二次大戦前後の時代背景、である。このような設定はいまどきよほどの自信がなければ使えないだろう。まず凄みを感じさせるのは、時代背景を彩る資料のリアリティ。いつもの端正な語り口がさらに効果的。真贋虚実入り乱れて、そこに主人公である双生児が組み合わさり、しかも作中作の構成が伏線になって重層性をさらに増して、しかし展開が速く物語として面白いのでほとんどいっきに読み終わってしまう。面白すぎます。 |
| 池谷裕二 『進化しすぎた脳』(講談社ブルーバックス) |
| ニューヨークの日本人高校生を対象に、若手の脳科学者が、質疑応答をしながら、脳について語る。大変分かりやすいし、高校生の質問も当を得ていて、読み手の疑問にもうまく対応している。クオリアの説明なんて、これ一番よく分かるんじゃないか。さらに新書版に際して、著者が所属する東大薬理の学生相手に「僕たちはなぜ脳科学を研究するのか」と題した章を加えていて、これが別の視点からの研究ガイドになっていて面白い。中高生が読めば格好の進路教材にもなる。 |
| P.G.ウッドハウス『ジーヴスと朝のよろこび』(国書刊行会) |
| 今回も毎度おなじみのドタバタで事態がどんどんねじれていき、いよいよというところでジーヴスの働きによって意外な方向でほどけていくパターン。主人公の頓馬ぶり、まさに類は友を呼ぶ友人たちに、きついお嬢様方のリードぶりがいつも面白い。ところで、あとがきによると、この作品は、第二次大戦中ドイツにとらえられ、のちにイギリスで非難される対英プロパガンダのラジオ放送に出演させられる時期をはさんで執筆されている。ラジオ放送はむしろ非常に皮肉めいた内容で、むしろじつに巧妙にドイツに協力しているフリをしながらひねった内容になっているのだが、放送自体を聴いてもいない文壇や論壇から集中砲火を浴びることになってしまったらしい。ドロシー・セイヤーズのように冷静な見方が出来る人物はなかなかいないようだとは考えさせられるが、かなりひどい非難をしたA.A.ミルンにはこれまた皮肉な意趣返しは作品の中でしているにせよ、ミルンの作品そのものの価値は評価し続けたというウッドハウスの器にも感心させられる。 |
| 若島正編 『エソルド座の怪人』(早川書房) |
| 異色作家短編集20は世界編のアンソロジー。不条理で突き放すような作品、フォークロア風ほら話など好みの作品が並ぶ。ワタシは「死んだバイオリン弾き」が一番気に入った。しかしタイトル作が一番分からない。 |
| 工藤庸子 『宗教 vs. 国家 フランス〈政教分離〉と市民の誕生』(講談社現代新書) |
| フランスの公立高校でヘジャブの着用が禁じられた問題は、うっかりするとフランスでも公然と反イスラムの風潮が強まってきたかと思いがちであるが、仮にそのような意識を持つものが増えているとしても、フランス革命に前後する長い混乱期に、公立学校がいかにして宗教からの独立を果たし、それを保ち続けようとしてきたかといういきさつを知れば、ずっと奥の深い問題であると考えざるを得ない。イラク戦争においても独自の立場を貫き続け、マグレブ諸国との長いつながりとそれに由来する移民を抱え、確かに右派勢力の伸張など先進国に共通の傾向もありながら、フランス人はおそらくこの闘いとった自由を何とかして、バランスをとりながら、守ろうとするだろう。翻って、「宗教」教育を都合よく口にするこの国のトップたちのあまりの軽さに向き合う時のむなしさは大きい。 |
| 斎藤英喜 『読み替えられた日本神話』(講談社現代新書) |
| 幅広く神話伝承を構造分析し読み解く部分はともかく、興味深いのは平安時代の朝廷の儒学者たちによる日本紀講のいきさつや、鎌倉時代の歌学者、神官、僧侶とさまざまな立場からの中世日本紀の驚くべき豊饒さには、目をみはるばかりだ。これが幕末から近代にかけて国体論に収束していく日本神話のいわば「正統」へと、やせ衰えていく様子はいかにも無残に映る。「日本神話」をきちんと学ぶことは重要である。右も左もこの日本人の豊かな想像力と知性・感性の魅力を忘れている。 |
| 内藤朝雄 『いじめと現代社会』(双風社) |
|
親が転勤族だったために、私は小学校3つ、中学校2つに通った。一番きつかったのは、都下の非常にリベラルな小規模校から、近県の管理教育を目指す新設校に移った小学校6年生のときである。まだ右も左も分からない、転校初日の始業式前に、体育館に集合がかけられ、横一列に並んで雑巾がけさせられたのにはいきなりのカルチャーショックだった。まあ、一年間だけだったのと、担任がそういう流れに乗れないというか乗るつもりのないおばちゃん先生にかわいがってもらったからである。アレがバリバリやる気丸出しの若い体育会系教師だったら・・・人生変わっていたかもしれない。 著者は愛知の新設高校でバリバリの管理教育を経験、中退したという経歴をもつ社会学者である。いじめや学校への考察は、そういう経験もあって、リアリティがある。実は著者の提言はいたってシンプルで、群れてつつきあう学級制度からの解放は、子どものみならず教師にも必要だ。朝日新聞で著名人によるいじめに対する提言みたいなのが連載されていたが、ノーベル賞受賞学者のとんちんかんさなどまたぞろこれで新聞社の良心の体裁づくりの記事に引っ張り出される素人も気の毒だよななどと思いつつ、さかなクンの水槽の中の魚の群れの話は一番説得力があった。狭い水槽でつつかれている個体を出してやると、他の個体がつつかれるようになる。さかなクンも著者も同じことを言っているのだ。常日頃学者の書くものに幻覚性じゃないや厳格性を求めるワタシとしては不本意だが、直感的に言い切ってしまうが、これはたぶん、正しいぞ。 |
| 布施克彦 『昭和33年』(ちくま新書) |
|
もちろん私はこのタイトルに惹かれて、この本を買ったのである。私は昭和33年生まれ。映画の三丁目の夕日も見たし、東京タワーには親しみがあるし、自分の生まれ年が話題になること自体、率直にうれしい。当然、昭和33年がどんな年だったか、記憶にはないわけだが、親の話や自分でも調べたりして、それなりに知っている。そうしたことどもが、どんなふうに料理されているか、と思って、楽しみに読み始めたのだが、見事にだまされた。これ・・・何の本なの?
著者は、昭和33年の朝日新聞を切り口にしているのだが、そこに日本人の「昔はよかった症候群」や「未来心配性」があるという日本人論に結びつけるのである。海外体験者がちっちゃい経験主義で物をいう日本人論が溢れているけれども、コレも何のことはない、非常に薄っぺらなアメリカ人、中国人などの分析になっていない分析で、それに対して日本人はこうだ、という展開が雑そのもの。ああまたこれかい、と、もうこの時点でイライラしてくる。「この一年間の朝日新聞縮刷版を、何度も読んでみた」。つまり、まず新聞の記事から「未来心配性」を引っ張り出してきたようだが、はたして記事の分析をどのように行ったのだろうか。「未来心配性」を支持するのに都合のよい記事をピックアップしているだけではないという根拠が全く示されていない。しかしまあ、もし著者の言うとおりだったとする。つまり、「未来心配性」があるとする。この場合、 (1)未来心配性であったにもかかわらず、未来は(少なくとも33年よりは)「よく」なった。 (2)未来心配性であったからこそ、未来は(少なくとも33年よりは)「よく」なった。 のどちらかである。だから、未来を心配するのはやめよう、という主張の根拠にはどっちにしてもならないし、もし(2)だったら、未来心配性を捨てたらやばいでしょう! 昭和33年は決して良い年ではなかった、というのは、まあ当たり前である。地方出身のサラリーマン家庭であった我が家もまだまだ生活は豊かではなかったのであって、あの映画でも決して33年を美化して描いていたとは思わない。しかし、著者はそのことを「今は悪くない」ということを言うための比較対象として取り上げているので、まずそのあたりからズレがひどくなってくる。だからあ、そんなに昭和33年が良かったわけないじゃん、とこっちは思っているので、どんどんしらけてくるのである。たとえば「集団就職とフリーターとどっちが厳しい?」といった調子で、もともと比較しようのないものを比較しているわけだがそれはおくとしても、そんなもん口減らしの集団就職と、ちょっと働けばとりあえず食えているフリーター、厳しいったら集団就職に決まっているじゃないか。 万事がこの調子で進んで、ついに後半はエブリシングおーけー!と煽りまくりみたいな展開に・・・。あらためて著者経歴を見ると、おっとすみません、ついつい団塊世代論に走りそうな1947年生まれ。商社マンで世界を駆け巡った後はNPOで・・・自分で言っているからいいでしょう、世代でくくるのは嫌だが、「団塊世代」のコーディネーターみたいなことをやっているようだ。元気が欲しい人、暗い雰囲気でいたくない人には、力の出る本かもしれないし、そういう人は著者のNPOにも参加したらよいだろう。楽観的であることはじつはワタシも大事なことだと思っているので、そういう意味では共感がもててもよさそうなものだが、それがどうしても共感できないのは、根拠らしい根拠がないのに、昭和33年を出しにして根拠めいた対照に使っているからだろうか。そして「今は悪い」という意識にそんなに意味があるように思えないのと同じくらい「今は悪くない」という意識にもたいした意味があるように思えないからだろうか。 |
| 吾妻ひでお 『逃亡日記』(日本文芸社) |
| かつての失踪先を訪ねるグラビアつきのインタビュー本。これまであらかた語られてきたことの確認めいた内容ではあるのだが、あらためてまとまった形でインタビューされているので、楽しく読んだ。奥様やお嬢様のコメントがあるのも楽しい。 |


