

 バックナンバー(07年1月~3月)
バックナンバー(07年1月~3月)
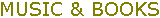
| >HOME >BOOKS |
| 工藤隆 『古事記の起源』(中公新書) |
| 古事記の文献学的研究は、もはや飽和状態に達している。無文字時代の口承伝説を編集したものである以上、その元になった神話は知りようがない。しかし、中国の少数民族には、今でもかろうじて残存している「歌垣」がある。著者はみずから調査を繰り返し、現存する歌垣と古事記以前の生きた神話とを繋ぐ糸を手繰り合わせる。その試みのいくつかには深い説得力があるし、いくつかはそれをもってしても弱い仮設にとどまってはいるが、これらの糸をさらに撚り合わせることによって、これまで見えてこなかった古事記の輪郭が、よりはっきりと見えてくる。日本の古層は何か、新しい視野が開ける。 |
| 内海健 『うつ病新時代 双極Ⅱ型障害という病』(勉誠出版) |
| うつ病の(あえて言えば)氾濫のなかで、じつは思った以上に多彩な病像があり、薬の効きかたもそれほど単純なものではないことが明らかになってきて、さまざまな視点が示されている。「とりあえずうつ病→SSRIが効く」というような単純な図式の遷延にはそろそろ歯止めがかかってきただろうか。本書は、双極Ⅱ型障害に注目、患者が示す軽躁に注意を促している。SSRIによる行動化や、境界性パーソナリティ障害への安易な結びつけなど、問題は山積しているようである。というのもDSMの普及と精神病理学の退潮という、根の深い問題状況を指摘するあとがきにも注目。 |
| 橋元淳一郎 『時間はどこで生まれるのか』(集英社新書) |
| これは実に分かりやすかった。物理学者にしてSF作家、予備校講師も務めるだけあって、分かりやすさは格別。たとえば非因果的領域など図解で一発で分かる。哲学的時間論にも詳しいので、私などは本書で改めてカントの天才と偉大を再認識したりしている。過去や未来は生命の意思によって生じるのである。ここから価値論を再出発させることもできるだろう。 |
| 千葉望 『よみがえるおっぱい 義肢装具士・中村俊郎の挑戦』(海拓社) |
| 以前に雑誌記事で見かけて気になっていたのだが、たまたま見かけて読んでみた。マスメディアでも何度か取り上げられていたようだ。失われた体の部分を、さまざまな工夫で再現していく。その技術もさることながら、中村の人柄とその歩みが興味深い。衰退する石見銀山の地に生まれ、苦学してアメリカにも留学、そして帰郷して起業、優れた技術を生かして会社を発展させるだけでなく、赤字を出しても乳房の再現などをメディカルアートと名づけて研究し、またモンゴルの少年のために義足を作る。地元の振興にも大いに参画する。本書はそんな中村の人柄をよく引き出したルポルタージュである。 |
| ピーター・ディキンスン 『キングとジョーカー』(扶桑社ミステリー) |
| 今は亡きサンリオSF文庫、当時はかなり読んでいたはずだが、ディキンソン作品は記憶になく、読まなかったかもしれない。惜しいことをしたものである。この作品はそのうちのひとつで、待望の復刊ということになる。風変わりな推理小説はいかにもケンブリッジ出らしく、また児童小説も多く出版、こちらもずいぶんと翻訳されてきたらしい。本書は、架空のイギリス王室に起こる不気味ないたずらが、ついに殺人事件にまで発展し、思春期を迎えて揺れ動く王女ルイーズが、事件に巻き込まれながら成長していく物語。しかし、奇妙な読後感というか、読みながらすでに奇妙な感じがするのだが、重要な鍵でもあるのは王室の男女関係で、それをルイーズがひとつひとつ受け入れていくプロセスが描かれていることが、じつは非常に重要なのである。だから、推理小説としての面白さと同時に、児童文学者でもあるディキンソンの言いたいことがもっとあるのかもしれない、という感じもする。 |
| 岩田重則 『「お墓」の誕生』(岩波新書) |
| 本来輪廻と解脱のなかに置かれたはずの仏教的な生/死が、日本において祖先崇拝と並立したのは、中国仏教が儒教の影響を強く受けたことからくると聞いていたが、本書を読むと、民俗的にも方形の墓石を先祖代々の墓とする習いは江戸中盤以降からということである。その事情はむしろ江戸時代の檀家制度にあると考えられるが、それでもごく最近まで多彩な死者祭祀が行われ、その名残は今でも見られることから、死生観の豊かさ深さに気づかされる。柳田民俗学の不備を問い、また現代の常識にもとらわれず、地道な調査から今日あるところの規格化された「お墓」への道のりを明らかにする書である。靖国も規格化の目論見の中にあることに気づかされる。 |
| サマー 『姉ちゃんの詩集』(講談社) |
| 妻が楽しみにしている『えらいところに嫁いでしまった』とか、長男が(小西真奈美が見られるので?)楽しみにしている『キラキラ研修医』とか、ワタシはドキドキしてとても見ていられない『今週、妻が浮気します』とか、ちょっと気になるテレビドラマがネットやブログ発であると後から知ることが多くなったこのごろ。この『姉ちゃんの詩集』は、高校生の姉が小学生や中学生だったころに書いていた詩を、弟がこっそりとネットにアップしたらたいへんな評判になって、ついに本になってしまったというもの。こそっとアップしているところから、姉ちゃんに白状するあたりまで、リアルタイムなネット上でのやり取りがないのが物足りないという話もあるが(その前後の家族の会話がまた面白かったりする)、コレが気に入ったら検索して読めばよし。とにかくこの詩はすごいよ。子どもならではの発想や思春期特有の動揺なんてものではない。駆け巡るような想像、家族や学校生活のリアリズム、誰でも知っていること感じていることなのに言葉に出そうとしないことなどが、誰も思いつかないコトバがつぎつぎ芽吹いて実をむすんでいく。コトバのもぐらたたきみたいな気分になる。予測もつかないところからコトバが顔を出して、あーやられたという楽しさ。詩を読むなんてことをしばらくやっていないワタシも、ついのめりこんでしまった。詩は引用したら丸ごとになってしまうからやめておきますが、これゼッタイ面白いよ、と無条件に人に薦めてしまいそうになる久々の一冊でした。 |
|
P.G.ウッドハウス 『サンキュー、ジーヴス』(国書刊行会)
P.G.ウッドハウス 『エムズワース卿の受難録』(文芸春秋) |
| 毎度おなじみウッドハウスのジーブスモノ、いつも疲れたときにお世話になっているが、今度もタイミングよく翻訳がでた。木ばかり見て森がまったく見えなかったり、本末転倒も行き着くところまで行ってしまう主人公やそのお仲間、扱いなれた執事ととにかく活動的で魅力的なお嬢様方、というのがいつもの配役で、今回も長編だが期待にたがわず一気に読み終える面白さだった。一方、エムズワース卿のほうも、年季が入っている分スケールアップ。豚の肥立ちや南瓜のできばえに夢中になるほど、それを取り巻く人間関係がもつれていくドタバタぶり、こちらのシリーズももっと読みたいものだ。 |
| 三谷幸喜、清水ミチコ 『むかつく二人』(幻冬舎) |
| 三谷幸喜の対談の類は面白い。これはラジオ番組の再構成らしい。三谷の知識や嗜好の極端な偏りを清水が遠慮会釈なく増幅していく。『気まずい二人』ほどのスリルがないのは、清水が三谷の面白さを引き出しているからで、安心して読めるのはこちらになるだろう。間に挟まれる解説はなくもがなだが、ウンチクとしてイケるものもときどきある。 |
| 井沢元彦 『ユダヤ・キリスト・イスラム集中講座』(徳間文庫) |
| まえがきに「日本の教育体系の中に、宗教に関する基本的知識を得るという部分が非常にかけているという認識があったからです。これはみなさんも同感だと思います。」とある。これはイエスでもありノーでもある。以前、『ソフィーの世界』が話題になった時に思ったのだが、ちょっちょっ、オレの「倫理」の授業はコレより分かりやすいよ、ということだったし(ソフィーの世界、あれ読んだ人はほんとうに分かったのかな?)、この前書きを読んだ時にも、ちょっちょっ、「倫理」でも「現代社会」でもオレは宗教とは何かかなり基本から体系的に押さえているつもりだけど、と言いたくなる。しかしまあ、一般的には、実際あまりちゃんと教えていないのだろうか、という不安もあるので、ノーとは言い切れない気もするのだ。だからちょっと気弱になって、この本はお勧めしてしまう。読みやすい文章で、手軽な文庫本で、しかもこの本のミソは、オレの授業でも十分な(しつこい)概説部分よりも、キリスト教のテレビ伝道師、日本ユダヤ教団のラビ(トケイヤー氏)、イスラミックセンタージャパンの設立者の一人で建築家・大学教授にしてスーダン大使、というそれぞれの人々との対談が半分以上を占めているところである。もともと2004年の発行だが、本質的なところは古くなっていないと思う。宗教についてきちんと学ぶ機会がない(らしい)高校生にも薦めたい一冊。 |
|
上野正彦 『死体は語る』(文春文庫)
上野正彦 『ヒトは、こんなことで死んでしまうのか』(インデックス・コミュニケーションズ) |
| 東京都で長らく監察医として働いてきた著者の、ベストセラーとなった処女作が『死体は語る』である。変死者の検死が仕事だが、それは死者の人権を守る重要な仕事である。事故死と思われる死体から殺人の事実が解き明かされる。ドラマ化もされたらしい。それ以降著者は多作だが、本書にたんたんと綴られる死をめぐる奇談の数々に驚きながらも、いずれ劣らぬ不幸な死者たちの哀れに注がれる目線と語り口の真摯さには打たれる。『ヒトは、・・・』のほうは2004年の本。こちらもタイトルがなかなか気が利いている。プランクトンの話など補強されたものもあるにせよ、重複する内容が多いのも確かだが、安楽死をめぐる内容など、むしろ著者のヒューマニズムの一貫性に気づかされるところもある。 |
| コニー・ウィリス 『最後のウィネベーゴ』(河出書房新社) |
| 奇想コレクションからもついにウィリスのアンソロジーが出た。収録4編。またまたもったいないもったいないと思いながらも一気に読みきってしまった。それぞれの表向きのテーマはフェミニズム、タイムトリップ、ファーストコンタクト、動物愛護というところだが、これが読みはじめから煙にまかれながら、しかしどうしても先を読まずに入られなくなる誘惑に満ちている。そして表向きのテーマからは予想も付かなかったクライマックスになだれ込む展開の巧緻さ、そこにこめられた皮肉とユーモアと愛にあふれた、申し分ない傑作。 |
| 新藤健一 『疑惑のアングル』(平凡社) |
| 報道写真家である著者が、実際の取材体験と、そこから過去の問題を掘り起こしての検証を組み合わせながら、写真にとどまらず報道の実態と課題を抉り出していく。キャパの「崩れ落ちる兵士」や南京虐殺の写真などが、戦争プロパガンダに利用され、あるいは最初からそのためにつくられてきたことで、過去の戦争の「事実」が操作されてきたことは明らかであるが、著者はそこからさらに現代の日本がいかに戦争の「真実」から目をそらされているかという問題提起につなげていく。最大の矛盾を背負わされている沖縄の現実は当然本書でも主要なテーマだが、しかしカバーにも使われている一枚の写真、六本木の一等地に堂々と存在する「麻布米軍へリポート基地」は、私たちが置かれている本当の立場を如実に物語っているというべきであろう。 |
| アンドリュー・ニューバーグほか 『脳はいかにして〈神〉を見るか』(PHP研究所) |
| 副題「宗教体験のブレイン・サイエンス」とあいまってなかなか魅力的なタイトル。監訳は茂木健一郎というのも期待させる。内容は前半は脳科学の概説、後半は宗教体験を脳科学のコトバでなぞっていく。概説は分かりやすく、日進月歩のこの分野に関して穏当な内容となっている。後半は進化の視点や宗教体験のリアリティに重きを置いているので、これまた穏当な展開となっている。ただこの内容であれば取り立てて脳科学のコトバを用いるほどのものでもないだろう。ニューバーグ、ダギリの二人の臨床家にライターのローズの三人の共著になっているところがミソ。あくまでも一般向きの本である。 |
| チャールズ・ストロス 『アイアン・サンライズ』(ハヤカワ文庫SF) |
| 『シンギュラリティ・スカイ』の続編で、あとがきにはこちらを先に読んでもよいとあるが、やはり順序どおり読んだほうがよいと思う。今回はエシャトンの存在感は物語的にはやや後退し、レイチェルの大活躍にウェンズデイも魅力的、まさに手に汗握る宇宙サスペンスになっているが、星系丸ごと滅ぼしてしまう話のデカさは相変わらずで、質量ともに重厚な読み応え。しかも最後の最後に・・・まだまだ続編が期待できます! |


