

 バックナンバー(07年7月~9月)
バックナンバー(07年7月~9月)
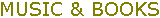
| >HOME >BOOKS |
| カート・ヴォネガット 『国のない男』(NHK出版) |
| ヴォネガット晩年のエッセイをまとめた、最後の一冊。非常に悔しいのだが、帯の太田光の言葉、「この本の全ての言葉を自分の頭にインプットしたいと思った。」という以上に、うまい感想が出てきそうにない。訳者あとがきすら、彼の言葉の引用を組み合わせるしかなかったのだろう。2007年4月、彼の逝去は惜しんでも惜しみきれない。良識とユーモアと怒りと悲しみを、ごく短い一つの文で、同時に、一瞬で、いくらでも、表現できる人なのだ。この本を読んで共感できる人とは、私は友達になれると思う。そうでなければ、・・・きっと向こうから先にご免こうむる、だろう。ああ、何を書いているのだろう、せめて一つ二つ、気に入ったところでも紹介すればよいではないか! とも思うが、しかしもし一文でも引用したら、もうあとはとめどなく引用したくなってしまうと思うのだ。だから、この辺でもうやめておく。読んでくださいな。 |
| ジェシカ・ウィリアムズ 『世界を見る目が変わる50の真実』(草思社) |
| イギリスのジャーナリストによるグローバル社会への警告。シンプルな数字で重要なトピックを語らせる手法は、数字の前提に気をつける必要はあるが、世界の現実を端的に知らせるうえで有効な手段だ。「世界にはいまも2700万人の奴隷がいる」、「世界の喫煙者の82%は発展途上国の国民」、「毎年、10の言語が消滅している」など、考えさせられることは山ほどある。国内的には「格差社会」が問題になりつつあるが、この国際的な格差を語る資格があるかどうか、よくよく考えたほうがよさそうである。最近、子どもにも分かるようにヴィジュアル版が出たということで、国際問題に関心を持つきっかけになればよいと思う。 |
| 加藤忠史 『躁うつ病とつきあう』(日本評論社) |
| 著者が精神科医として経験してきた、治療や教育や研究についての、随想集。患者との付き合いや、治療の失敗談、研究のいきさつなど、一見とりとめがないようでいて、臨床と教育と研究の日常が明かされていて、その誠実さにしばしば感心したり感動したりする。ミトコンドリア遺伝や脳内リチウム濃度の測定など、専門的なトピックから、躁うつ病の家族への思いや阪神淡路大震災の経験など、患者とのかかわりの機微まで、気負いなく書かれている。10年前の著作なので、研究や治療で現在との差はあるが、逆にここ10年、一般向けの話題がSSRIやSNRIなどにばかり偏っていたことにも思い至らせられる。ここにきて双極Ⅱ型がクローズアップされてきているなど、躁についても一般の理解が望まれる。 |
| P.G.ウッドハウス 『マリナー氏の冒険譚』(文芸春秋) |
| ジーヴスもの、エムズワース卿ものに続いて、マリナーものの選集である。シリーズと言ってもあとから冒頭にマリナーいわくの部分を加えたものもあるとのことで、ジーヴスものなどのようなまとまりはあまりないし、そうなるとマリナーいわくの部分はなくもがなと思わないでもない。ただこのシリーズで興味深いのは、ハリウッドの経験が随所に反映しているところで、ショウビジネスの世界を手玉にとってユーモアに仕立て上げているところが面白い。ナチスの放送問題で著者に理解を示したドロシーセイヤーズを持ち上げるコメントがさらりと入ってニヤリとさせられたり。 |
| 若島正編 『棄ててきた女』(早川書房) |
| 異色作家短篇集19はイギリス編アンソロジー。「時間の縫い目」、「パラダイス・ビーチ」、「詩神」などは、SFのフィールドで時間・空間テーマの作品として素直に読めるが、やはり奇妙な味としてはタイトル作や「何と冷たい小さな君の手よ」のようなミステリー調や「虎」のようなフォルクローレ調の作品を挙げたくなる。最後のどんでん返しによって驚かされるが、しかしそこでは謎の半分はまだ解決しないまま放り出され、結果的に謎は倍になるのだ。この取り残されたような感覚がクセになると、つい奇妙な味の短編を渉猟するようになるのだろう。 |
| ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア 『輝くもの天より墜ち』(ハヤカワ文庫SF) |
| ついに彼女の長編二作のうちの翻訳が読めるようになった。しかし若干の戸惑いを感じたのも正直なところである。かつて人類に虐待されたダミエム星を守る人々と、やってきた観光客、そこに紛れ込んだ刺客・・・という設定からすると、読みなれたあの作品この作品が浮かぶのだが、彼女の作風はまったくちがって、あたかも名探偵ポアロが登場人物を一堂に集めて謎解きを始めたような雰囲気なのである。繊細な異種族、失われた文明といった、いかにも彼女らしい設定も加わって、他の作家にはない独特の仕上がりになっている。残る長編のひとつもぜひ翻訳に期待。 |
| 村松秀 『論文捏造』(中公新書ラクレ) |
|
私も論文書きの端くれ(いやマジで端くれも超端くれだが)、分野的に一人か少人数で行う研究が多いので、論文捏造の状況も心理も構造も分からないではない。そういう私に忘れられないのが、修士論文のための研究に四苦八苦していたところに、指導教官がかけてくれた言葉である。「上手くいかんかったらなあ、なぜ上手くいかんかったかがちゃんと考察できればいいわけや」。そのとき、目からうろこが落ちる思いだったのが今でも忘れられないのだが、まあいまだに出来の悪い院生の修士論文に要求されるレベルでいるというのは研究者としては情けないわけだけれども、トップを走る研究者が期待に追い詰められていくプロセスは残酷だなあとも思う。とはいえ、シェーンのケースで言えば、彼はまだ若かったし、大学ではそれほど業績はなかったわけで、ベル研究所に入れてしまったことから始まって、有機物と金属薄膜というそれぞれ専門化が進んだ分野の組み合わせだったということ(私も倫理教育と統計学を組み合わせるとなかなかどちら側からも反応が微妙だったりするが、まあこれはどちらにも相手にされなかったということに過ぎない)など、いくつかの好条件が不幸にも揃ってしまったからこその出来事であったと思う。 しかし決定的だったのは、著者が指摘するように、シェーンは次第に自分が本当に成功していると思い込んで行ったのではないか、ということであろう。本人が雲隠れしてしまったのでそれ以上の検証はできないようだが、もともと何らかのパーソナリティの偏りがあったとすれば、横領がばれないようにさらに横領を重ねる人と同じなのであって、それが「科学の最先端」で起きたために、三面記事ではすまなくなったということであろう。そういう意味では、科学研究と利潤追求の結びつきが強まり、「サイエンス」「ネーチャー」を頂点とするジャーナルや「ノーベル賞」レースのあり方が拍車をかける現状では、たまにはこんなこともあるけどそういう競争体制はよりよい成果を生むためには必要悪と割り切るのが、今の流れなのかもしれない。 NHKのドキュメント取材にもとづく本書、著者は工学部からNHKに入った人で、科学ジャーナリストのすばらしい仕事になっていると思う。 |
| 池田暁子 『片づけられない女のための こんどこそ! 片づける技術』(文芸春秋) |
|
片づけられない=ADHD、のような診断本は、もうそろそろ十分に役割を果たし終えたかもしれない。名前をつけることは重要な転機だが、もちろん次はそれをどうするか、である。発達障害そのものには薬物療法が効くわけではないから、あとは認知療法や行動療法の出番なのだが、ADHDの人は昔からいて、その中に適応行動を身に付けていった人たちも少なからずいたわけで、じつはADHDを診断する医者や心理士ではなく、そういう人たちこそがADHDの人たちの助けになるはずである。 イラストレーターの著者はとんでもないゴミ部屋住まい。領収書書くのも一日がかり。床が見えない部屋には布団を広げることもできない。修理の人を呼ぶこともできずシャワーヘッドは二年も外れたまま。モニターをまたがないと部屋に入れず、洋服賭けは台所にある。『捨てる! 技術』も結局役に立たなかった。とくれば、最近のスタンダードはここでADHDの薀蓄が出てくるものだが、本書はまったくそんな寄り道はしないのである。著者は、ついには「普通の部屋」を実現する。コミックなので楽しく読めて、5つのステップは確かに参考になるだろう。 |
| 中村健之介 『宣教師ニコライと明治日本』(岩波新書) |
| 御茶ノ水のニコライ堂で知られるロシア正教のニコライ大主教は、克明な日記をつけていた。著者は最近その全訳六巻を完成させた。本書は10年ほど前に発行され、なかなか完訳本までは読む機会がない人にも、日記を手がかりに当時の日本のありさま、ニコライの活動と人となり、ロシア正教のしくみや各教派の日本宣教の様子、国際関係までがよくわかる解説書である。神学校を出てすぐ、応募して日本にやってきたニコライは、篤実な信仰はもとより、誠実で精力的な人柄で、苦労しながらも教団を成長させていく。日本語学習の上達、幅広い人間関係、豊かな好奇心、庶民の暮らしや旅先の風物への関心が、著者の研究の真摯さによって、わかりやすく面白く読める。 |
| 井上信子 『対話の技』(新曜社) |
| 井上信子著・神田橋條治対話というクレジットである。井上の事例と神田橋の言葉を交えた独特の展開がとられていて、類書のない、示唆に富むガイドブックである。いや、「ガイドブック」という表現がふさわしいかどうか。もとより神田橋の対話精神療法の一つ一つは技法ではなく「技」と呼ぶべきものであり、神田橋はその技法が体系化されていくことにあえて「違和感」を公言すらしている。神田橋の著作を再読しつつ、並行して読み進むならば、セラピストとクライアント、さらにスーパーバイザの三つ巴の関係に、あいまいな立場でその治療の時間・空間に入り込んでいくことで得られる体験は貴重である。 |
| 小塩真司 『実践形式で学ぶSPSSとAMOSによる心理・調査データ解析』(東京図書) |
|
このシリーズは3種類あって、青い表紙の基礎編、黄色い表紙の研究編、そしてこの赤い表紙の事例編とそろえれば、SPSSとAMOSを一般的な調査研究で使うのに必要なノウハウはばっちりだ。なかでも、この赤表紙本は、学生や院生レベルの調査研究を想定して、多くの調査研究事例をクリティークしていくプロセスがとても面白い。事例も架空とはいえ十分吟味されていて、追試したくなるようなものばかりである。 SPSSやAMOSを使うときに、こういうときはコレを使うということを説明するわけだが、なぜそれを使うかについての説明が、非常にスッキリ明快に述べてあって、実用性と分かりやすさをうまく両立させている。もっと詳しく原理を調べようと思えば、その手がかりも与えてくれている。このテキストの存在は、もし学生が統計パッケージを使おうとするとき、これがあるからSPSSにしなさいといいたくなるほどのものだ。 |
| 太田直子 『字幕屋は銀幕の片隅で日本語が変だと叫ぶ』(光文社新書) |
|
子どもたちが小さかった頃、テレビでディズニーの短編アニメをよく見た。しかし、すぐにいらいらしてくる。明らかにもとはいっさい言葉が入っていなかっただろうに、いちいちうるさい説明が入るのだ。もともと何もなかったのにセリフがつくのだから、吹き替えですらない。子どもをバカにしているのか、言葉の無い放送が出来ないような何か決まりがあるのか、どういうつもりなのかは知らないけれど、これではかえって言葉の能力は落ちてしまう。際限の無い説明過剰、勝手な決めつけの押し付けと垂れ流しは、短い言葉、単純な言葉に、深い意味や広がりのある感情をこめてやり取りすることをできなくしてしまう。 そう思えば、字幕翻訳者というのは、限られた言葉で意味や感情を伝える、もっとも洗練された言葉の職人というべきであろう。限られた言葉というと、俳人や歌人も同様かと思うが、自分の発想を表現するのではなく、字幕翻訳者はすでにあるメッセージを読み取って、映像と字幕の組み合わせでもともとのメッセージが上手く伝わるように突き詰めて言葉と文を選んでいくわけだから、まさにその禁欲と気配りのこまやかさにおいて、職人というべきであろう。あのアニメのように説明過剰に陥りがちな配給業者の圧力に、厳しい納期に安い労賃と戦いながら作品を仕上げていくいきさつを知れば、いつもお世話になっていますと頭の下がる思いである それにしても・・・最近妊娠して結婚引退した若い女性タレントの相手が、バラエティ番組で「映画を見に行っても○○ちゃんは字幕が読めないので、吹き替え版を見るしかない」と言っていたが、もうそこまできてしまっているのですね・・・。 |


