

 �ŋ߂̍X�V�i�P�U�N�R���`�P�V�N�R���j
�ŋ߂̍X�V�i�P�U�N�R���`�P�V�N�R���j
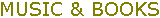
| >HOME >BOOKS |
| BOOKS |


 �ŋ߂̍X�V�i�P�U�N�R���`�P�V�N�R���j
�ŋ߂̍X�V�i�P�U�N�R���`�P�V�N�R���j
|
| �p�I���E�}�b�c�@���[�m�w�G�����l�ɂ̓E�\������@�_��D���̍E�q�m�炸�x�i������Ɂj |
|
�@������悭���Ȃ��Ɖ��̖{���킩��Ȃ��B����^�c���̊G�ő����������Ă��邩��A�u�E�q�Ɋw��Ńz���g�ɑ��v�H�v�Ƃł����������ꂽ�т��t���Ă��Ȃ�������A���̂̂���Ȃ����Җ��i���͓̂��{�l�̑�w�̖^�搶�j�������ĉ�����A�Ƃ����{�ł���B �@���͂��̂Ƃ���E�q�ɂ��Ē��ׂĂ���̂ŁA���҂̌����Ƃ���͔��ɂ悭������B���������E�q�̓`�L�炵���`�L�͂Ȃ����i������2500�N�O�̐l�Ȃ̂����瓖����O���j�A�E�q�̐��������������Ƃ��炵�������Ă���{�͂��������͎i�n�J�́u�j�L�v���Ƃ���ȃl�^������A���j�w�I�Ȋm���炵�����Ȃ��B���������́u�j�L�v�ł���A�E�q�ɂƂ��ēs���̈������Ȃ��Ƃ������Ă��邭�炢�ł���B����ɂ���������Ε���Ĉ�����Ă���u�E�q�ƌ�v�Ɏ����ẮA�����S�����ĂɂȂ�Ȃ��E�E�E�B �@�܂��A�����V���v���ɍl���Ă݂Ă��A�{���ɏo�����������s�m���i�������Ă��Ȃ��j�ȗ������̖�l��50���ŏA���̗��ɏo�āA�N���ق��Ă��ꂸ�A���ǔ�яo�����c���Ɋ҂��Ă���b�ȂǁA���������݂��߂ƌ������g�ɂ܂����킯�ŁA��������肪�������čՂ�グ��l�����������C�Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��낾���A���ǒ����ł͍E�q�̌��t������ɂǂ�ǂ���t�����Ă����āA��q�w������ɂȂ�Ƃ����܂�ŕʕ��́A�������w��I�ȑ̌n�Â��͈ꌩ�����Ƃ��炵���ł��Ă�����̂ɉ����āi��{���R�������獻��̘O�t���ƌ����Ă��܂�����܂ł̘b�ł͂��邪�j�A���ꂪ���{�̍]�ˎ���̊w�⏊�ɍ̗p����A���璺��̓����I��b�ɂ��Ȃ�̂�����A���m�̃L���X�g���ɕC�G����e���͂ł͂���B�ǂ�������̎n�c�̐��������͞B���Ȃ��̂ł��邪�i�J��Ԃ����A�����2000�N�ȏ���̂̐l���̐��������ȂNJm���߂邷�ׂ͂Ȃ��̂œ�����O�Ȃ̂����j�B�������ɔ������ꂽ�u�|�P�b�g�_��v���x�X�g�Z���[�ɂȂ�A�a��h�ꂪ�������������ƂŃu�[���ɂȂ����E�q�̎v�z�i�݂����Ȃ��́j���A���܂ł��e���͂������Ă���̂́A���X�ɍs������l�b�g�ŃO�O��Ζ��炩�ł���B �@�����A���҂������悤�ɁA�������͂��Ƃ��ăV���v���Ɂu�_��v��ǂ߂A���Ȃ�u���u���Ń_���_���Ńw�^���ȂƂ����������E�q�̐l�ԑ��������яオ��A����Ȃ�������̐���{���Ȃ̂��Y���Ȃ̂��Ǝv���߂��炵�Ȃ���t�������y���݂͂Ȃ��Ȃ��̂��̂ł���B�u�_��v��Ҏ[�������炭�E�q�̑���q�ӂ�̐l�������A�E�q���Ղ�グ�����Ȃ炢����ł����悤���������낤�ɁA���̃_���l�ԏL����`����G�s�\�[�h���قǂ悭���ꍞ��ł��邠����A��͂蒘�҂̌����Ēʂ�Ǝv���B �@���҂̌����u�_�ꋳ�v�ɐ��]����Ă�������ɂ́A�ʉߋV��Ƃ��ēǂ�ł����ׂ�����ł͂Ȃ����낤���B |
| ���슮�@�w���{��c�̌����x�i�}�K�АV���j |
| �@�b��̖{�ł��邵�A�����o�Ă����ɔ����ēǂ��肾�����������t�����Ă݂��5��20����O���ł���i���ő�����5��1���t�j�B���g�̋��낵���ɂ��ẮA���Ԃ��o���Ă��܂��������������ł͏����Ȃ��B�������A�o�ō����~�߂̔����ɂ͋��������A����ȏ�Ƀ}�X�R�~������ɑ��Đ키�p�������܂茩���Ă��Ȃ��i�悤�ɂ݂���j���Ƃ̕������낵���B�ٔ����̌������^����Ƃ���Ȃ̂����A�������̐\�����Ă̒��̈ꂩ���݂̂����グ�A���������ꂪ�����Ȃ��Ƃɂ����v���Ȃ��\���̉ӏ��ł���Ƃ��낪�A�ÂɁu���ꂭ�炢�Ȃ�폜���Ă��悢�ł���A�����r���ĂȂ��Ŏ��߂ĉ�������v�I�ȋC�����ĂȂ炸�A�i�@�͂��������ǂ��Ȃ��Ă���̂��ƈ��W����v���ɋ����B���ہA���̉ӏ��̕\���������Ƃ����肳���̂Ȃ����̂ɂ��Ă��A�{���̉��l�͂܂������ƌ����Ă悢�قlje�����Ȃ��ł��낤�i���ہA���̉ӏ���36�������폜���Ĕ̔�����Ă���j�B���ꂾ���炱���������āA�s�����o����̂ł���B���ꂭ�炢�͋�C��ǂ�őË����ĉ�������A�Ƃ������Ƃ̐ςݏd�˂��ǂ̂悤�Ȏ��Ԃ������炷�̂��A�������͒ɂ��قǒm���Ă���͂��Ȃ̂����B |
| �����j�w��R�R�~���[��1974�x�i�u�k�Е��Ɂj |
|
�@���͋��������D���Ȃ̂����A�������t�@���ɂ͒c�n�t�@���������A�����c�n�Z�܂������ӏ����o�����Ă���̂ŁA���낢��ƃl�b�g�Œ��ׂĂ��邤���ɁA���̖{�ɏo������B���ƒ��҂Ƃ͐���I�ɂ͑�̓����Ȃ̂ŁA�w�i�ƂȂ�Љ��⋳�玖��͋��ʂ���B���ۓ������70�N��̋�C���ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��������ɂ��ẮA�ĊO�`���ɂ����̂ł���B�������͏��w������̑啔������s�ʼn߂����A��t�s�ő��Ƃ��Ă��邩��A�n���I�ɂ͋߂����A���Ԃ͂��Ȃ�قȂ��Ă������Ƃ��ǂ�ŕ��������B���Ȃ݂ɕ���ƂȂ��R�c�n�ł͂Ȃ����A���͌����̑O��ɓ����s���̓��v���Ēc�n�ɏZ��ł�������A���������e�ߊ��͂킢���B �@���v���Ďs���掵���w�Z�́A���Ƃ��ƒn���̎q���������ʂ��Ă����Ƃ���ɁA��R�c�n���ł��āA�啝�Ɏ��������������B���w�Z�ƐV���̒c�n�}�}���������o���Ă��������̂��A���҂������u��R�R�~���[���v�ł���B�����Ɏ������܂�Ă����͉̂��R�[�́u���������v�ƁA�S�������w���������c��S����������u�w���W�c�Â���v�ł������B�{���ł́A���҂��g�������Ė�������u�w���W�c�Â���v�����ݏo�������w�Z�̏��A���A���ɕ`���o���Ă���B�NJ����̋����A���ݔᔻ��l���A���o���ꂽ�����B�w���̂����߂��e�[�}�ɂ����t�B�N�V�����h���}�ȂǂɌ����鑕�u�͌����̂��̂Ƃ��Ă������̂����A�q���������x�z���A���C�ɓ������肭�g���ďW�c���v���ʂ�ɓ��������Ƃɉ������o���鋳�t�����̎p�́A�v�z�̔@������Ȃ��B�S�����̊����͂₪�ĉ��ɂȂ��Ă������A�����ɂ����߂��Ă����~���͂��܂₢����u�V���R��`�v����₠�́u�_���̊w�Z�v�ɋ��ꏊ�������Ă���B �@����ɂ��Ă����҂͂悭���̎��̏o�������L�����A�B���ȂƂ������ނ��A�č\�����čs�������̂��Ɗ��S����B���ꂾ���̃V���b�N���Ă����̂��낤���A�m�ɒʂ����Ƃő��ΓI�Ȏ��_�������Ă������Ƃ����낤���B���̏ꍇ���A�̂�т肵��������s�̏��w�Z����A�U�N�ɂȂ鎞�ɐ�t�s�̐V�ݍZ�ɓ]�����A���̌������ƁA�V�ݍZ�̈ӋC���݂̗��̕����I�ȌÏL���Ƃ̃M���b�v��焈Ղ������ƂŁA�悤�₭�����Ȃ�̑��Ή����ł����̂����A�U�N�ԓ����w�Z�ɒʂ��Ă���Ƃ������Ƃ͋��낵�����Ƃł���B �@���ꂵ�����e�ł��邪�A���e����̓S���D���ł��钘�҂́A������Ƃ����G�s�\�[�h�A���ɊJ�Ƃ����Ă̕�������ɏ������A�䑷�q�w�̖퐶���ʼnw����H�ׂ���A�Ƃ���������ɂ́A�����̐������ɋ߂����Ƃ����邪�A�ق��Ƃ�������B |
| �i��`�j�w�{���̓u���b�N�ȍ]�ˎ���x�i�C���o�Łj |
| �@�ɂ�����Ύ��㌀�`�����l���Łu�S���ƉȒ��v��u���q�����v�����Ă���ȂɁA���Ǖt�������Ď������y����ł��܂��̂����A�܂�������������Ȃ�ɕi�i�̂��錴��ɂ̂��Ƃ��č��ꂽ�h���}�͂悢�����B�₽��ƍ]�ˎ���������グ����A�����̃g���f���b�ɂ����Ȃ��u�]�˂������v�������̋��ȏ��ɓ�������ƁA���R�Ȃ�Ƃ��Ƃ��\���V�Ȃ�Ƃ��̃g���f�����㌀�o�[�W�����̍]�˂̒��C���[�W�ɁA����ɃN�[���W���p���̂���������x���\�����̌���ɂ͂��肾�B�]�˂̏����̕�炵�̌�����ǂ݂₷���G�s�\�[�h�ŒԂ��Ă���Ă���̂��{���̖ʔ����ł���B�]�˂œ����Ƃ������Ƃ��ǂꂾ���u���b�N�ŁA�]�˂ŕ�炷�Ƃ������Ƃ��ǂꂾ���댯�ŕs�q���ŁA�܂�Ƃ���]�ˎ������Ƃ������Ƃ��ǂꂾ�������������̂��A�悭������B |
| �R�c����@�w���̃r�U���q�����j�@���ҐߎO�ƃ��_����x�i�m�g�j�o�Łj |
|
�@�A�����J���w���ɃX�s���o�[�O�́w�V���h���[�̃��X�g�x���ςĊ������A�����琤��m��A�u���̃r�U�v���������̃��_���l�����͂ǂ��Ȃ����̂��낤�A�Ƃ����^�₩��A���{�ɂ���Ă������_���l�����̑؍݊��Ԃ��������A������O���ɑ���o�����߂ɐs�͂����l���A���҂�ǂ����ƂɂȂ������҂͔o�D����B�A�����J�A���{����A����ɃC�X���G���ɂ܂Ŏ�ނ��A�����̐l�X�Əo��A���҂̋Ɛт�����̖{�ɂ܂Ƃ߂��B�f���炵���d���ł���B�}�[���B���E�g�P�C���[�Ƃ̋��R�̂Ȃ�������������ɁA���⑰�ɐM������āA��ނ��d�˖{��������������B �@���҂͐_���̉Ƃɐ��܂�Ȃ���L���X�g���ɉ��@���A�q�t�ƂȂ��ăA�����J�ɗ��w�A�����ƃ��_�������������Ĕ��m�����擾�B�A����͂������E�ɏA�����a�C�Ŏ��E�A�u�������T�������v���J�݂��邪���͂��ĕ����Ƃ���ցA���S���ق̏����m�E�ɐ����āA���B�̃��_���l�R�~���j�e�B�̒������Ƃ��đ�A�ɓn��B�A����A�։ꂩ��_�˂ɂ���Ă�����ʂ̃��_���l�����̂��߂ɁA�����r�U�̏\���ԂƂ����؍݊��Ԃ��������邽�߂ɖz������B�I�����l�X�̋�J���o�ă��_�����Ƃɉ��@���A���ċ~�����l�X�ƍĉ��B �@���炷���Ƃ��Ă͂����Ȃ�̂����A�����ׂ��G�s�\�[�h��A�ӊO�Ȑl���Ƃ̏o��ȂǁA�܂��ɔg������ł���B�n���s���ŏI����}�������҈�Ƃ��A���x�̓��_���l�����ɋ~����ȂǁA�܂��Ɋ����ł���B �@�{����ǂނƁA��O����풆�̓��{�ƃ��_���l�Ƃ̂�����肪����Ȃɂ������̂��Ƌ������A�����m�E�̐l�ƂȂ�ɂ��Ă��A�������ς���Ă���B�f���炵���l�X��A�������錾�t�ɖ������{�ł���B |
| ������F��Y�@�w�L�����A����̃E�\�x�i�����܃v���}�[�V���j |
|
�@���ɂ͑��q����l���āA�ʁX�̒�����эZ���炻�ꂼ��̑�w�ɐi�B���j�͗��n�ő�w�@�܂Ői�݁A��]�̊�ƂɏA�E���āA��Ђɂ��d���ɂ��������Ă������A��ő����Ă������y�����Ƃ̗������ł��Ȃ��Ȃ�A���ǁA���y�̓���I�B��j�͕��͐U���Ȃ��������A�s�A�m�𑱂��Ă������Ƃ��特�y����ɐi�w�A�����Ƌ��͎�������̂́A��w����ɂȂ��ď��߂Ė{�i�I�Ɋw���y�ɒx�܂��Ȃ��疣�����A���܂��C�s���ł���B �@���q��l���Ăǂ�������y�̓��ɐi�ނƂ����̂́A�e�Ƃ��Ă͗\�z�����Ȃ��������Ԃł���B������Ɠ�l�Z�킾���A��l�Ƃ����ʂ̋ߐl�ł���A�������Ďq������l�����܂�A�i���̂Ƃ���j�������]�E��������N���߂Â��Ă���Ƃ����̂́A���ꂾ���Őe�͉�X�Z��Ɋ��ӂ��Ăق����Ǝv���قǂ����A���Ƃ����đ��q�����̑I����ے肷��C���܂��S���Ȃ����A��ĕ����Ԉ�����Ƃ��v���Ă��Ȃ��B�ł�����艞���������B�S�z�ł͂��邯��ǂ��B �@�N��Ɋo���Ă��邱�Ƃ�����B�������\�N�O�A�����ɂȂ��čŏ��ɕ��C�������ƍ��Z�ɂŁA�E�ƓK���������s��ꂽ�B�Ԃ��Ă������ʂ����Ĝ��R�Ƃ����̂́A�قƂ�ǂ̐��k�́u�K���̂���Ǝ�v���u�y�E���z�v�ł��������Ƃł���B�������������A��ʎ����E����]���鏗�q�������Ƃ���ɁA���̌������ʂ��ǂ��~�߂�������悢�̂��A���ɔY���̂ł���B���ǂ́A�����܂ŎQ�l������A�ƌ����Ă��܂������̂́A������Ӗ����ǂ��ɂ���̂��킩��Ȃ��B�l���Ă݂�Ύ��������Z���̎��ɂ��̂悤�ȃe�X�g�����悤�ȋL�����ڂ��肠��̂����A�i�H����ɎQ�l�ɂ����L���͑S���Ȃ��B �@�����A�u�L�����A����v�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂��邪�A�ǂ�����悢�̂��́A�{���̂Ƃ���悭������Ȃ��B�{���ł��ᔻ����Ă���悤�ɁA����ōs���Ă���u�L�����A����v�́A�A���o�C�Â���̂悤�ȃ��x���̂��̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����Ă����B����ɑ���Ƃ��ẮA�v�͌^�ɂ͂܂����L�����A����̃E�\��i�ɂ����炸�ɁA���K��邩������Ȃ��ω��ɔ����悤�Ƃ������Ƃ��납�B�ǂ������ς��Ȋ����ł͂��邪�A�����ς�Ƃ����^�C�g���ŃL�����A����̐��Ǝ��g���L�����A�����ᔻ����Ƃ����\���͋C�ɂ������B |
| �ɓ��S���@�w���̂��߂Ɏ��˂邩�x�i���t�V���j |
|
�@�s�v�c�Ȗ{�������B
�@�тɁu����Ԍ����I�@�����̃��A���e�B�I�v�Ƃ����āA�C�㎩�q���̓��ʌx�����i��������ꕔ���j��n�݂����l���̋L�^�ł���B���ہA���ɖʔ����āA�����Ƃ����ԂɓǂݏI���Ă��܂��̂����A����͉�b���������ǂ݂₷������ł�����B�m���t�B�N�V�����ʼn�b�����������Ƃ����A���e�B�Ǝ�邩�ǂ����ƂȂ�ƁA�ǎ҂Ƃ��Ă͋C�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���ł���B���҂͂܂��ɂ����ɂ��ĉ�b�����Ă����킯������A�Č����͍����̂��낤���A�ǂݎ�͉�b����ǂނƎ����Ȃ�ɑ���̐l������Ȃǂ�z���ŕ���č\�����ēǂ�ł��܂��B������A���q������߂čs�����~���_�i�I���ł̃����C���Ƃ̂�����A�t���b�V���o�b�N�I�ɑ}������郊���p�b�N�ł̏o�����Ȃǂ��A���ɂƂ��Ă͂��܂�ɂ��ِ��E�̘b������ł��낤���A�����قƂ�ljf������Ă���悤�Ȉ�ۂɂ����Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł���B �@�Ƃ���ŁA�{����ǂݏI���������A���܂��O�J�K��̃G�b�Z�C�i�O�J�K��̂���ӂꂽ�����F�W�P�V�u�r��̃K���}���͉ǖفv2016�N9��15���@�����V���j��ǂB�O�J�͍��V���u���l�̎��v�ƁA��������Ƃɂ����W�����E�X�^�[�W�F�X�u�r��̃K���}���v������ׂāA���l�̃L�����t���ɂ��Ę_���Ă���̂����A�K���}���̉ߔ������ǖكL�����ł��邱�Ƃ���A���̂悤�ɏq�ׂ�B �ǖقł����Ȏ咣�͂͂����肵�Ă���r��Ŏ��l�B�u�����i�[���N�[���ŁA�u�݂�ȑ�l�Ȃ���D���Ȃ悤�ɂ��邪�����v�I�ȁA�B�ς��_�Ԍ�����B�`�[�����[�N�Ō����鎘�����Ƃ́A���Ȃ�C���[�W���قȂ�B���ꂪ�������Ȃ̂��A�K���}���Ǝ��̈Ⴂ�Ȃ̂��́A�l�ɂ͕�����Ȃ��B
����ɂ͚X���Ă��܂����B�܂��ɁA�{���ŏq�ׂ��Ă����A�މ�̓��ꕔ���̓����ł͂Ȃ����B |
| �y�c�����Y�@�����w�_��W���x�P�`�S�i���}�Г��m���Ɂj |
| �@�K�v�������Ď�q�w�ɂ��ď������ׂȂ���Ȃ炸�A�ƂȂ�Ƃ܂��́w�_��x����q�͂ǂ��ǂ̂��Ƃ������ƂŁA�{���ɓ�����ق��͂Ȃ��B�Ђ��Ƃ��Ă݂Đ悸�������̂́A��q�̂��Ƃł͂Ȃ��āA�҂̓y�c�����Y�̎d���ł���B�������A���m�œǂ݂₷���̂͂��肪�������A����ȏ�ɁA���������ɓ��m�ւ́w�_��Ë`�x�y�щ����h�q�́w�_�꒥�x����̈��p��������Ă��邱�ƂɁA�����҂Ƃ��Ă̎��тƐ����Ƃ��ςāA���ӂƊ������o�����ɂ͂����Ȃ������̂ł���B �@�Ⴆ�A���������ΐl�w�_�ꕨ��x��ǂ�ł����v���̂́A���蒷�ё�O�͂́u���l�v�͂ǂ��ǂނׂ����Ƃ������Ƃ�����B��g�̋��J�������������߂͂��Ȃ�h煂ł���B���������u�N�q�͊�Ȃ炸�v�ł���A�܂����蒷�т�����ɏo�Ă���q�v�̕`������͊m���ɍD�ӓI�ł͂Ȃ��̂����A���Ď�q�͂ǂ����߂����̂��낤���B���ꂪ�u�N�q�̒i�K�ɂ͂܂������Ă͂��Ȃ����A�M�d�Ȋ�ł͂���Ƃ������Ƃł��낤���i������V�M�ҟb�j�v�ƁA����ӂ�ȉ��߂ł������B���ꂾ���ł͌��������ł��邪�A�y�c���́A�܂��m�ւ����l�̓��͓��p�̓���ł���Ƃ������߂���A�q�v�����߂��Ǝ��̂ɑ��āA�h�q�͐m�ւ��Ԉ���Ă��āA���͑�@���i�T��璷���j�̓��ł��邩����l�͂���ɓ����낤�ƌ����Ă���B�ӂ��ށB�ق߂Ă���̂����Ȃ��Ă���̂��A���ǂ͂ǂ���Ƃ�����̂��B�����w�_�ꕨ��x�̏����Ԃ�͂������������I������Ƃ�����ۂ������Ă��A�ԈႢ�ł͂Ȃ������ł���B �@�܂��A�q���ё��͂́A�u�ق��Ă���������A�w�тĉ}�킸�A�l���q���Č��܂��v�̌�́u���L����Ɓv�B���J���́u���ɂƂ��Ă͉��ł��Ȃ��v���������肫�Ă��Ȃ������B��q���́u���͂ǂ�������Ă��悤���i�ǂ�������Ă��Ȃ��j�v�Ƃ�������A����������͌������Ƃ����̂ł���B�m�ւ́u����痼�҂̑��ɉ��������ɂ��낤���v�B�h�q�͐�̎O�͏��ԂɊW�������Ă��Č��ʓI�Ɂu�w�Ԏ҂����ɗ͂����Ȃ��Ă����R�ɂ����Ȃ�v�B�����Ɖ���ċ��J���̈Ӗ����h�q�̐������D�ɗ������B �@�p���p���ƋC�y�ɓǂނ����ŁA����܂ʼn��ƂȂ������������Ă������Ƃ�A�t�ɂ��܂�[���l���������ɒʂ�߂��Ă������ƂɁA�����������Ă����B�C�y�ɓǂނɂ͏��X�����{�ł͂��邪�A�����炷�����͑�ςȉ��l�̂���{���B |
| ���`���[�m�E�f�E�N���V�F���c�H�@�w�^���Ƃ������Ɓx�i�������[�j |
| �@�d���ɕK�v�Ȗ{��T���Ă��āA���������̎d���ɂ�������ƍs���l���Ă��āA���܂����I�ɂ����ĖڂɂƂ܂������̖{���A������������̓T�b�Ɠǂ߂Ėʔ��������͂����A�Ǝv�������Ď��o���āA�ǂݎn�߂�������~�܂�Ȃ��B�N���V�F���c�H�͂��Ƃ���IBM�߂̃r�W�l�X�}���������̂ɁA��ƂƂ��Ă����������l���ŁA�[���N�w�I�f�{�ƃZ���X�ŋC�̌��������͂������l�Ȃ̂ŁA����120�y�[�W�قǂ̏����͊y�����ǂ߂āA�������ƂĂ��l����������B�T�̃G�b�Z�C����Ȃ邪�A�����͑��͂́u���R�ƕK�R�v���B���m�[�́w���R�ƕK�R�x�����������ɏo���Ȃ���A65�̒a�������j����ݕv�l�̔ӂ�����ɁA�萯�p�t�A�i���A��߂����Z�t��������荇���B�I�Ղ̃G�s�\�[�h���y�����B��O�́u�G���g���s�[�v�́A�i�|������~���m�ɓ]���Ă�����������l���ɁA�ǂ����炪�t�B�N�V�����Ȃ̂�������Ȃ��A�����ē��e�Ƃ��Ă͑O�͂̑����̂悤�ȉ�b���J��L�����A�����������˂ɏI���B�ǂݏI����Ďd���ɖ߂鎞�ɂ́A�s���l���Ă���Ƃ������Ƃ����������Ō��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă����B����ł͂��ǂ�킯�ł͂Ȃ�����ǁB�i�ŁA�T���Ă����{�͂܂�������Ȃ��E�E�E�j |
| �}�C�P���E�s���G�b�g���N���X�e�B�[���E�O���X=���[�w�n�[�o�[�h�̐l�����ς�铌�m�N�w�x�i���쏑�[�j |
|
�@���{��ł̑薼���������C�ڂ̖��̉��̃h�W���E�ŁA���͂��Ɏ���Č���C�ɂ��Ȃ�Ȃ������i�����"The Path"�i���j�ł���j�B�ɂ�������炸�A�{�����Ђ��Ƃ��ɂ��������̂́A������{�̒����N�w�̌����҂̘b�ŏЉ�ꂽ����ł���B���̐搶�͐́A���ۂɃs���G�b�g�����̃[�~�ɏo�Ă������Ƃ������āA�����͊w���Ƀ��|�[�g�����A���_�����邾���ŁA�����ł͂قƂ�ǂ���ׂ�Ȃ������̂ŁA����͂��炵���A�����������ꂱ�̂悤�ɂ�肽���A���A�y�ł͂Ȃ����I�Ǝv�����̂����A��������������Ă݂�Ƃ����͂����Ȃ������A�ƌ������Ƃł������B���̉�������ׂ�Ȃ������s���G�b�g�������A�قƂ�ǂ���ׂ�Â��߂̍u�`�ő�l�C�A�Ƃ����̂��܂��ӊO�������Ƃ����B���ہA�o�ϊw��R���s���[�^�T�C�G���X�Ɏ����A��O�ʂ̐l�C�u�`���Ƃ����B �@�Ƃ����킯�ŁA���ۂɓǂ�ł݂�ƁA���ɑf���炵���A���m�v�z�̓��发�ɂȂ��Ă����B���{�ɂ���Ƃǂ����Ă����Z�ϗ��̃X�^���_�[�h������肪���Ȃ��ꂼ��̎v�z���A����ς̂Ȃ��Ǝ��̐����������N�����Ă����̂ŁA�V�N�ł���B �@�Ƃɂ������Z���Ǝv���̂́A���Ƃ������J�[���A���[�Y�x���g�A���[�K���̂�肩�����A�V�q�ɗႦ�Ă���B���̂�����͋����̃O���X=���[�̎�r��������Ȃ����A���{�l�̎����ǂ�ł��A����Ȍ���������̂��Ɣ��ɖʔ����B���̂悤�ȃn�b�Ƃ������鎋�_�����������ɂ����āA�Ñ㒆���v�z�ɉ��߂Ėڂ�������Ƃ������́A���ǂ���͗m�̓����̍��ق̘b�ł͂Ȃ��A���{�I�Ȃ��̂��Ƃ̌����̖��ł���A�l�ԂƂ��Ă̐������̖��ł��邱�ƂɋC�Â������B �@�Ō�ɏ�����Ă���悤�ɁA���m�v�z�͐��m�œs���悭���ς���A���p����Ă����B�s���G�b�g�����̍u�`����҂����ɂ��A���̂悤�ȓ��@���Ȃ��Ƃ͌����Ȃ����낤�B�������{����ǂތ���A���m�v�z���w�Ԃ��Ƃ̐^�̓��Ɉ����߂���邱�Ƃ͑傢�Ɋ��҂ł���B�Ƃ���ŁA�����{����ǂނ��������ƂȂ������m�N�w�̐搶�́A����ł������N�w���w�ڂ��Ƃ�����{�̊w�����قڂ��Ȃ��Ƃ�������������Ă����B�l�����{�y���̕����ł��낤���B���̂Ƃ���A���{��œǂ߂钆���v�z�j�̃e�L�X�g�Ƃ��Ă����Ƃ��M���̂�������̂́A�����炭�A���k�E�`�����́w�����v�z�j�x�i�m�@�j�ł��낤���A���ꂪ�t�����X�ꂩ��̖|��ł���Ƃ����̂��A���{�̓`�����v���Ƃ��ꂩ�炪���ڂ��Ȃ���������B |
| �{�ԗ��@�w�����v���p�K���_�x�i��g�V���j |
| �@���z���n�k��̂�����ł��������A���ł������āA���芠�H�����̌��w�ɏo���������Ƃ�����B�����̓W���Z���^�[�̂悤�ȂƂ���⌴���������ē�����A�L����DVD�Ȃǂ��z��ꂽ�B����������p�͂܂��Ɂu�����v���p�K���_�v�̈ꕔ�ł��������낤�B�l�b�g�����قǕ��y���Ă��Ȃ��������A�d�����A�������K�v�Ŗ₢���킹��ƁA������ł������Ă����B���ʁA���ȏ��Ȃǂ̌��q�͔��d���̋L�q�ɑ��ẮA�֘A�c�̂���̃`�F�b�N�́A���ɕ\�����������������悤�ɕ����Ă���B���L���㗝�X�Ζ��̒��҂́A�d�ʂ_�Ƃ���L���㗝�X���A�����̈��S�_�b�����グ�邽�߂ɂǂꂾ�����f�B�A�ɐH�����݁A���������痘�v���z���グ�Ă��邩���A���肷��قǂ悭������悤�ɏ����Ă���B�d�͉�Ђ̍L����́A������x�o���Ă��d�C�����ɏ�悹�ł���B�܂��Đ��{�L��Ȃǂ͐ŋ��ł���B���������������ŋ���d�C�����ŁA���������������̈��S�_�b��M�����܂���Ă���Ƃ����}���ł���B�A�����J�ł͓��Ƒ��Ђ̍L���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����K��������̂ŁA�ǐ艻���N���邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ����̂����A���{�ł͉ǐ�ǂ��납�Ɛ�ɂȂ肩�˂Ȃ��ł���B�L���㗝�X���͖ܘ_�e���r��V���ň����邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ��B�Ɨ��̃l�b�g���f�B�A�ɂ��̋C�T�͂���̂��낤���B |
| �e�b�h�E�R�Y�}�g�J�@�w�{�[���E�A�i���X�g�x�i�n���J�����ɂr�e�j |
| �@�v���Ԃ�ɁA�����Ƃ����ԂɓǂݏI������r�e�B���܂�u�A�i���X�g�v�ɏd�_������킯�ł͂Ȃ��Ȃ��Ǝv������A�����"Prophet of Bones"�������B�����J�Ɂu����ǂ݉����ҁv�Ƃ܂ŕ�������Ă��āA�M��̃Y�����������Ă��邱�Ƃ�����̂����A���セ�̂��̂��r������͂��܂蒆�S�I�ȃe�[�}�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă���B���i���_����������������̐��E�ݒ�͖ڐV�����͂Ȃ����A���̒��ł�����قǖ����⊋�����[�����ɂȂ��Ă��Ȃ��̂����A�����������ɗ��ނƂ��낪�A���܂�r�e�I�ł͂Ȃ��̂����A�X�g�[���[�Ƃ��Ă͐V�N��������Ȃ��B�nj㊴�Ƃ��Ă͑тɂ���e�N�m�X�����[�Ƃ������ʂ������A�㔼�ł͂قƂ�ǃA�N�V�������̂ɂȂ��Ă���������A�v���Ă����̂Ƃ͈���Ă������A�I�Ղɂ����ĉ�����������Ă����������悭�ł��Ă��邵�A���X�g�̓˂����������Ȃ��Ȃ��̂��̂ŁA���҂����҂�����B |
| �����q�q�w�u�w�́v�̌o�ϊw�x�i�f�B�X�J���@�[21�j |
|
�@�u�o�ρv���������Ȃ��Ƃ܂Ƃ��Ƀf�[�^�����Ƃɂ��ċc�_���悤�Ƃ��Ȃ��u����v����̋����A������₷���������x�X�g�Z���[�{�B���v�w��S���w�ł��悭�m���Ă��鎖�Ⴉ��A�ŐV�̌����܂ŁA�i������O�����j�f�[�^�����Ƃɂ��ďЉ��Ă���B����̎d�������Ă���A�����ɂł��𗧂��e���A����������Ă���B �@�u�o�ρv���������Ƌ����̂́A�u��{�I�ȃ������������̈�Ƃ��Đe���狳������l�́A�S�������Ȃ������l���N�����W�U���~�����v�i��.95�j�̂悤�Șb���ɂ߂ĕ�����₷������ŁA���w���Ɛe�Ɋw���ƔN���̃f�[�^��p���ĎZ�o���ꂽ����̎��v����m�点��ƁA�m�炳��Ȃ��O���[�v���L�ӂɂɊw�͂������Ȃ����Ƃ����}�_�K�X�J���ł̎����i��.107�j�Ȃǂ��������ƁA���l���w���Ґ������͂邩�Ɍ������ǂ��Ƃ������f�͗e�Ղɕt���B�������w�͂��Ⴂ�q�ǂ������ɂ͏��l������̃����b�g������Ƃ����f�[�^���Љ��Ă���B �@�������A���Ƃ��Ηc������̒����I�ȃ����b�g�͔�F�m�I�\�͂ɂ���Ƃ��A�������������邱�Ƃ��d�v�ƂȂ��Ă���ƁA�����ʑ��肪��������̋�����e����@�ɓ��ݍ��ށA�ʕ���̌������i�܂Ȃ��Ǝ��p�ɂȂ�Ȃ��B����ɁA��`��ƒ����n�搫�ɂ���Đ����鍷���傫����A�o�ρu����v�ɂ͑����̕ϐ�������ɉ�����Ă���B���ۂɋN�����Ă��邱�Ƃ����A�{���ł��w�E����Ă���ʂ�A�w�Z���ƂɊw�̓e�X�g�̐��т����\���ċ��킹��͖̂����ł���B�����̗p�̏�ǂ�Ⴍ����A�������͖Ƌ����x���Ȃ������Ƃ́A�c�_�⎎�s�͌J��Ԃ���Ă��邪�A�����̃����b�g���m�����Ă����Ȃ��Ɛl�ފm�ۂ͓���B�܂������_������r������������̏�Ŏ������邱�Ƃ͔��ɓ���i���̑�̂̏C�m�_���͋����@�̌��ʑ��茤���ł��������A��������_������r�Ȃǂ��肦���A���߂Ă��̑ΏƌQ�̐ݒ����ݍ�p�̓����Ȃǔ��ɋ�J�����j�B�w�̓e�X�g�̃f�[�^�������ɖ𗧂悤�Ȍ`�Ō��\����Ȃ����R���A�\���ɐ������t���B�u����ɃG�r�f���X���v�Ƃ������҂́i������O�����j���_�̗]�n�̂Ȃ���{���A���̍��́i�����Ɍ��炸�j�s���ł͂ނ���Ӑ}�I�ɔr������Ă��邱�Ƃ���A���ۂ̌�����ɂ������Ă��闧�ꂩ��𗧂Ă��邱�Ƃ́A�ӊO�ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B���Ƃ����āA���������������i�߂��邱�Ƃɂ���āA����s���̒��̐S����l�X�͊m���ɐS��܂���Ă��邱�Ƃ��܂��d�v�ł���B |
| ���Z�ϗ�������w���Z�ϗ����D�����I�x�i�������@�j |
|
�@�͂��A����͐�`�ł��B���������ҏW���܂����B�ȉ��͎����l�����A�`���V�̃R�s�[�ł��B 20�l�ȏ�̓N�w�҂����Ƃ̑Θb�ւ̗U���@---�@�R���p�N�g�ɓǂ݂���� �u���Z�ϗ�����ɂ�������Ă��������⌤���҂��A���ꂼ�ꎩ���Ɛ[�����������Ă����l����I�сA�ނ�Ƃ̐S�̑Θb�ւƓǎ҂�U���܂��B���̒����ǂ̂悤�ɕς�낤�Ƃ������Ȃ��u�ϗ��v����̌��_�A�����č��Ƃ��ꂩ��́u�ϗ��v����̎p��ʂ��āA�l�ԂɂƂ��ėϗ��Ƃ͉��Ȃ̂��������Ă������ł��B�v
�@����ł�����Ɠǂ�ł݂悤�Ƃ����C�ɂȂ��Ă��������邩�ǂ���������܂��i�����Č֑�L���ɂȂ��Ă��Ȃ����Ƃ�]�ނ���ł����j�A�������̌�����Ԃ��A�v�z�Ƃ̎v�z�Ǝ������g�Ƃ́u���������v���������߂��A���ɂȂ�����ɂȂ��Ă��܂��B�����A�����肪�����̂ŏ����Ԃ�𑵂���̂͂Ȃ��Ȃ���ςŁA�O��ł��Ȃ������Ƃ���͂���܂��B����ł��A�����ԓǂ݂₷���{�ɂ͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B |
| �䗯�Ԋ��@�w�������x�i���g�����A�j |
|
�@���͋��������D���ŁA�����₩�Ƀu���O������Ă��邪�A���̒��ɂ͋������}�j�A�͌��\���āA�������̂���f���炵���T�C�g��}�b�v������A�I�t��Ȃǂ����{����Ă���悤�ł���B���͈�l�œ����ߍx��A�o���◷�s�̂��łɍs�����炢�����炽�����m��Ă��邪�A����ł�������Ďʐ^���B���āA���Ƃ����̑��݊�����肭���߂����Ǝv���̂����A���ꂪ�Ȃ��Ȃ��ӂ̂܂܂ɂȂ�Ȃ��B����ŁA�{���̂��Ƃ����ɂ��L����Ă���x�b�q���[�v�Ȃ̋������i��������Ȃ����j�ʐ^�̂悤�ɁA�v���̂Ƃ������A�[�e�B�X�g�Ƃ��Ă̎ʐ^�Ƃ����߂����̂͂������ɂ������B �@���̎ʐ^�W���A���܂��ܒ��҂��J�����e�X�g�Ŏ�����ꖇ�ɉf�荞���Ƃ��狋�����ɖ������A�B��W�߂�ꂽ���̂ł���B�x�b�q���[��i�̃^�C�|���W�[�ʐ^�Ƃ������W�������ł͂Ȃ��A�A�[�e�B�t�B�V�����ȍ�i�Ƃ��Ă̔������́A������̂悤�ȑf�l�ʐ^�ł͋y�т����Ȃ��B�������ł��邪�������s���ĎB���Ă������̂ƌ���ׂ�Ƃ��ߑ����o��B���ɖ�i�ɂ͂��ꂽ�B����̐ΐ_�A��t�݂̂������A�����ċɂ߂��͍��q�̉H���ł���B���������Ă��d�����Ȃ����A�H���̓o�X�ƕ����ł͖�͍s���Ȃ����A���������C�g�t���̂��I�������ȁE�E�E�Ƃ����A�܂��f�l�̂�����݂݂����ȋC���ł���B �@���̎�́A�������Ȃ��Ă��Ă���B�������͂ǂ�ǂ�Ȃ��Ȃ��Ă��邩��ł���B���Ƃ����̔���̃G�s�\�[�h���_��I�ł��邪�A�������Ƃ����܂��ɑO���I�̈╨�Ɖ������Ƃ��Ă��錚�����ɁA�o��邤���ɏo����Ă��������A�ʐ^�Ɏ��߂Ă��������Ƃ����C�����ɋ����̂ł���B |
| ���o�[�g�E�`���[���Y�E�E�B���X���w�y������x�i�n���r�e���Ɂj |
| �@�C�O�r�e��Ƃł͂����Ƃ��D�݂ɍ�����l�B�n���O�������`���q�d�g�w�r�ɕ����āA���a��搉̂���l�ށB�n���O�����̖ړI�������āA�V���ȓ����������钆�A���̑��݂�m��l�X���ǂ��߂��Ă����B����̂قƂ�ǂ́A���̑�D���ȃ��[�h���[�r�[�X�^�C���ŁA���܂�b�f���g��Ȃ��Ŏ��ʉf��ɂ��ė~�����^�C�v�B�ݒ�͂�����ƎG�ȋC�͂��邵�A�����w���ԕ����x�R�����m���Ă��܂����ǎ҂ɂ́A�ǂ����Ă�������Ȃ����������Ă��܂����A���̕��A�т̎��ǂ���u��C�ǂݕK���v�̋�����ł���B |


