

 最近の更新(15年3月〜16年2月)
最近の更新(15年3月〜16年2月)
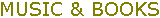
| >HOME >BOOKS |
| BOOKS |


 最近の更新(15年3月〜16年2月)
最近の更新(15年3月〜16年2月)
|
| 爆笑問題&町山智浩『自由にものが言える時代、言えない時代』(太田出版) |
| 爆笑問題の日本原論シリーズの一冊のようで、2009年から2015年2月までの世相を、月ごとに区切って爆笑問題が対談したもの。年頭部分に町山智浩が加わった鼎談が入る。もちろん面白くて噴き出すんだけど、タイトル通りの笑えない状況があって、相当考えさせられることになる。冒頭の3人による「ごあいさつ」と、巻末の大田による「あとがき」を読めば、もうこの一年だけでも思い当たることが多すぎて気が重くなる。 |
| 松永正訓 『運命の子 トリソミー』(小学館) |
|
生命倫理の授業でも21トリソミー(ダウン症候群)については比較的よく取り上げられてきた。出生前診断との関連で、21トリソミーは成人まで生きられる人が増えていることがよくいわれている。しかしそこを強調すると、生存期間が比較的長いか否かということが、生命の選別の判断基準として当然のように繰り入れられることになり、それが適切なのかどうかを、まず考えなければならない。 ここで紹介されるのは、21トリソミーに比べて非常に重篤な障害を持ち、短命である13トリソミーと18トリソミーである。著者は小児外科医を経験して小児科クリニックを開業、13トリソミーの赤ちゃんの自宅療養を頼まれたところから、その朝陽君とその家族の物語を軸にしつつ、障害のある子どもを自宅介護する親たちを訪ねていく。本書が読み手を引きこみ深く考えさせるのは、著者が小児外科医としての経験と家庭医としての経験とを併せ持ち、医師としての視野も広く、予断なくいろいろな人に会って話を聴く力があるからだと思う。親たちにもいろいろな考えがある。たくさんの誤解と戦ってきたはずである。そんな親たちが、著者に率直に語っているのは、文章には書かれていない著者の関わり方への安心があるからのはずだ。それによって可能となった一つ一つのサイドストーリーも重く厚い。 生命倫理の授業を、もう一段階、深くするにはどうしたら良いのか、具体的な方法はまだ出てこないが、学ぶ者に必ず読ませたい本である。 |
| 井川聡 『頭山満伝 ただ一人で千万人に抗した男』(潮書房光人社) |
|
NHKの朝のテレビドラマ『あさが来た』が好調である。私も録画して楽しんでいる。主役の波瑠さんが大好きなのもあるが、やはり実在のモデルである広岡浅子の生涯が魅力的で、ドラマは史実通りではないけれども、脚色も上手い。ところで浅子が最初に乗り出した事業が筑豊の炭鉱経営である。明治17年ごろかららしいが、少し遅れて炭鉱経営に乗り出した者の中に、頭山もいる。玄洋社員が積極的に炭鉱の権利を取得、後には夕張炭鉱にも手を伸ばしている。それもすべて、玄洋社の活動資金となった。 頭山満、玄洋社・黒龍会といえば、戦前戦中の右翼、超国家主義の黒幕であるという、紋切り型の理解のもとに、今ではすっかり忘れられている存在かもしれない。しかし、戦後左翼が低迷から抜け出せず、ニューライトもネトウヨの蔓延に絡みつかれつつ、新自由主義という「主義」というには余りにも浅薄な政治の看板に隠れてうごめく者たちの姿を見ていると、明治維新から戦中までの政治思想界を、レッテルをいったん剥がして中身を改めることが必要に思えてくる。 本書は総頁数600ページを超える大部にもかかわらず、非常に読みやすい。会話の場面などたいへん臨場感あふれる描写になっているからである。臨場感があふれるということは、それ相応に著者の脚色があるだろう、ということである。しかし、さすがに新聞人だけあって、資料収集や取材、インタビューなどは実に念入りで豊富である。筆致も上滑りなところはない。学術書ではないということを踏まえつつも、この本はたいへんな労作であり、非常に参考になり、しかもたいへん面白かった。 そもそも私の頭山満との出会いは、亡父の物好きによるものである。両親は市川市に住んでいて、中山法華寺が近かったのだが、この法華寺になぜか頭山満の像があるのである。父は興味を持って、たまたま市が募集していた、法華寺を含む歴史散歩のような企画に応募していたのだが、持病で身体が利かなくなっていたこともあって、自分で行くのも周りに迷惑をかけそうだから、代わりにお前行って来い、と命じられたのである。仕方ないのでその歴史散歩に行って、ほとんどがご老人方ばかりの参加者に混じって、それなりに楽しんではきたわけだが、私自身は頭山満についてその時はあまり興味もなかったし、案内の人に由来を尋ねても、今一つ要領を得なかったのである。 それだけでは父に報告するのも気がひけたので、法華寺に直接質問してみたところ、先代(だったか、もう一つ前だったか記憶が定かではない)の住職が親交があったという。境内には頭山のほかに蒋介石の碑もあったから、おそらく戦前から戦中にかけて、民族主義者の依頼で保護したり援助したりしたのであろうか。本書を読んでも、日蓮宗の寺というと、そういう傾向もあったかと思われる。本書にも出てくるチャンドラ・ボースの墓があるのも、杉並の日蓮宗蓮光寺である(私も学生を連れて訪れたことがある。ちなみに、中山法華寺の訪問計画もあるのだがこちらはまだ実現していない)。ただ、今の法華寺の反応は、なんとなくよそよそしい感じで、あまり触れてほしくもなく、あくまでも先代の個人的な交友によるものという言い方だった。 頭山はいわゆる「大アジア主義」を唱え、金玉均、孫文、蒋介石、汪兆銘らと親交を持ち、自らも玄洋社員も、大陸で様々な諜報活動や軍事的な支援をしていた。和平交渉にもかかわりを持っていた。満州国を立てたり日中戦争に突入したりしたことや、韓国併合のやりかたについて、頭山は反対であった。日本が主導する大アジア主義が中国や朝鮮に受け入れられる素地があったのかということになると、今はもちろん当時も大いに疑問ではあるが、欧米列強に浸食されるアジアを何とかしなければという志からの一貫性ははっきりしているし、しかしまたそれゆえに、維新政府への決起による獄中生活からはじまって、民権運動結社としてスタートした玄洋社が、現実政治からは翻弄され続けることになったのだろうか。 第一回帝国議会解散の際の暴力的な選挙干渉は、どう見ても不当であるが、著者はこのことがそれ以降の頭山・玄洋社の現実政治との距離感を決定づけたとみている。日比谷焼打ち事件については、国民大会を主催したのが頭山たちだがら、これもまたいささか分が悪いように見える。しかし、当時の国民はすでに扇動的となっていた威勢の良い世論に巻き込まれていた。社屋が襲撃され輪転機を破壊された『国民新聞』は東京の新聞で唯一政府の決定を支持していたが、主宰は徳富蘇峰である。政府と軍部と右翼と左翼、マスコミを絡めた関係性の図式で単純にとらえきれないことが分かる。 大正十四年の普通選挙法が公布された折のエピソードが私は気に行っている。頭山は普通選挙に反対で、戸主参政権を主張している。政治的意見は家でしっかり議論して、統一されるべきだという持論である。大正デモクラシー期にあって、個人主義が当然の権利として浸透してきており、反対運動を進めるように言われた内田良平は、勝ち目もないとためらうのだが、 「良平、例えば、大勢の者が一つの船に乗るとする。その船が動揺して、われもわれもと一方の舷側に寄ったら、たちまち転覆するだろう。私は昔から君が知ってのとおり、大勢の者が一方に乗れば、私一人だけでも片方に乗るという流儀だ。事の成る成らぬは別として『われらの考えはこうだ』という一本の杭を打ち立てておこうじゃないか。・・・」 玄洋社・黒龍会の「純正普選運動」は、当然のように敗北するが、たまたま十八歳選挙権が実施される時期に読んで、私は考えさせられてしまった。もちろん家制度を肯定するつもりはなく、一人一票の権利は当然と考えるが、それにしてもかつての「家」に代わって、政治的意見を議論して、意見の対立も踏まえながら一票を投じる相手を決定するような場を、例えば学校は用意できているのだろうか。 |
| ボビー・ヘンダーソン 『反進化論講座』(築地書館) |
|
STAP細胞事件の小保方晴子が手記を発表、売れているようだ。どうやら、実際の実験や論文作成の過程で、小保方氏ではない人物が大きくかかわっていたという話のようだ。そのあたりの真偽は別として、STAP細胞でいえば、小保方氏が報告した方法で再現できないのだから、悪意の有無は別にして少なくとも間違いであったと判断される。追試で実現できないものを発表すればいずれはばれてしまうではないか、それでも発表したというのは悪意がないからではないか、というのは素人の当然の思いつきだが、たとえばベル研究所のシェーンのケースなどは良く検証されており(『論文捏造』)、STAPのケースもこれに重なる。 それにしても、このケースが耳目を集めるのは、「もしかすると本当はSTAP細胞はできているが、何らかの理由で隠蔽されているのでは?」というような陰謀説(しかも彼女が美女)に魅力を感じるからであろう。一般人は科学には弱いので、トンデモ話を期待しがちなのであり、カルトにはまる心理や通販で健康食品を買う心理ともそれほどの違いはない。おかしなカルトに対して科学的な方法で反論しても、その反論にいくら非の打ちどころがなくても、あるいは非の打ちどころがなければないほど、カルトに対抗する力としては弱い。 聖書根本主義は、信仰の自由の問題で割り切ることはできない。教育に与える隠然とした影響力は無視できず、学校教育の中に天地創造説を入れて進化論を潰す試みは、これまでにも相当の事例がある。いくら進化論が創造説よりも説得力があると言っても、例えば古い地層に埋まっている化石と新しい地層に埋まっている化石で進化を説明しても、「いやそれは、そう見えるように神様が作ったんだから!」と言ってしまうので始末が悪い。それでもさすがに神様ではちょっと分が悪くなってきたところに作り出されたのが、インテリジェント・デザイン(ID)説である。これだけ複雑で精妙な自然を作りだすことができるのは、超越した知性でしかありえないという理屈で、「単なる仮説に過ぎない」進化論に、選択の幅を与える仮説として対抗しようとしているのである。まあ、テレビなどで安保法制反対を言うなら同じだけ賛成の意見も入れろというのも、同じような発想ではある。 これに対して、ID説と全く同じやり方で、「空飛ぶスパゲッティ・モンスター」が世界を作ったと「論証」するのが、この「空飛ぶスパゲッティモンスター福音書(原題:The Gospel of the Flying Spaghetti Monster)である。著者は「空飛ぶスパゲッティ・モンスター教団」の「教祖」を名乗り、ID説が科学を名乗ってデザイナーの正体をキリスト教の神であるとは言わないのを逆手にとって、そのデザイナーこそ空飛ぶスパゲッティ・モンスターであると主張し、その「証拠」を次々と提示して行く。もちろん、実際の教育委員会にも、ID説だけでなくスパモン福音書も教えるように申し入れている。 アメリカにおける宗教右派の問題は、特に子どもたちへの影響を考えると、決して笑いごとではないのだが、こういう抗議の仕方もあるのかということで、自分もスパモン教会に入信したくなるほどだ。ホームページを見ると、Tシャツなどステキなグッズもあるようだ。 |
| 家庭養護促進協会大阪事務所編 岩崎美恵子監修 『子どもの養子縁組ガイドブック』(明石書店) |
|
要保護児童の養育をどこで行うのか。欧米では家庭的環境(養子・里子)が過半数であり、オーストラリアのように9割近いところもあるが、日本は2割に満たない。ちなみに韓国も少なかったが、先進国としてどうかということで様々なキャンペーンを張って、3割を超えるようになったという。 子供にとって、家庭的環境で育てられることが望ましいということは、よく言われていて、実際に良い里親・養親によって育てられることは子どもにとって幸せである。ただ中には里親に問題があることもあるようで、アメリカのテレビドラマを見ていたら主人公が里親に恵まれなかったエピソードが出てくることもある。 血統主義の文化が長く戸籍管理が厳格な日本では、特に養子については、全く血縁のないところから取るということは抵抗が強く、跡取りのためと目的も限定されてしまう。アメリカでは中産階級以上の人には実子があっても里子や養子を取る人がいる。それは自分のニーズではなく子どもの側のニーズを満たそうとするからである。 本書の著者は昭和39年から養親・里親を希望する人と子どもたちの仲立ちをしている公益財団法人で、すでに1000件を超える縁組を実現してきた。本書では特別養子縁組・普通養子縁組に関する法律や実務はもちろんだが、その長い経験から、実際の様々な問題点やトラブルまで紹介している。書類の記入例などもある実用的な内容であるが、実際に養子縁組を考えている人にはもちろん、日本の児童福祉の現状を知る上で欠かせない文献の一つだと思う。 |
| 栗原俊雄 『遺骨』(岩波新書) |
|
副題は「戦没者310万人の戦後史」。著者は毎日新聞記者で、戦後史の取材の中から遺骨収集問題に着目し、実際に参加しながら問題提起を続けている。 だいぶ前に、不動産のいわゆる事故物件の話題をテレビで見ていたら、コメンテーターの誰かが、そんなこと言ったら東京なんてみんな事故物件だよ、と発言して、なるほどというか、大事なことを思い出させてくれるよな、と思った。東京大空襲や、広島、長崎など、一瞬のうちに何万もの遺体に埋め尽くされた時、生き延びた人にはその弔い、いや始末が任されることになる。正確に数えることもかなわず、火葬も追いつかず、止む無くまとめて埋められた遺体は、しばらくして掘り返されて改めて火葬されることもある。 本書で意表を突かれたのは、東京都にもまだ収集すべき遺骨が一万体も眠っている場所があるということだ。激戦地として知られる硫黄島である。復帰後も全島が自衛隊の基地となっているため、遺骨収集にも困難があり、ましてや旧島民の帰還も果たせない。もちろん、沖縄戦の犠牲になった19万人近い人々の遺骨収集も。 遺骨収集ということの意義を、私は長く誤解していたと思い知らされた。遺骨という「もの」は、もちろん大切である。しかし、その遺骨がどのようにそこにあったかを明らかにすることで、その人の最期が分かる。その人がどのようにして亡くなったのかということが、遺族にとってはとても大切なことであり、さらには私たちすべてにとって知るべきことなのである。 この夏も、数名の学生を伴って千鳥ヶ淵戦没者墓苑を訪れたが、先立って立ちよった靖国神社に比べて、その静まり返る様子そのものが彼らには重く受け止められたと思う。遺骨収集に様々な思いを持って汗を流す人たちの中には、彼らと同じ世代の若者もいる。 |
| ケン・リュウ 『紙の動物園』(早川書房) |
| 新ハヤカワSFシリーズの新刊。そしてこれは、私にとっては間違いなく、ここ数年来読んだSFの短編集としては、もっとも面白かった一冊。中国系アメリカ人の著者は、中国だけではなくて広くアジアの文化に目配りし、アメリカの中国人という立場を、異なる文明の交錯を物語として置き変えていく技に極めていく名手である。ある物語の呪術は、別の物語では科学である。ある物語では現実の歴史が綴られるが、それは別の物語に裏腹の神話を紡ぎ出す。そしてどの物語でも、深い愛が謳われる。どの作品がどう、というのもはばかられる、すばらしい短編小説の集合である。「もののあはれ」はいささかこそばゆいにせよ。 |
| 畑村洋太郎 『技術大国幻想の終わり』(講談社現代新書) |
|
またぞろ日本の危機感をあおるタイトル本、と危うくスルーしそうなところ、著者名にピンと来て思わず手に取った。六本木森ビルの回転ドア事故検証に始まる、著者の『危険学のすすめ』がたいへん面白く、技術倫理の授業にもしばしば引き合いに出すのだが、本書でも取り上げているように3.11の事故調査・検証委員会委員長も務めている。 第一章の現状分析が、まずしっかりと読みごたえがあるし、著者の分かりやすく説得力のある書きぶりに引き込まれる。「日本人がつくるものが優れているという幻想」「職人の技幻想」「品質幻想」の三つを指摘する。第二部では、「価値」を重視すること、しかもそれをはっきりと「お金に換算して」とらえよということが指摘される。 この本を読み終わった頃に、日中がインドネシアで熾烈な受注争いをしていたジャカルタ・バンドゥン間の高速鉄道計画が中止になった、というニュースが届いた。どっちにしてもお金がかかりすぎるし、それだったら普通の特急で十分、ということのようだ。本書の3章で著者が、安倍晋三総理がやりたがる原発と新幹線といったインフラ輸出は、相手国が欲しがっているものではない、と指摘していた通りのことが起こったわけだ。「移動手段でいったら、高速鉄道よりも普通の鉄道のほうが必要」、「むしろ新興国の都市で深刻化している渋滞緩和のための都市交通の解決策として」鉄道が重要、と言っている。まさに当のインドネシアについては、JR東日本が埼京線中古車両180両、横浜線中古車両170両を、技術支援付きで輸出していることを紹介している(こっちはあまりニュースにならないが)。ベトナムでのオートバイのシェアを中国から取り戻したホンダや、インドネシアのワンボックスカー用のデンソーのカーオプションの話など、はたとひざを打つようなことばかり。 今後の対応に必要なことはやはり教育にありというまとめもまさにその通りなのだが、ではどのような教育システムが作られるとよいのかについては、われわれが考えていかなければならないようだ。 |
| 鵜飼秀徳 『寺院消滅』(日経BP社) |
|
亡父は福井県の出身で、宗旨は真宗大谷派、先祖代々の墓も福井に在った。とはいえ、父は戦後東京で大学を出て以来、福井で生活したことはなかった。福井の祖父母も亡くなり、今の住まいの近くに真宗大谷派の寺院を見つけ、墓所も寺の境内に移してあった。おかげで、父が亡くなった時にはわれわれ息子たちも戸惑わずに済んで、いろいろあったけれども墓を移しておいてよかった、福井にあるままだったらえらいことだった、と言っていた。 しかし、この本を読むと、人口の移動はもとより、菩提寺を地方から都会に移すことで、過疎地の寺院がどんどん消えていっていることを、改めて認識することになった。そういえばどこかの無住寺の本堂が倒壊したニュースを聞いた記憶もあるが、本書を読むとそのようなことは珍しくもないようですらある。寺院や僧侶の側からの改革も必要で、いろいろな試みも紹介されているが、限界集落の寺が見捨てられていく事の深刻さは、そのような改革によってどうにかなるものではない。尼寺の状況など、知らないことだらけだった。国家との結び付き、特に戦争協力に関しては、やはり表に出てきにくい汚点である。もっとも、キリスト教もほとんどの教派が協力させられ、非協力を貫いて弾圧された教派はわずかであったのだが。 僧籍を持つジャーナリストならではの視点が生かされて、重要な問題提起の本になっている。 |
| 木田元 『哲学散歩』(文芸春秋) |
| 日本の現象学、とりわけハイデガーの専門家で、「反哲学」の概念でも知られていた木田元が昨年(2014)に亡くなり、その最後の連載エッセイになったもの。古代から現代まで、哲学者の簡単な紹介と興味深いエピソードが綴られるが、著者のハイデガー哲学との出会いにからめたカントとのかかわり、不思議な臨場感のある短編小説のような「マッハを想う」、そして巻末のレーヴィットとハイデガーに関する複雑な心境など、著者の人柄がよく現れたすばらしい読み物になっている。オムニバスのエッセイ集でありながら、哲学史のサブテキスト、いや教科書そのものにも成り得そうな一冊である。 |
| 雁須磨子 『こくごの時間』(秋田書店) |
| 実家の押し入れを整理して出てきた国語の教科書を、喫茶店の本棚に置くという設定で、お店に来た客などと教科書に載っていた作品とを絡めてモチーフにした、オムニバス短編形式の漫画。ペンネームが凄いのだけど繊細な心情を描いていてそのギャップがまた面白くもある。こういう本を読んでいて気付かされるのは、義務教育で学ぶことの意義、と言っちゃったらいささか牽強付会だろうかなあ。たとえ間違って覚えていても、ああそういえばそんな話、あったなあ、という共通体験は、単に知識としてではなくて、感情体験としてコミュニケーション上けっこう重要なのではないだろうか。同じものを同じように読んで、同じように感じたり、逆に全く違うことを感じたり、その確かめ合いや同意や驚きは、貴重な経験になる。数学や理科や社会でもそういうことはあると思うが、国語はとりわけ大切ではないか。私の専門の倫理でも、だれかこういう漫画を描いてくれないかなあ。 |
| マーサ・ヌスバウム、アマルティア・セン編著 『クオリティー・オブ・ライフ 豊かさの本質とは』(里文出版) |
| 1988年、ヌスバウムとセンが企画したWIDER(World Institute for Development Economics Research)のシンポジウムの論文集のうち、第一部を翻訳したもの。もう四半世紀前だから、QOLの概念が医療分野に浸透し始めたころということになるだろうか。センを含む一流の経済学者と哲学者が、QOLとは何か、そしてそれをどのように測定するのかという根本問題を論じ合う、たいへん充実した内容とスリリングな構成になっている。まずロールズ、ノージック、センの流れで「何の平等か?」の論点を整理したコーエン論文は、何が問題なのかを分かりやすく説いていて初学者にありがたい。そしてそれを受けて展開されるセン自身の反論も興味深く、潜在能力アプローチの可能性の広がりを示唆している。さらに3章では哲学者が、4章では経済学者が、これらを受けて論評する・・・といった具合に、シンポジウムの展開が現前するような構成が取られている。今となっては古典的な論争になるのだろうが、論じられている内容はピケティが話題になるこの時代にこそ踏まえておきたいものである。 |
| キジ・ジョンスン『霧に橋を架ける』(東京創元社) |
| このところSFの出版が盛んなのかな?と思わせるくらい、早川と言い創元と言い、文庫じゃないソフトカバーのシリーズをよく出しているなあ。というところで、これは「創元海外SF叢書」の第三弾。帯によると「本の雑誌」の2014年度SFベスト1なのだそうである。ヒューゴー、ネビュラのダブルアワードの表題作は、異世界を舞台に、川の上にかかりそこに棲む凶暴な生物が襲いかかる深い霧で隔てられた両岸を、はるか高みにかかる橋でつなごうとする技師、彼をとりまくその地の人々とのかかわりを描く、感動的な作品である。ただ私はなんとなくイアン・ワトスンの「黒き流れ三部作」を思い出してしまって、もちろん短編なので比較するべきではないのだが、そこまでの傑作かな、という気もしてしまうのが申し訳ないところである。むしろ世界幻想文学大賞をとった「26モンキーズ・・・」が気にいった。短編らしい落ちもそこまで意外性はないのだが、やはり人物の書き込みと設定のファンタジー性が、このような作品ではより生きてくるように感じる。さらに短い「陳帝、死者の国」など、ショート・ショートを思わせたり、「噛みつき猫」など、あきらかに非SFで人物描写が光る短編もあったりと、一つ一つが印象に残り、短編集としての満足度は極めて高かった。 |
| エリック・R・カンデル他『カンデル神経科学』(メディカル・サイエンス・インターナショナル) |
| カンデルらによる神経科学の教科書、第五版の待望の翻訳である。神経科学の専門家や学生なら原書で読めば良いのだろうが、それにしても1600ページもの大著であるから、気軽に日本語で読めるのはありがたいだろう。まして私のような非専門家にとっては言うまでもない。カラー図版が多いために紙の裏映りが気になるという声もあるようだが、本の厚みと価格を抑えようとすれば(それでも14000円だが・・・)我慢できる範囲だ。私にとっては、リファレンス的な使い方には内容の豊富さが当然ありがたいのだが、えいやっと開いたページを読むのがとても楽しい。たとえば、「運動単位と筋活動」などという項目は、私の専門からは離れているので、こういう本がないと読む機会がないが、常日頃思っている「EXILEの人たちとかのダンス、すごいなあ」というようなことが、「多くの筋は骨格に対し中心を少し外れて付着しており、1つ以上の軸回りの回転を引き起こす。そのうち1つの動きが不要だとすると、神経系は他の筋を活動させ、望まない動きを抑制しなければならない。」なんて一節を読むと、なるほど、そうだと納得するわけである。EXILEもすごいけど、やっぱり神経、すごいわ!と感動を禁じ得ない。適宜配置された小見出しの切り口が、読みやすさに貢献している。専門家以外にはなかなか手を出しにくい価格なのだが、専門家ではないからこそ身近に置いておきたい本なのである。 |
| 中村智志『あなたを自殺させない 命の相談所「蜘蛛の糸」佐藤久男の闘い』 (新潮社) |
| 2002年、自殺率ワースト1位の秋田県で、事業に失敗して自殺を考える人を救うためにNPO法人「蜘蛛の糸」を始めた佐藤久男。彼もまた、うつ病を患い、不動産事業で倒産を経験している。カウンセラーやケースワーカーの専門性を疑う余地はないにせよ、事業に失敗した人を救うという専門性は佐藤のような人に敵うまい。実際、彼の相談は、カウンセリングの鉄則に結果的に則っている。その上で、経験則に拠っているために、カウンセラーの悪しきプロフェッショナリズムに陥ることなく、相談者を直接救うのみならず行政はじめ周りを動かす働きをなしている。著者の丹念なルポルタージュによって、佐藤の人物像、彼の元を訪れる人々、家族をはじめ彼を支える人々の姿が生き生きと浮かび上がり、どんな立場の人が読んでも感動と勇気を与えてもらえる本になっている。 |


