

 最近の更新(14年9月〜15年2月)
最近の更新(14年9月〜15年2月)
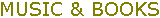
| >HOME >BOOKS |
| BOOKS |


 最近の更新(14年9月〜15年2月)
最近の更新(14年9月〜15年2月)
|
| マーサ・C・ヌスバウム 『経済成長がすべてか? デモクラシーが人文学を必要とする理由』(岩波書店) |
| ヌスバウムと言うとフェミニズムの印象が強いのかもしれないが、私はアリストテレスを読んでいて注釈によく引用されていて名前を覚えたように思う。古代哲学の研究から現代の法哲学まで、幅広くも深い思索に立って、現代の教育について、国際的にも広い視野から考察した内容になっている。私は主として高等学校公民科教育について、特にその中の『倫理』について研究する立場にあって、かつて必修科目『倫理・社会』があったのに、現在では選択科目となってしまった(しかも、カリキュラム上の立場は同等である『政治・経済』に比べて明らかに開講されにくい)『倫理』について、どのようにその重要性を語るべきか日々苦悶しているだけに、本書は実に心強い指針となる。しかも自分の専門外ではあるが同様に芸術科目についてもその重要性を感じていて、その点でもヌスバウムが同じ主張をしていることにも、さらに励まされる思いである。人文学と芸術は民主社会に生きる人間にとって必要であることを、アメリカの伝統的な教育や、インドのタゴールの教育思想を手がかりに説いていく。しかし本当に不安なのは、もともとこれらを重視していたはずの儒教の伝統に従う日本の教育で、人文学や芸術が片隅に追いやられていくのは、自由や民主主義を国民から少しずつ奪っていくために、段階的に計画的に進められているとしか考えにくいことである。 |
| 小田切徳美 『農山村は消滅しない』(岩波新書) |
|
私は高校公民科教育関係の仕事を時々しているのだが、教科書などで「少子高齢化」を取り上げるときの扱いに、あんがい難儀している。というのも、いわゆる「増田レポート」がメディアでもセンセーショナルに取り上げられて、かつての「限界集落」どころではない「消滅可能性都市」などという言葉が独り歩きし始め、豊島区ですら消えてしまう!という危機感がわき上がっているからである。実際に「増田レポート」に目を通せば、「消滅可能性都市」やその可能性がさらに高い都市というのも、目安になる基準をもとに定義して使っている言葉であって、それこそ「日本の人口は減っているのだから、日本が消滅するのか?」と考えれば、そういうことではない(と思っていたら、逆に「だから消滅都市なんておかしい」という批判になったりするようだ)。 とはいえ、本書に挙げられているような、増田レポートの悪影響には、本書が指摘するようにその背後には財務省や政権の意図が見え隠れしている可能性は高い。終章にまとめられている通り、「国民は国家の為にある」という逆転した価値観に立つ「財政の関数化」があって、農山村の再生などという財政に不利なことはやめて、地方の高齢者は都市にまとめてしまえと言う、明らかに乱暴だが「財政の関数化」によって正当化される本音が恐ろしいのである。政府の少子化対策がおざなりに見えるのは、いよいよ困るところまで効果を(わざと)上げないうちに、外国人労働者を受け入れて済ませようとしているのではないか。英語教育を義務教育で普及させているのは、外国で活躍する国際人を育てるためではなくて、カタコトの英語が話せないと、飲食店や介護施設で意思疎通できなくなるからではないか。 本書はフィールドワークに基づく豊富な実証例をもとに、農山村がいとも簡単に「財政の関数化」で消滅させられることはないということを、希望を持って説く。それでも、農山村の置かれている状況の厳しさには変わりない。本書で言われる「田園回帰」に、柔軟な思考でさまざまに取り組んでいかなければならないし、「増田レポート」と言われるがゆえに矢面に立つ増田寛也も、農山村の消滅を望んでいるわけではないのであれば、国レベルで財務省や政府の考え方を糺して、本気の少子化対策と東京一極集中対策を進めさせてほしい。 |
| 朝日新聞「働く人の法律相談」弁護士チーム 『会社で起きている事の7割は法律違反」(朝日新書) |
| 本をネットで買うことの多くなった時代、本は題名だなあ、ということをしみじみと思い知らされた一冊。タイトル買いしてしくじった感が濃厚。著者名がコレだから気づくべきだったのだが、中身はほぼ見開き2ページで労働問題のQ&A集をまとめたようなもの。この程度なら、それこそネットで検索すればいくらでも情報が手に入る。本になる以上、個々の問題についてもうちょっとは掘り下げた内容を期待してしまうのだが、見事に肩透かしを食らってしまった。 |
| いぬんこ 『おかめ列車』/『おかめ列車 嫁に行く』(長崎出版) |
|
うちの次男は子どもの頃、機関車トーマスが嫌いだった。もともとあまり好きではなかったようなのだが、テレビで見ていて何かの理由でトーマスの顔面にジャムがかかってしまう場面があって、それ以来、決定的に嫌いになってしまった。ほかにも理由があると思うが、人間の顔でありながら連続性のない表情の質感は確かにつかみどころがなく、そこにさらにべっとりしたジャムが加わる動画は異様に映ったようである。それではこのおかめ列車はどうだろう? ストーリーは、どちらも子どもの夢であり、ファンタジーである。しかし、この出版社の絵本にどことなく共通していた、生々しい質感が練り込まれたような色合いや遠近感を狂わせるような絵柄、アセチレンランプに照らされた光とその背後に広がる深い闇を思い出させるような祝祭感、と、われわれの世代には昭和のノスタルジーを感じさせつつ、おそらく子どもたちには見たことのないスペクタクルとして興奮を与えるのではないだろうか。家にはそういう子どもたちがいなくなってしまったので、試しようがないのが残念である。それにしても、そもそもおかめ列車とかひょっとこトラックとか、どこから発想が生まれるのだろうか。すごい。 ところで、この絵本は今はいずれも絶版で、古本にけっこうな値段が付いている。出版社が「こびとづかん」シリーズのヒットで多角化の拡大路線に走り、トラブルから「こびとづかん」シリーズも他社に権利が移り、倒産してしまったらしい。人気のあった「わんぱく小学校」シリーズや「給食番長」シリーズも他の出版社から再発売されているようだが、この「おかめ列車」も、ぜひ手に入りやすくなってほしいものである。 |
| 山崎喜比古、戸ヶ里泰典編 『思春期のストレス対応力 SOC』(有信堂) |
| SOC(Sense of Coherence, ストレス対処力)は、20年ほど前に、アメリカの健康社会学者アントノフスキーによって提唱され、その後実証研究が進められてきた概念である。本書では一つの中高一貫校において、最大3年間にわたって、同一生徒のSOCを継続調査した研究を含む、わが国での実証的研究として極めて充実したものとなっている。もともと、ストレスが医学生理学の概念であったことからすれば、本研究のように、医学や社会学の立場から研究されてきたこともあって、整理や環境とのかかわりに注目してその連関から捉えるSOC概念はたいへんわかりやすいものになっていると言える。私の所属する研究会では、本書でも言及されているセルフエスティームについて調査をしてきているので、その意味からも関心を引かれる内容であり、調査において身体的要因や環境的要因に目配りしているので、より信頼のおけるものになっている。これからの思春期調査に大いに活用されるべきである。 |
| 速水敏彦 『仮想的有能感の心理学』(北大路書房) |
| 副題に「他人を見下す若者を検証する」とあるように、2006年に著者が講談社現代新書から『他人を見下す若者たち』という本を出したところ、プロモーションもあって話題を呼んだ一方で、またぞろお決まりの若者批判かという目で見られ反発を買った面もあって、発達や教育分野で堅実に活躍している心理学者である著者としては不本意であったかもしれない。本書は、そこで提示された仮想的有能感という概念について、やはり地道に、オーソドックスな方法で実証的研究を進めた成果の報告である。仮想的有能感は様々な既存の特性因子概念と統計的に比較検討され、アジア諸国や白人系北米人などとの比較から文化の影響についても吟味される。教育や就職、問題行動についても検討され、リアルな有能感につなげるための道筋にも触れている。 |
| 小出真朱と@wondernunothc 『ねぞうアートの本 寝ている間にHAPPY赤ちゃん写真』(ぶんか社) |
| 自分の子どもが小さかった時、その寝顔や寝姿があまりに可愛くて、見とれていたり、写真やビデオに収めたりした経験のある人は少なくないと思う。私が思い出すのは、二人の息子たちの様子撮ったビデオを編集して、田舎の親戚に見せようと持って行った時のことである。運動会やら誕生日やらのイベント的なものに交えて、二人が並んですやすやと眠っている映像を入れたのだが、仕上がった時に見直していて「全く動きがないのに、ちょっと長かったなあ」と反省したものの、まあ見せていて飽きられたら早送りすればいいか、と思って持って行ったのである。ところが、集まった親戚一同にいざ見せてみたら、この場面が始まると、みな静かに見とれて「いやーかわいいねー」「かわいいねー」ともっとも評判がよかったのである。眠っている赤ちゃんは、本当にかわいい。あまりに可愛くて、涙が出ちゃったり、笑っちゃったりする。いつまでも見ていたい。しかしクリエイティヴな人は、そこからひと仕事してしまうようなのである。小物や布や台所用品などを配置して、一つの情景を作り上げてしまう。すごく手が込んでいるものはさすがだが、それよりもまさにあり合わせのものでササっとやりましたというようなものが素直に笑える。でもどんなシチュエーションにおいても、眠っている赤ちゃんはとにかくかわいい。 |
| 海老原嗣生 『いっしょうけんめい『働かない』社会をつくる」(PHP新書) |
| 副題は「残業代ゼロとセットで考える本物のエグゼンプション」。ホワイトカラーエグゼンプションがよくわからん、というのがまずあって、この本の帯に「過労死促進法か、改革の切り札か、いったい誰トク?」といううたい文句に、まず興味を引かれた。ただそれ以前に、それも含めた雇用問題の先が見えない、という実感があるので、自分としては何か定まった視点を全体的に提供しているものが欲しかったのだが、読んでみると本書はまさにその全体像のイメージを描きつつ論じていたので、私にとってはかなりトクした気分で読んだ本となった。欧米型雇用と日本型雇用とがそもそも根本的にどこが違うのか、ということがまず良く分かっていなかったというのが実感。そしてそれぞれにはどのような、雇用者側と労働者側とそれぞれにとってのメリット、デメリットがあるかについて、詳しく分かりやすく述べられている。その上で、著者の主張は、日本型と欧米型のいわばイイトコ取りをした仕組みを作ることである。それを実現するとして、過渡期に乗り越えなくてはならない課題は多いとは思うが、かといってホワイトカラーエグゼンプションであれ何であれ、制度改革を主張する側も反対する側も、全体像を見せない議論に終始しがちであるから、こういう本を読んでおかないと、定見が持てないまま流されてしまう。 |
| 三澤洋史『オペラ座のお仕事』(早川書房) |
| 著者は新国立劇場の合唱指揮者。ウチの次男がオペラの勉強をしているのだが、私にはまったく知識がなく、話についていけないのも癪なので、たまたま書店で見かけたこの本を買ってみたのだが、オペラの魅力や知識もさることながら、この著者の人柄や経歴がとても面白い。親は建設会社でもともと音楽的な環境にはいなかったのだが、いろいろなきっかけではまりこんでいく。偶然もあるのだがこれと決めたら自分で道を切り開いていくところが痛快である。「芸大のピアノ科」を目指して、正式にならったことがないのにピアノ教師の門をたたき、さすがにそれは無理だからと声楽科に入り、籍を置きながら指揮を学ぶ。でもこれ、気をつけて読まないといけないのは、この先生、どれもこれもこなしているのであって、留学先のベルリン芸術大学指揮科を首席で卒業するほどの人だからこその説得力である。並みの音楽好きではこうはいかない。それでも、総合芸術たるオペラの合唱指揮者というポジションで、著名な世界中の、人柄国柄にも個性あふれる(中国公演の話が一番面白かった)歌手やオケの指揮者や演出家たちとわたり合い、時には戦い、結果で納得させるやり方には、感動させられるだけでなく、学ぶべきものが多い。 |
| 原田実『江戸しぐさの正体』(星海社新書) |
|
知人を通じて聞いた話だが、今の教育改革で、文部科学大臣は道徳のイメージとして江戸時代を考えている、ということだった。それ以上は詳しく聞かなかったし、所詮はまた聞きにすぎないのだが、それを聞いて私は「ふーん朱子学あたりのイメージかね、教育勅語も結局は儒教道徳だしねえ」ぐらいにしか受けとめなかったし、まあそれでも十分に厄介ではあると思ったが、そのときはまだ私は迂闊にもこの「江戸しぐさ」のことを知らなかったのである。本書は、この「江戸しぐさ」なるものが、まず内容的にひどくおかしいということから、その成り立ちをたどり、今日のような事態に至った道筋を明らかにしている。 そもそも「江戸しぐさ」は1980年代に、反骨の知識人芝三光が作り上げたもので、なんの歴史的根拠もなく、実際の江戸風俗とは無関係だった。芝の語り口からすると、どうもSF小説やファンタジーであるかのようなとぼけ方もあって、史実に基づいていないことがばれるのはかまわないというか、むしろこれはちょっとしたほら話なんだよというほのめかしを感じるのであるが、これが、コンサルタントやマスコミ出身の後継者たちによって、創始者の経歴から何からが都合よく改変され、祀り上げられていき、文部科学省の道徳教材にまで取り上げられるに至ってしまったようなのである。 この後継者たちのやり方のいかがわしさにはあきれるばかりで(私自身、勤め先の様子が変わって以来、しばしばかかわってくるコンサルタント業界とその関係者にしばしば感じられるいかがわしさに通じるものがある)、たとえば「江戸しぐさ」に歴史的な裏付けがないのはもともと秘伝であって、伝える人たちが幕末に皆殺しに在ってしまったからだという設定自体が、これはもう、ありとあらゆる陰謀ヨタ話のレベルにあることは明らかである(このあたりは、ちょっとググれば歴史的におかしいという批判がたくさん出てくる)。 まあ、当人たちの発言や著作を読めば、これがゴミ屑に過ぎないことはすぐにわかるのだが、あまりにもくだらないので、まともな学者が相手にしないことが悪影響ともなって、恐ろしいことにこのオカルトが崇敬されてしまうメカニズム、そして法則化や道徳教材という形で公教育に取り込まれてきたのが現状である。道徳教材『私たちの道徳』は、文部科学省が制作し、教科書検定もないままに、学校で使われている。大臣はわざわざこのテキストは家庭に持ち帰って家族も読めという。幸いにしてこのテキストで道徳教育を受けさせられる世代が我が家にはいないのだが、文部科学省のホームページではすべて公開している。該当部分を含むファイルはコレ。 ここでは、七つの「江戸しぐさ」が紹介されている。「かさかしげ」は当時の傘の構造からすると、傘をすぼめる方がはるかにスムースであるし、江戸庶民にはこの種の傘はまだ高級品でそれほど普及していなかったはずだとか、「こぶしうかせ」はもともと渡し船のエピソードとして登場しているが、渡し船には座席がなく、荷物も馬も乗りこんでいたとか、つっこみどころだらけであるが、ほかのものもふくめて、結果的にごく当たり前のマナーを「江戸しぐさに学ぼう」というもっともらしい(けれどもインチキな)テーマでまとめたものである。それにしても気になるのだが、このテキストを編纂するときに、出典のあるものはいくらなんでもチェックはするだろう。そのときに、乗り物の出入り口に仁王立ちになってはならないとか、トマトスープが健康に良いとか、どう考えても江戸に無関係なものが堂々と登場することはすぐわかる。江戸町人虐殺説だって、まずはバカバカしいと思うだろう(だからすぐに否定することはないが、そこから調べればすぐおかしいと分かるはず)。そこでちょっとこれは使えないぞと思わなかったのだろうか? それとも、思ったとしても止められない力が何か働いたのだろうか? せっかくなのでついでに、続きのページも見てみるが、作業用の空欄が付いているページなどはどれも陳腐なもので、国語や社会のワークブックのように、単に認知的能力を測るものにしかなっていない(頭のよい子は条件に当てはまったり類似した事例を思いつく、ということ)。ちょっと長いお話である(出典がないので著作者の創作であろうか)『最後の贈り物』も、これだってかなり微妙である。全体としては泣ける話に仕立てたように見えるが、そもそも主人公は誰からともしれないお金を使ってしまってそもそも良かったのか(ロベーヌとかジョルジュとかフランス風の名前なのでフランスでは良いのか)、それ以前にこの状況ではジョルジュ以外の誰かからのものとは考えられないということもあるけれども・・・。そして、ページを繰るとドーンと見開きで・・・みつを。他の部分でも、野口英世の医学的業績が不正確なままだったり、いかにももっともらしく仕上げました、という作りである。 もっとも、教材テキストの内容がいかにもわざとらしかったりもっともらしかったりするのも、だんだん子供たち自身がわかってきて、いわゆる裏面的コミュニケーションが成り立ってくるのである。率直に言えば、道徳教育といわれているものは、学校でやろうとしても基本的にはうまくいかない(学級集団の質によって全く違ってしまう)ので、現場ではいかに当たり障りなくしのぐかという工夫を凝らしているというのが実際のところである。実践事例はいろいろなものがあるけれども、同じようにやってうまくいくとは限らない。だから、実際に使えるのは「面白い教材があったよ!」という部分に過ぎないのである。で、この国定テキストの江戸しぐさを見れば、一つ一つは陳腐な事例なので、それだけ並べたのでは単なるマナーテキストでしかない。そこに江戸しぐさというおしゃれっぽいタイトルがついて、300年の秘伝とつけば、体裁が整うわけである。 今は「江戸しぐさ」で検索すれば、ドッと問題の指摘が出てくるので、本書の内容のチェックにもなるが、その一方で「NPO法人江戸しぐさ」のサイトも見れば、これがまかり通っていることの不気味さも伝わる。今の教育改革は、これまでとはケタ違いの危険性があると思う。この江戸しぐさのようなキワモノや、今や通用しないレベルの野口英世の偉人伝のようなマヤカシが使われるということになると、話はそこにとどまっていられなくなる。それは学校教育が「もう真理には従わなくて良い」というメッセージを出しているという危険性である。 |
| コワコフスキ『哲学は何を問うてきたか』(みすず書房) |
| 言わずと知れた名著である。哲学の全くの初心者が読むには難しいが、多少の関心を持ってきた者、哲学に限らずともヨーロッパの文学や歴史に興味のある者にとっては、哲学再入門としてこれ以上のものはないと思う。実は(というか、この本の感想の流れで書くのはとんでもなくおこがましいのは当然と承知しているが、その上で)今、一般読者に向けて、高校の倫理ってこんなに面白いんですよ!的な本を出そうと、研究仲間で取り組んでいるところなのだが、哲学にせよ倫理にせよ、語り口も大切だし、それ以上に、人物とテーマをどう結び付けるかが肝心なのである。本書で扱われているのは30のテーマで、それぞれ一人の哲学者を主としている。1テーマ=1人わずか8ページで、読みやすいけれども密度は濃い。そして、それぞれのテーマで数多くの問いかけが、読者に投げられる。どのテーマも、最後は必ず、問いかけで終わっている。つまりそれが哲学である。 |
| 安富歩 『生きるための経済学』(NHKブックス) |
| 副題は「〈選択の自由〉からの脱却」。市場と書いて「イチバ」とも「シジョウ」とも読む。経済学は抽象的な「シジョウ」概念にとらわれ、実は複雑多様な経済現象も生身の人間が行き合いやり合っている「イチバ」現象なのだという視点が先ず提示される。そこから、経済学が物理法則にも反する前提に立っていること、〈選択の自由〉の不条理性を論理的に解き明かし、フロムの思想からポラニーの創発を手がかりに、「生きるための経済学」を導こうとする。論旨の展開は説得力のあるもので、バブル崩壊や結婚の失敗など著者の体験に基づくエピソードが絡むなど薬味も気が効いていて、特に私のような哲学的興味からの読み手には一気に読める楽しさもある。しかし孔子の「仁」に活路があるという結論には驚いた。まさかここでも出会うことになるとは。 |
| 三浦國雄 『「朱子語類」抄』(講談社学術文庫) |
|
高校公民科の『倫理』にかかわっていると、いくつかのミッシングリンクがある。かつて『倫理・社会』ができた時代に取り上げられた思想が、50年間準拠枠となって、いまだに教科書と入試を規程し合っているのである。なので、新しい思想が入ってこないのはある程度は理解できるし、しかもさすがにこちらは徐々にではあるが取り入れられてくるのだが、通り過ぎた時代に忘れ去られた思想は、なかなか入り込めないのである。だから、たとえば「ローマ時代の哲学はどうなっていたのか?」「鎌倉時代以降の日本の仏教はどうなっていたのか?」などなど、ふと気付くと不思議な空白が空いているのである。 中国思想についても同様である。諸子百家のあとは、ぽっかりと空白になる。そして突然、宋明の朱子学と陽明学が、しかし日本の儒学を説明するための流れでのみ登場する。そしてまたプツリと姿を消す。 こうしたミッシングリンクが気になりだして、日本思想をある程度理解しようと思えば、大陸の儒学の流れは知っておく必要がある。というわけで、手始めに読むとすればやはりこれであろう。何せ、『朱子語類』そのものは全140巻、汲古書院からの訳注書も2007年から20年がかりで刊行中という、気の遠くなるようなしろものである。本書も十分な読みごたえがあるが、これでもエッセンス中のエッセンスというべきであろう。また、例によってこれも弟子のノートであるから、文献学的な詳細な訳注は読み手に絶対必要である。こうした条件をバランスよく押さえた、良書、というか、唯一の参考書である。 それにつけても、朱子学に限らず儒学の基本姿勢、例えば本書129頁にあるような、徹底的な虚心熟読の心構えを、およそ現代の学問というかそれ以前に現代人の生き方や在り方に、どのように噛み合わせて行ったらよいのか、これがまた、教育の立場からすれば気が遠くなる話である。教育に関して道徳のモデルに江戸時代を挙げる意見もあると耳にするが、朱子学の学びを導き手にするようなカリキュラム(そもそもカリキュラムになりえるものか・・・)にする覚悟はあるのだろうか、一案でも出してほしいところである。 |
| チャールズ・ユウ 『SF的な宇宙で安全に暮らすっていうこと』(新ハヤカワSFシリーズ) |
| 久しぶりに、SFを読む気がそそられるタイトルに惹かれて、手ごろな厚さの本書を手に取ったが、これがなかなかの難物だった。設定は理系作家(とひとくくりにするのは雑なのだが)らしい手の込みようともっともらしさ、しかし物語の中心はむしろ父子関係にある。タイムトラベルの研究に没頭して、ついに成功したものの、公には認められずに家庭も崩壊とは、ありがちな設定のように思うが、家族の心情は痛々しいまでに緻密に描かれていて、人物描写が物足りないSFはなかなか読めないのだがここまで来ると・・・と思いきや、解説によるとこの本もSF出版ではないとのことで、腑に落ちた。タイムトラベルの原理は人間の生そのものに深く根を張っているところがミソ。BTTF的なものを期待すると全く裏切られるというか、対極にあるとも言えるような作品。 |
| 國分功一郎 『暇と退屈の倫理学』(朝日出版社) |
| 新進気鋭とは月並みだが、若手の研究者が書いた哲学書として、いや「若手の」は余計かもしれない、哲学書として実に読みやすく、かつエキサイティングな内容に、ほとんど一気に読み終えてしまった。ハイデガーの退屈論を軸に、暇と退屈というものが何であるかを、文字通り解き明かしていく。タイトルからスヴェンセンの『退屈の小さな哲学』を思い出すし、本書でもそれは取り上げられているが、本書は暇と退屈を、人間の在り方を捉えるための根本的な鍵概念としているので、厚みというかスケールが違う。退屈は「小さな」哲学では決して扱えないということがよく分かる。さまざまな暇と退屈の哲学はもちろん、さらにヴェブレンや『ファイト・クラブ』、ユクスキュルにコジェーヴまで目配りをして、人間的自由の問いに向かっていく過程で、いくつも目を見開かせられる体験をする。そして、結論で満を持して立ち現われるのがスピノザである。ほとんど、上質な推理小説を読み進むようなスリルを与えてくれて、本書を読むということが暇と退屈の倫理学の体験になって行くということに、結論で気づかされる。副題に「人間らしい生活とは何か?」とあったことを、いまさらながら思い出すのである。あまりにも見事であり、こうなると、ハイデガーとスピノザを読みなおさなくてはならなくなるではないか。 |


