

 最近の更新(13年7月〜14年8月)
最近の更新(13年7月〜14年8月)
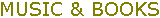
| >HOME >BOOKS |
| BOOKS |


 最近の更新(13年7月〜14年8月)
最近の更新(13年7月〜14年8月)
|
|
ヨナス・ヨナソン 『窓から逃げた100歳老人』(西村書店)
|
| これは実に面白かった。100歳のじいちゃんが誕生日祝いの日に老人ホームから脱走する。そのじいちゃんの珍道中に、世界を股にかけて歴史を動かすことになってしまった人生がフラッシュバックされる構成になっている。一人の人間が意図せずして国際政治を動かしていく話、といえば『フォレスト・ガンプ』を思い出すけれど、本書の洒脱さははるかに上をいく。実際のところ、とんでもない事件は起こっているし、人も死んでいるのだけれど、いかにもノーベルの国らしい主人公の人生は、それをちょっとした面白いエピソードに過ぎないものにしてしまう。ブラックではあるがあまりにもユーモラスな、訳者が言う通りの出鱈目小説の極致である。それにしてもやっぱりバリ島にはまた行きたくなるねえ。 |
| ハーフィズ著 黒柳恒男訳 『ハーフィズ詩集(東洋文庫299)』(平凡社) |
| ペルシア文学の七大詩人とたたえられるうちの一人が、14世紀の詩人、ハーフィズである。もっとも、私はペルシア文学にはまったく無知で、七大詩人といってもオマル・ハイヤームくらいしか知らなかったのだが。それで、なぜこの詩集を楽しむことになったのかというと、イスラームについて調べている時に「そもそもムスリムがお酒を飲まないというのは、オマル・ハイヤームの詩からすると想像が付きにくいんだが、他はどうなの?」という疑問がわいて、誰がよいかと調べたところで、最大の抒情詩人として名高いハーフィズに出会ったわけである。読んでみると、これが酒、酒、酒、・・・酒と恋にあふれた作品ばかり。神秘主義的解釈に立てば、酒は神の愛の、恋人は神の象徴表現なのだということだが、少なくとも当時のペルシアが飲酒に寛容であったことは分かったから、すべてを神秘主義的に解釈するのも、どうも不粋な気はする。ハーフィズ自身、飲酒を厳しく取り締まる支配者に難儀した時代もあったようであるし。解説によれば、イランの家庭でハーフィズの詩集のない家はなく、その詩のいくつかを暗唱できないイラン人はいないとのこと。しかしイスラム原理主義国家となった今では、飲酒は厳しく取り締まられているとのことだから、そのギャップはこのような神秘主義的解釈で埋めているのだろうか。想像するばかりだが、どのページを開いてもあふれかえる酒と恋の讃美に、私自身は鼓舞される気持ちで楽しめる。音読でも聞きたいものである。 |
| マイクル・コーニイ 『パラークシの記憶』(河出文庫) |
| マイクル・コーニイはサンリオ文庫で翻訳された4冊は全部読んだはずだが、実はあまり覚えてはいない。『ブロントメク!』が結構面白くてどこかに何か書いた記憶があったのだが、このサイトではなかったようだ。本書は、同じ河出文庫で再訳された『ハローサマー、グッドバイ』の続編、待望の翻訳で、帯には「恋愛SFの名作の続編」とあるが、異星人のコミュニティに訪れる危機に際しての少年の成長譚といった趣。男女や生業で分かれたコミュニティや、はぐれ者や、地球人(!)や、謎の異種族や、殺人のミステリや、記憶遺伝子といった、SF的設定やガジェットが巧みに配置され、ストーリイ展開もスムースで、なかなか楽しめる作品である。前作とは設定の違いもあるようだが、前作を覚えていなくても全く問題ない。ところで河出文庫には、残るサンリオのイギリスSFとしてはボブ・ショウをぜひ復刊していただきたいものだ。 |
|
ジョンソン祥子 『ぼくのともだち』(新潮社) ジョンソン祥子 『ことばはいらない』(新潮社) |
| 子どもと犬の写真集というのは、禁じ手でしょうね。かわいいに決まってますもの。でも、結婚してアメリカにわたり、言葉も十分に通じないときに、やってきた柴犬マルに慰められ、生まれてきた息子の一茶君との暮らしの様子を写真にとって、ブログに上げていたら、評判になって今こうして2冊の写真集にまでなったというのですから、かわいいかわいいと言って楽しませてもらうばかりです。もうね、これはどうしようもありません。うちにもすでにおっさんになってしまった息子二人、犬は二匹目ですが、もちろんジョンソンさん家の一茶君やマル君のような美男美犬ではありません。でも、同じ表情、同じポーズ、思い出すんですよね。あーこれこれ、こういう姿勢するよね! こういう顔するよね! という、絶妙なかわいさの瞬間を、しかも犬と一緒にカメラに収めているのです。ブログも見始めると止まりません。一茶君大きくなったね! って、知らない家の坊ちゃんになれなれしいですね。でも結局、どの写真を見ても、こちら側の祥子さんの隣にいる気になってしまうのです。それこそなれなれしいんですけどね。ブログはこちらで。 |
| 日本思想学習指導研究会 編 『日本の思想家 珠玉の言葉 百選』 日本教育新聞社 |
| はい、これは宣伝です。私も3つほど書いています。でも原稿料なので、売り上げは収入にはなりません。念のため。そういえばもう一つ、不干斎ハビアンの原稿も送ったのだが載っていないのでボツになったのだと思います。さてこういう仕事が来ると、あまり引き受け手のないパートを頼まれたり、こういう人はどう?と自分で申し出たりするのが悪い癖なのだが、それが楽しくて仕方がないのだから我ながら困ったもの。ここでお手伝いしたのは、林羅山、井原西鶴、雨森芳洲。たしか芳洲は私が提案したもので、羅山と西鶴はなんか余っていたので引き受けた記憶がある(違っていたらごめん)。羅山はポジティヴな評価がなかなか難しい人物だったが、鈴木健一『林羅山』(ミネルヴァ書房)に出会って、少し見直した。が、まああまりお友達になりたくはない人物である。西鶴は素晴らしい。素晴らしすぎて残っていたのかもしれない。取り上げるのは迷うことなく『本朝二十不孝』である。とにかく道徳がらみでご高説を垂れ流す政治家が多いけれども、まあこういう本(西鶴の方ね)を読みなさい、と私は言いたい。六親和せずして孝慈あり、ですよ。まずあなたがたが清廉潔白な政治家ばかりになってから他人のこと言おうね。雨森芳洲は、この人もすごい人で、言うこと聞かない人だ。まあもちろん、他の人が書いたのにも面白いのがあります。なにせ、一人目が宮崎駿だ。不思議な本です。ところが、読んでみようかなと思った人に不親切この上ないことに、アマゾンとか楽天ブックスとかに出てこない、というだけではなくて、版元のホームページにも出てこない。版元に電話したら、在庫あります、というので注文したのだけれど、発送予定日として告げられたのは一週間後の日付・・・。うーん、不思議というか、この日本教育新聞社というのはなかなかに謎の世界である。そんなわけで私にお問い合わせいただいても、安くもならないし早くもなりません。ちゃんとISBNはついてます(ISBN978-4-89055-309-9)ので、書店でふつうに注文はできる・・・はずです、試したことはありませんが。 |
| 保苅瑞穂 『ヴォルテールの世紀』(岩波書店) |
|
映画『パリ20区、僕たちのクラス』で、舞台となる中学校に転任してきた歴史の教師が、国語の教師に、テキストについて相談する場面がある。彼は、フランス革命前の歴史を扱うので、ヴォルテールはどうだろう、『カンディード』は、というのだが、国語教師は難しいね、という。『ザディグ』でも?と歴史教師は食い下がるが、たいへんだと思うよ、と国語教師はアドバイスするのである。ちなみに、国語教師は『アンネの日記』をテキストにしていた。余談だが(いや、本質的なことだが)、新学期が始まってからこんな風に自由に「テキストは何にしよう」と話しあってる公立中学校というのも、わが国のあり様に照らし合わせて、まさにフランス的であるなあとつくづく思う。 さて、読了してからもう一年近くたつので、いくらなんでもそろそろ感想をまとめておきたいのだが、まずはこのヴォルテールという人物の偉大さを再認識させられたということからはじまって、著者のライフワークとも言える本書の、ヴォルテールとその時代を蘇らせる多くの資料そのものの魅力、著者の深い考察と平明な名文に圧倒され、それがなかなかはかどらないのである。ヴォルテールその人と、ヴォルテールと対話し続けた思索の重厚な成果とを前にしては、どんな感想を書いても浅薄であり無力である。 ヴォルテールについての概説的なプロフィールとしては、反権力・反教会でイギリス経験論に影響を受けた啓蒙思想家という、反骨のイメージを持ちがちであるが、実際のところはもっとずっと複雑で繊細である。フランスばかりか他国の王侯貴族や政府の権力抗争の中で、平民出身のヴォルテールが、彼を排斥しようとする人々と、すぐれた才能に注目して彼を保護する人々との間にあって、国王を頂点に貴族や政府高官、さらには多くの夫人たちとの付き合いを巧みにこなしながら、多くの問題作を世に出していく。哲学者という視角からつい考えてしまいがちであるが、彼は何よりもまず芸術家であったし、信仰者であったし、実業家でもあった。逮捕歴がありながらも、やがてアカデミー会員になり王室つき侍従の地位についている彼の人生は、まさに波乱万丈、その伝記としてまずは大いに楽しみながら読むことができてしまう。 本書では、彼を巡る多くの手紙が数多く紹介されている。その手紙の数々によって、彼の人生が浮き彫りになり、綴られていると言える。ヴォルテール本人は勿論のこと、貴族達や婦人たちが、すばらしい手紙をやり取りしている。多くの出来事が手紙で動くこと、素晴らしい文章が書ける多くの人々が歴史を動かしてきたことを、あらためて思い知らされる。メールのやり取りがほとんどの現代の人間関係にあって、これもずいぶんと考えさせられる事実である。 思想家として自らが社会に関わる人は少なくないのだが、村を再生し、多くの国民に熱愛され、国家にここまで影響を与えた人物となると、ごく限られてくるであろう。どうにもまとまりのない感想になってしまったが、とりあえずこれでいったん、読み終えたということの標としておきたい。おそらくは、これからも折にふれては読み返し、新しい発見や解釈に出会いながら、自分の血肉に少しずつ取り込まれていくであろう一冊である。 |
| 安全なエネルギー供給に関する倫理委員会 『ドイツ脱原発倫理委員会報告』(大月書店) |
|
表紙に「原題『ドイツのエネルギー大転換−未来のための共同事業』」とあるけれども、あくまでも主眼は「大転換」にある。3.11から時間がたって、あの頃はもはや当たり前に思われた「脱原発」が、すっかり「再起動」に向かう動きの前に押じ戻されているが、この原題と邦題の違いに、その成り行きが象徴されているかのように思えてしまう。われわれは「脱原発」ではなくて「大転換」を旗印にしなければならなかったのだ、と痛切に思う。「脱原発」後の道筋をわざと描かないことによって、あらゆる「大転換」の可能性をつぶすのも、いつものやり口だろう。 ドイツでは幅広いメンバーによって構成される「倫理委員会」の長い伝統がある。各分野の専門家、各政党の政治家、各教派の聖職者が集められ、公開の討論も含めて、政界・産業界・市民社会の共同事業として「大転換」を進めることを提言するに至っている。そこにはライフスタイルもビジネスモデルも含めた、方向性としての明確さがある。なお、未だに「ドイツは原発やめてもフランスから買うから言えるんだ」などというおそまつな批判が出ることがあるが、もちろん、われわれが自国の政治や行政のやりくちで身にしみているそんな粗雑なビジョンではない。2023年以降は原発が稼働する理由がなくなるロードマップが作られているのであり、それはなぜかわが国では取り組まれようとしない事業である。原子力規制委員会の「活躍」がしばしば取り上げられるけれども、それも「原子力」の枠組みの中ですべてを進めていこうとする巧妙な罠であるというべきである。消費税増税前に住宅の駆け込み需要が言われるが、個人住宅はもちろん地域再開発などにおいて、省エネルギーや新技術の導入に大幅に助成や控除を積み増すとかいった政策がなぜ強く謳われないのかを見ても、政財界のスタンスは見えている。 いまやオリンピック景気目当ての東京招致に成功し、流されかねないわが国である。動いていた原発がコントロールできなくなったのだから、どうして今の状況がコントロールされているなどと言えるのだろうか。そういえば真夏のドバイでサッカーのワールドカップなんかできるわけないと、決まってからのドタバタも進行中であるが、大がかりなプレゼンテーションとネゴシエーション大会であるオリンピック招致というあまりの浮かれ騒ぎに、目をそむけたくなっていたのは、決して少数派ではなかったと思う。スポーツと平和というような謳い文句には抗いがたい魔力があるが、それに惑わされることなく、わが国の身体には大きく開いたままの傷口があって、じくじくと毒のある膿が染み出しているのを、根治の見通しも立たずにあれこれといじくっているという、正しいイメージと感覚をしっかりと持ち続けたいと思う。 |
| 施川ユウキ 『バーナード嬢曰く。』(一迅社) |
| まずはタイトルの不可思議さ、表紙の一コマのネームに魅かれて、「本を読まずに読んだふりをしたい読書家(?)」の主人公と、それをとりまく図書館にやってくる人たちを描く、この奇妙な漫画を楽しんだ。途中かなりSFネタが多くなるので、SF好きとしてはちょっと物足りなくなってしまうのだが、そんな事を言うと82頁の最後の一言「なぜSFファンは色々うるさいのか?」と言われてしまうのである。そういえばサンリオ文庫もずいぶん処分してしまったがもったいなかったかな。一番うけたのは聖書の引用の話。まあどうあれ今までなかったテーマである事は間違いないと思う。 |
| キム・ヘギョン 『涙と花札』(新潮社) |
|
最近読んだ新聞記事で、結婚披露宴で親に感謝の手紙を読んで涙にむせぶというシーンが、外国人から見ると奇異に映るというものがあったが、日本人からすれば(クサいなあと思いながらもまあそこそこ)通常の風景に見えている。イム・グォンテク監督の映画『祝祭』は、都会暮らしの人気作家の母親がなくなり、田舎の伝統的な葬式にやってくる話だが、これを見ていてまさに不思議に思ったのが「花札」なのである。葬儀に集まった人々が飲み食いして騒ぐのは日本の通夜風景と照らし合わせても不思議はそれほどないのだが、そこでなぜ村人たちは「花札」に興じ、それも喧嘩まで始まるほど熱心なのか、ということが分からなかった。「なぜ韓国人は、葬儀で遺族が号泣している横で、日本由来の花札に興じるのか?」この帯の一文が、まさに私が知りたかったことだったので、読んでみたのがこの本。 で、本書を読んで、それはすっきりと分かった。李氏朝鮮時代に日本からすでに伝わって愛好されていた花札を、朝鮮併合を果たした日本政府が同化政策の一環としてさらなる普及を図ったものだったこと、米軍払下げのクッション生地が、模様が派手で花札には向かなかった韓国の座布団にかわって重宝されたことなど、興味深い説明だった。 しかし本書は、全体としてはそういう文化の謎を説きおこすものではなく、日本好きの著者がさまざまな紆余曲折を経て、明治大学で教べんをとるにいたったかの半生記になっている。準備を整えていたのに日本留学が認められなかった悔しさから、延世大学に合格したうえで日本に留学、明治大学で司法試験を目指すが当時の国籍条項で受験できず、卒業して韓国の放送局に職を得るも満足できず、9月入学が可能な早稲田大学の大学院に入り、国際法を研究。博士課程に進学後は家族が暮らすアメリカでも学び、ジョージワシントン大学やハワイ大学でも教鞭をとり・・・という、本人のドラマチックな成長の記録は、わくわくさせられる。 文化人類学的な興味で読み始めて、はじめはやや肩透かしを食らったような気になったが、すぐに引き込まれて読んでしまった。多文化社会の経験者の語り口にありがちな、突き放し気味で客観的であろうとするあまりに、どことなく高所から見下ろすようなところがないばかりか、エピソードが一つ一つすごいので自慢話になってしまうところを、そう感じさせることのない日本語で書き下ろしていて、親しみさえ覚える。韓国の上流家庭の生き方や考え方、北朝鮮の存在、母子関係と家族のきずななどが、率直な書きぶりでよく分かる。 |
| コニー・ウィリス 『オール・クリア1・2』(新ハヤカワSFシリーズ) |
| 長かった! 第二次世界大戦中のイギリスを舞台とするオックスフォード大学史学部のタイムトラベルシリーズの大長編、前篇『ブラックアウト』は分厚くて読みにくかったが、後編『オール・クリア』は二分冊になったはよいが、間が2か月空いたから、結局全体を通して読むことができず、とにかく『1』までは次から次へと生じるトラブルと謎がたたみかけてくるので、頭の中はパンクしそうであった。『2』を読み始めた頃には細かい部分をいろいろと忘れてしまっているし・・・。しかし、もう一度読み返すよりは読み進めていった方が、と腹をくくってみれば、これまで宙ぶらりんになっていたあれやこれやが、一つ一つ明らかになっていくときのカタルシスたるや、さすがにウィリスとしか言いようがない。あとがきを読むと、作者自身が8年がかりで書きあげ、あまりの長大さに改稿を繰り返す作業がたいへんだったようだから、これだけ登場人物も時代も入り組んだ小説を楽しませてもらえることに、本当に感謝である。あらかたの謎が解けて、あと最後の一章を残すのみ、というところまで来て、私はそれを翌日にとっておくことにした。たぶん、最後の最後に絶対、とんでもないオチが来るはずだ、という大いなる期待と共に。もちろんそれは裏切られなかった! 途中でくじけないでよかった! ところで、疎開児童の世話をする場面については、89年にシンシア・フェリスとの共作で書かれた『アリアドニの遁走曲(フーガ)』(ハヤカワ文庫SF)の冒頭部分で、近未来のカナダで疎開している主人公アリアドニが、全く同じように子どもたちの世話でドタバタしている。ということは、ウィリスは第二次世界大戦下のイギリスの疎開児童のエピソードをこの頃から温めていたというか、いよいよこっちのシリーズで本格的に使ったということか。とにかく「当時のイギリスであったこと」の詳細な調査と、それをさらに「当時のイギリスらしく」肉付けしていったであろう緻密な作業は、このSFを上質の歴史小説としても楽しめるものにしている。本作後も続々と新作を執筆中とのこと。楽しみはまだまだ続く。 |
| マイケル・サンデル『それをお金で買いますか 市場主義の限界』(早川書房) |
| 技術者倫理の授業でよく引き合いに出す例の一つに、フォード社のピントのケースがある。フォード社は追突されるとガソリンタンクが簡単に損傷し炎上することが分かっていながら、わずか1台11ドルでできる設計変更をしないまま、ピントを市場に出した。その時の試算では、改造に要する費用は1億3千万ドルを超えるが、死傷者と車両に支払う補償金は5000万ドル程度だったので、改造しない方が合理的であるという判断だった。この考え方はどこかヘン? ヘンだとすれば、どこが? というのが授業の視点である。もっともオーソドックスな問題点は、「人命=補償金」ではない、ということである。金額に置き換えた途端に、それが持っていた本来の価値が腐ってしまう。「公正」の視点に加えて、「腐敗」の視点が必要であること、これらがいわゆる市場原理に十分に対抗できることが、本書では多くの例を取り上げながら、明解に説かれている。ところで授業で実例を試行錯誤していたら「子どものころ100円握りしめて遊戯王カードを買って、ピッと開けた瞬間にキラが出た!という時と、大人買いや専門店でプレミア払って買って手に入れるのと、どっちが喜びが大きいか?」というのが一番分かりやすかったようなのがちょっと微妙。 |
| 成毛眞 『日本人の9割に英語はいらない』(祥伝社黄金文庫) |
| マイクロソフト日本法人の取締役だった著者の、ごくまっとうな内容の本。あまり大きな声では言えないが、私の勤め先の学校でも、上の意向でやたらと国際化国際化といわれるのだが、そのために割かれる国際化以外にかけられるはずの労力がそろそろ冗談ではすまないレベルに達しようとしているんじゃないかという今日この頃。だいたいこういうことは、最初は「やらないよりは、やった方がいいんじゃない?」という反論しづらいところから始まって、「おいおい、こんなにやらなきゃならないのかい?」という時には、もう後戻りができなくなっているのである。つまり政治と同じですね。実際、採用側のニーズとしても、「語学力」はかなり低くて(経団連の採用アンケート見れば19位3.6%で、「倫理観」4.1%「出身校」3.9%より下だ!)、ふるい落としの口実こそが最も多いTOEICの使い道だったりする。好きだったり、必要だったりすれば、中学英語の基礎くらい身につけておけば何とかなるというか、何とかできるぐらいの知力や創造性のある人でないと、そもそもそういうエリート層に居続けることができないはずだ。英会話にせよ、高校「情報」科目にせよ、ほとんどが「スキル」に関わる内容を、学校の細切れの時間割に組み込んで身につけさせるという考えがそもそもおかしい(時間の無駄)のだが、全くそんな事には気づかずに、何かというと「学校で習わせろ」と言いだす人たちの存在が問題である。今英会話に長けていたりITで活躍していたりする人々は、学校で英会話や「情報」なんか学んでいなかったという、ごく当たり前のことにちゃんと目を向けるべきである。本書は軽い読み物だから、どこまで検証可能な内容なのかを突き詰めればいくらでも批判はできるだろうが、教育の仕事をしていれば経験的によく分かる話で、そうなんだよなあとため息交じりに読む程度であれば十分であろう。しかしさすがなのは、この本の仕掛けである。最後の章にはちゃんと英語の学び方について書いてある。推薦されている本の一つをアマゾンで検索してみたら、取り上げられている本がぞろぞろと「この商品を買った人はこんな商品も買っています」に並んで出てくる。もちろん、本書も含めて。なかなかの影響力である。ところで、日本の翻訳の文化が素晴らしいということは再認識させられたし、翻訳が不要になるほど日本の英語化が進むわけがないと思いつつも、一方で翻訳書を愛好する文化が廃れていきはしないかという不安は感じている。それは日本(語)の文化が廃れるということでもある。 |
| 日本公民教育学会編 『テキストブック公民教育』(第一学習社) |
| 宣伝です。私もちょこっと書いている、新しい学習指導要領対応の公民教育のガイドブックです。単に中学校社会科公民分野や高等学校公民科を解説しているだけではなく、わが国における公民教育の歴史を含む内容ながら、コンパクトにまとまっていて便利。まあ、そうは言っても、一般向けの本ではありません。教職課程で学ぶ学生さん用です。念のため。 |


