

 最近の更新(13年1月〜6月)
最近の更新(13年1月〜6月)
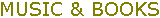
| >HOME >BOOKS |
| BOOKS |


 最近の更新(13年1月〜6月)
最近の更新(13年1月〜6月)
|
| 斉藤道雄 『悩む力 べてるの家の人びと』(みすず書房) |
| べてるの家については、報道等で取り上げられたことも多く、本やビデオシリーズなども知られている。この本は、ジャーナリストとしての著者の取材に基づいて書かれたものである。読む前にすでにいくらかの予備知識はあったものの、ここに登場する人々の声にはあらためていろいろな驚きを感じた。ケースワーカーの向谷地さんはべてるの家の特徴をひとことで言うと「管理の行き届かないところ」という。草創期を支えた浦河教会の宮島牧師夫婦、病気を治さない川村医師、様々な住人、そして街の人々。「普通に」生活している人々は、べてるの家の人々が「病人」であり、「精神異常者」であると思っている。それはその通りなのだが、しかし自分は「正常」で「健康」であるという思い込みは、べてるの家に立ち寄ることでこわされる。自分が抱えていながら抑え込んでいたり、気づいていながら蓋をしてしまっている、苦悩や心のひずみを思い知らされてしまう。そうして、いつの間にか交流がすすんでいくのである。べてるの家に暮らす人々は、内職がふとしたことからなくなったのをきっかけに、色々な事業を始めたので、今では会社員である。「安心して絶望できる人生」「安心してサボれる職場づくり」「手を動かすより口を動かせ」「勝手に治すな自分の病気」などなど、べてるの家が運営されていく中で発見され確認されてきた標語?の数々には、真の意味でのノーマライゼーションの神髄が絶妙に表現されている。しかし一般には、精神障害者は中途半端に「社会復帰」させられ、窮屈に「適応」させられて、再発して逆戻り、という流れが依然として多いのが実情だろう。とりわけ、今の世の中のおかしさはべてるに教えられるまでもないほどのレベルに達している。 |
| 西内啓 『統計学は最強の学問である』(ダイヤモンド社) |
| ベストセラーになっているようだが、タイトルがトンデモ本っぽくて、調べてみたら『サラリーマンの悩みのほとんどにはすでに学問的な「答え」が出ている』やら、『東大の先生がハーバードで実践した人を動かす技術』やら、「もしドラ」の線で『コトラーが教えてくれたこと 女子大生バンドが実践したマーケティング』なんてものまである。ここまで来るとこの企画やタイトルのセンスにいくらなんでもやり過ぎ感があるので、いつもの自分なら敬遠するところだが、中身についてはあんがい統計関係のヒトからの評判がよいので、思い切って買って読んでみた。まあやはりアマゾンのレビューで低得点のものを見ると、まずはこのタイトルで怒らせたな、という印象を受ける。逆に言えば、こんなタイトルでなければ、中身はなかなか面白かったので、怒らせたりがっかりさせはしなかっただろう。売れもしなかっただろうけれど。私なりに本書を一言で要約すれば「使えるところではもっとうまく統計学を使った方がいいんじゃない?」という本だと思う。ほとんどの統計学の入門書は、執筆者が自分の分野の説明をするので、まとまりはよいのだが、使える視点が限られている。また、ビジネス書としての統計分野の本は読んだことがないので分からないが、多分、実用に絞り込んで書かれているのだろう。本書は系統立てて統計手法を網羅するのではなく、統計を活用する分野を俯瞰する立場で書かれているので、手法を相対化してとらえられるところが役に立つのである。本書を読んで統計学が初歩から分かるわけではないが、一通り知っているとか、特定の分野で使っているという人には、(役に立つというよりは)面白い本だと思う。語り口や言葉遣いが偉そうだとか不快だというレビューも見かけたが、私は全く感じなかった。背の低い野村君の恋愛のエピソードが、実はゴルトンの「平凡への回帰」につながったとか(著者はこのことに気付いた時にどう思ったのか気になる)、私が一番笑ったのは、栄養食品などについて「髪の毛を食べたからといってハゲが治らないのと同様」というたとえである(こういうのが嫌な人は嫌なのかも)。結論的には、統計的に参考になるデータがあるにもかかわらず使わないことと、統計的に参考になるデータを出そうとしないこと(もう繰り返したくないが、教育政策はまさにそれ)を批判している。この点で大いに共感するので、私はこの本を支持する。 |
| 井部俊子監修、服部健司・伊東隆雄編著 『医療倫理学のABC 第2版』(メヂカルフレンド社) |
| 最初に一言で言うと、この本はとても面白い。私は倫理教育の立場から読むので、技術倫理のテキストを物色していると、違和感のあるものが少なくない。学生に勧めるには難しすぎるキャロライン・ウィットベック『技術倫理 1』(みすず書房)を別格とすれば、そうは謳っていないものの畑村洋太郎『危険学のすすめ』(講談社)を学生に勧めるほどで、いわゆる「技術倫理」を謳う本の多くは、知られたケースを上滑りな用語でさらう羅列的なものが多い。業界で作成された「倫理綱領」、PL法などのコンプライアンス、アカウンタビリティ、云々。規制に縛られた(もしくは、守られた)産業社会のおしきせの(あるいは、都合のよい)ルールに、いかに良心の呵責なく従うか、とまでは言わないが、どうしても明解な行動原理を示すことで安心してエンジニアとして働くことを目指そうとしているかのようである。その点では、取り扱う対象が直接生身の人間である医学では、倫理規定がこうだから、というだけでは通せない厳しさがあるので、応用倫理、職業倫理の観点からよく練られた著作が多い。本書はハイデガーを引き合いに出して、哲学は事柄を難しくするためにある、と前書きで言いきる。語りかけ口調の本文は読みやすく、取り上げる例も面白いが、例えば実際のケースを取り上げ、経過と結果を説き、法的な判断を明示したうえで、さてこれでよいのか?とたたみかけるのである。さらに念のいったことに、側注欄に多くの「コメンテーター」がその都度見解を加える、つまり茶々もしくはツッコミが入るのである。平板な記述で問題点を指摘する、哲学書にありがちな気取った構成ではなくて、このたたみかけとツッコミという絶妙な仕掛けによって、読み手を果てしなく混乱させかねない、つまり問題をより難しくして、考えざるを得ない状況に追い込んでいくという意味では、「医療倫理」に限定されないすばらしい「倫理」の教科書である。 |
| ハワード・ブロディ 『医の倫理 原書第二版』(東京大学出版会) |
| これはなかなかよい本なのだが、残念ながら品切れのようだ。もっとも、原書第二版が出たのが1981年、翻訳が1985年だから、医学書としてとらえれば30年前の本の内容が相当古くなっているのは確かで、ブロディの医療倫理や生命倫理、医学史の著作は原書ではその後も出ているので翻訳してほしいところではある。副題に「医師・看護婦・患者のためのケーススタディ」とあるように、「患者」が入っているところもユニークだが、短文に番号が振ってあり、豊富なケーススタディが例題としてして組み込まれ、自習用の学習プログラム構成になっているところも便利で分かりやすい。現代の医療倫理には不十分とはいえ、大部の本で古典的なケースは網羅されているので、生命倫理のケース研究の入門的な参考書としては今でもたいへん重宝する。私も古本で手に入れたが(通販で買ってみたら公共図書館の除籍本だった)、アマゾンで見ると400円からあるようで、もとが3914円だから買って損はない。これと『医療倫理学のABC第二版』をセットにして読むとよいと思う。 |
| 大泉洋 『大泉エッセイ』(メディアファクトリー) |
| たまたまテレビで『探偵はバーにいる』をやっていたので何となく見てしまったが、あまり面白くなかった。それは大泉洋のせいではないのだが、あまり面白くなかったのが何となく大泉洋に悪いような気がして(というのも変なのだがそう思わせる何かが大泉洋にはある)このエッセイを買ってしまったのだ。芝居はDVDで2本しか見たことがないし、ドラマは見たことがなく、やはりどうしても「水曜どうでしょう」の大泉洋の印象が強い。基本的には雑誌の連載コラムをまとめたもので、時代的にも軽薄なノリをそのまま文章にするのが一般的だったから、そこからはみ出すものもあまりなく、今まとめて読んで面白かったかと問われれば、ちょっと黙りこんでしまう。しかし、書かれている内容で一番楽しめたのは、大泉洋の家族がらみの話である。自分も道産子で、しかも札幌生まれで母の実家は後に江別の大麻(おおあさ、です。誤解なきよう)に移り今もあるという親近感もあるが、何かこう、札幌のファミリー感が漂うのである。鷹揚でどこかすっとぼけたところがある、というと過度の一般化は禁物といわれそうだが。それでいてさりげなく認知症のばあちゃんを見舞う話は、泣かせどころがはまっているTEAM NACSの脚本を思わせたりもするが。後は書き下ろし部分だろう。当事者だけあって、水どうがなぜ面白いのか、4人の役割から説明する内容は頷ける。しかし室内のカメラアングルが小津安二郎だったとは・・・。 |
| 児玉聡著、なつたか画 『マンガで学ぶ生命倫理』(化学同人) |
| 倫理学者が生命倫理を学ぶ高校生を対象に作った入門書。女子高校生を主人公にした短編のマンガと、解説文が交互に構成されている。これまで、あまりマンガで解説というような本を読んでいないのだが、これはとてもよくできていると思った。まず、マンガが、ストーリーも画も良くできている。それから、解説文がマンガに頼ることなく、平易で読みやすい文章になっている。マンガがあるから文章は難しくても良いだろうとか、文章で解説しているからマンガは添えものでよいだろうとか、そういう中途半端さがなくて、始めから終りまで、よくわかるし飽きないのである。もちろん、内容はまんべんなく現在の知識や論点を押さえているので、生命倫理の入門書としては、第一選択と言えるのではないか。惜しむらくは表紙装丁がややありふれていることで、これはもう少し凝れなかったかなと残念だ。それにしてもこのマンガのストーリー、もしかするととは思ったけど、ほんとうにこうなるとは・・・。 |
| 渡辺裕 『聴衆の誕生』(中公文庫) |
|
ヤナーチェクのオペラのCDを探して検索していたら、『小説に出てくるクラシック』というタイトルのCDがあるのに気づいた。あの(自分は読んでいないが)『1Q84』に、ヤナーチェクのシンフォニエッタが出てきたらしい。このCDを買うと『1Q84』に出てくる曲がほぼすべて聞けるそうだ。これを便乗商法と切って捨てるのは簡単だが、『のだめカンタービレ』がちょっとしたクラシック人気を呼んだことも含めて、小説なりマンガなりドラマなりで使われた音楽が、新しいクラシックファンを生み出したり、あるいは少なくとも知っている曲が増えたと感じる人が喜ぶだけでも、よいことではないかと思う。私もいわゆる「クラシックファン」とはとても言えず、通勤電車の中、iPhoneでヤナーチェクを聴いて和む幸せを感じている程度であるが、本書を読めば、いわゆる「クラシックファン」のイメージは、ごく限定されたものであることが分かって、ちょっとホッとする。 音楽社会学の興味深い著作の数々で知られる著者であるが、本書はその出発点とも言える本である。クラシック音楽の世界の裏話ならば、歴史が長い分いろいろとあって、楽しみにもなるし、当時の社会状況と出来事との関わりも面白いが、何よりも、クラシック音楽の楽しみ方や研究や評価を、現代の社会とのかかわりの中で分析していく方法が興味深い。本書は最初に書かれたのが89年、補章が追加され増補版となったのが93年、文庫版は12年に出されている。音楽の聴き方、消費のされ方を扱いながら、世の中も音楽産業も大きく変容してきたほぼ四半世紀後、本編をそのままに文庫化できるということが、研究考察の視点、方法の確かさを物語っていると思う。商業化、大衆化を経て軽やかに消費されるクラシック音楽の現状は、ジャンルを超えて音楽に共通に浸透している事態である。音楽の聞かれ方、楽しみ方の変化が、音楽著作権ビジネスなどに打撃を与えているにしても、それを危機ととらえて守旧的になるのでは、むしろ道は開けないだろう。最初から消費されるものとして流通する今日の音楽よりも、長い歴史をさまざまな形をとりつつ生き残ってきたクラシック音楽にこそ、新たな転進のヒントが詰まっているのではないか。 |
| マキヒロチ 『いつかティファニーで朝食を1・2』(新潮社) |
|
今のところ、何があっても朝はやってくる。明けない夜はない、という言いまわしは、ラジオ体操並みの希望の朝を思わせるが、いつも寝覚めが良いわけではないばかりか、また朝になってしまったとつらい思いをしている人もまた多いはずである。誰にも朝はやってきてしまう、せめて朝食はおいしく食べようよ、という願いは、ささやかだが切なるものだ。 コミック@バンチに連載中の漫画。要するにOLの朝食グルメ漫画か、と思って読み始めたら、これが面白い。やはりこういう表現も性的ステレオタイプであるということは承知で言うが、女性作家らしいリアルで細やかなストーリーが泣かせる。群馬の高校時代の同級生女子4人が、東京で別々の生き方をしていて、主人公のアパレルOLを軸に、それぞれの生活のエピソードを絡めながら、いろいろな朝食が紹介される。2巻の終り二つのエピソードが、愛犬の最期を看取ったこと、子育てに悩んだことなど共感させられて、特に泣かせる。 |
| 鈴木健一 『林羅山』ミネルヴァ書房 |
|
教科書では林羅山の記述はシンプルであり、どちらかと言えば評価はネガティヴである。いわく、朱子学を学び徳川に重用され、上下定分の理によって身分制度を支持し、幕藩体制を固めた、と。しかしそれはどうやら、小林秀雄や司馬遼太郎の記述に由来するようである。その学識から家康に取り立てられたものの、儒者の地位が認められないために仏僧の地位を与えられ剃髪もしなければならなかった。博学さはとびぬけていたが、その知識と文書作成力を便利に使われていた当初は、幕藩体制を支える思想家などと言うモノでは到底なかった、とするのが、むしろ今日では定説のようである。家光の代にようやく御伽衆の一人としてとりたてられ、やがて僧侶の最高位を与えられる。この僧侶の地位については、自分でも言い訳をし、中江藤樹には批判されている。林家が僧形を廃し大学頭を名乗ることができたのは、ようやく孫の代、林鳳岡になってからである。 読み終えて考えてみても、たしかに林羅山という人物のイメージが格別に変わったというわけではない。ものすごく頭がよいが、あまり面白味はない。しかし家族を大事にする素朴さをはじめ、その生き方はたいへん俗っぽい側面も持つので、不思議な親しみがにじんでくる。著者が整理するように、「出世するために、自分の学問を利用する」、「書物を読んだり、文章を書く生活を続けるために、社会的な地位を確保しておきたい」というのは、まあ考えてみれば今の大学教師がやっていることと同じようなものである。「書を読みて未だ倦まず」という、本書の副題にもなっている、あまりにも平凡な一言が、林羅山の人柄をそのまま表している。 |
| ロバート・チャールズ・ウィルソン 『ペルセウス座流星群』(創元SF文庫) |
| 『時間封鎖』三部作や『クロノリス』といった壮大なスケールの長編SFで驚かされてきた作者の、ハードSFの発想に立つホラー・ファンタジー風味の短編集。ファインダーズという古書店がそれぞれ登場するが、話がつながっているわけではなく、物語における軽重もさまざまである。得体のしれない大きな謎に包まれていくような運びは、長編にも共通している。どの作品も決して後味はよくないのだが、それがむしろもう一度読み直したくなる複雑な魅力になっている。 |
| コニー・ウィリス 『ブラックアウト』(新ハヤカワSFシリーズ) |
| 絶対に間違いのない面白さ、コニー・ウィリスの新作は『ドゥームズデイ・ブック』『犬は勘定に入れません』に続く、近未来のオックスフォード大学史学部を舞台にした第二次世界大戦タイムトラベルもの。この分厚さでまだ物語は前半、八ヶ月後に後半の『オール・クリア』が刊行予定だが、これは本国での原書の発行間隔に合わせたとのこと。待ち遠しい事この上ない。タイムトラベルのアイデアは、シリーズものだから共通だが、いわゆるタイムパラドックスを巡って学会で異論が出され、そのことがどうやらここで生じているトラブルに関係があるらしい。今回も第二次世界大戦下のイギリスを舞台に、帰れなくなった3人の学生たちの奮闘が描かれていく。それにしてもこの時代の歴史考証は念が入っていて、疎開児童やロンドン市中やダンケルクの様子が、その描写力と相まってリアルで目に浮かぶ。戦闘や空襲も手に汗握る迫力である。また旧作も読み返したくなってしまう。『ドゥームズデイ・ブック』同様、ヒューゴー、ネビュラ、ローカス賞のトリプルクラウンは当然と納得の作。それにしてもこの厚さをポケミスサイズの新ハヤカワSFシリーズで出すのはどうかと思うが。 |
| 南野忠晴 『正しいパンツのたたみ方』(岩波ジュニア新書) |
| 著者はもともと高校の英語教員だったものが、家庭科教員に教科替えした人。男性の家庭科教員は、想像される通りたいへん少ない。家庭科というと、炊事裁縫を習う教科というイメージがいまだに強いのかもしれないが(「食物」と「被服」)、私は著者のいうように家庭科は生活力を身につける教科だと考えている。そういう意味で、「家庭」科という教科名は、時代とともにまさに的確な名前になったというべきだ。正しいパンツのたたみ方はあるのかもしれないが、そういう「プロフェッショナル」な技術ではなく、「パーソナル」な技術を磨くことの大きな要素はコミュニケーションの技術であり、その技術を支えるのは共に暮らす家族を思いやる心であり、広い意味で「家庭」を大切にすることであることが分かる。単に必要最低限の炊事裁縫を学ばせるというだけなら、男女共修世代ではない私自身が一通り身につけているわけだから、そんなにどうしてもやらなければならないということもないと思う(「情報」科と同じですね。情報化社会を進展させた世代は、高校までにコンピュータなんか学んでないのだから)。ただ、私が公民科社会科系の授業で家族問題などを積極的に内容に組み込もうとしている理由の一つが、このことなのだ。 |
| 所澤秀樹 『鉄道会社はややこしい』(光文社新書) |
| 日頃あまり意識することも少なくなってきた「直通運転」。境目の駅で乗務員が交替する姿も良く見るが、そのまま運転していることもあるようだし、ホームの掃除とかはどっちがやっているのかな、というような単純素朴な興味をもったことはあるが、あまり深く考えたことはなかった。そこを深く追求したのがこの本である。青い森鉄道の東青森駅にある「JR貨物東青森駅(八戸臨海)」とマジック書きしてあるゴミ箱の写真から、複雑巧妙な直通運転にまつわるあれこれを導き出していく。考えてみればホームの掃除どころではない。駅舎や車両や線路の所有やメンテナンス、貸し借りはどうしているのか、うまくいっていなければそれこそ乗客の安全にだって関わってくるわけだ。それにしても、この微に入り細をうがった情報量はどうだ。正直なところ、細かいところはかなり飛ばして読んだことは告白しておく。それでも面白かった。 |
| 安田浩一 『ネットと愛国』(講談社) |
| これを読むと、かなりげんなりさせられる。いわゆる在特会についてのルポであり、そのあり様ややり方についての批判も全くその通りとしか言いようがないのだが、じっさいに彼らの「抗議」にさらされた場合はどうにもならないのか、という無力感もある。いやたまたまその場に居合わせただけでも、悪口雑言を吐き散らす示威行為に、ほとんど内容のいかんを問わず不愉快な思いでいっぱいになるに違いない。彼らが在日「特権」と呼ぶもののなかには、ケースによっては確かに不透明で不公正なものがあるのも実際のところなのだろうが、さまざまな差別や貧困対策の現実には多くの問題が生じるものであり、ここだけに見られる現象ではないだろう。弱者が弱者に矛先を突きつけ「特権」とやらをむしり取ろうとすることで「勝ちに酔う」状況には、とうてい明日はないと思うのだけれど。新自由主義者からすれば大いに好ましい行動であろうが。 |


