

 最近の更新(12年2月〜12月)
最近の更新(12年2月〜12月)
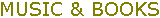
| >HOME >BOOKS |
| BOOKS |


 最近の更新(12年2月〜12月)
最近の更新(12年2月〜12月)
|
| J.A.ナグリエリ、E.B.ピカリング 『DN−CASによる子どもの学習支援』(日本文化科学社) |
| 勤め先の学校で、もう二年越しで要求が通らずにカリカリしている問題があるのを打ち明けよう。私は学生相談室長をしている。私自身はカウンセリング心理学で修士を終えているが、特に臨床の資格は取っていないので、日常の教育相談は担当しているものの、専門的なカウンセリングは非常勤の臨床心理士に担当いただいている。室長の仕事は、相談室の運営、教職員とのリエゾン、そして予算獲得、である。理科系の学校ゆえ、発達障害などへの対応は特に重要である。だから、カウンセラーの先生方もちゃんとトレーニングを受けている方々だから、アセスメントを取りたいのである。つまり早い話が、WAISを相談室におけば、いちいち病院の予約を取ってお金を払ってその結果をもってきて、などという面倒がいらない。そもそも「病院に行って検査を受けてきてもらう」ということ自体が、本人や保護者には経済的にも時間的にも心理的にも、大きな負担である。ところがこの、WAISの購入予算(10万円程度である)が、毎回、上でつぶされるのである。WAISはいわゆる「知能検査」として知られているので、どうやら未だに上部には検査への偏見があるらしい。よく言われる「言語性知能と動作性知能の差が大きいから自閉症スペクトラムだね」、というような使い方がしたいのことではなく、下位尺度を見てどのような躓きが生じているか、どのような支援が可能かを導き出していくための道具なのであるが、そこを理解させるのが大変なのである。今年も予算請求の時期が近づいてきたので、またやるかなと思っていたが、最近このDN−CASについての講義を受けて、WAIS以上に使えるという手ごたえがあったので、こっちを請求してみようかという気になっている。PASS(プランニング、注意、同時処理、継時処理という認知処理過程)理論に基づく学習指導へのアドバイスが蓄積されてきて、結果の解釈から何をするかに重点が置かれている。実際にはWISC/WAISの尺度を用いても同様のことはできるのだが、学校に導入するのはこちらの方が理解が得やすいかもしれない。本書はPASS理論の簡潔な紹介、事例による解説に続いて、半分以上の頁を49の具体的な指導案に費やしている。DN−CAS導入の説得材料に使って、ぜひ導入したいと画策中である。 |
| イアン・マクドナルド 『サイバラバード・デイズ』(ハヤカワSFシリーズ) |
| 近未来インドを舞台とした、連作中短編集。第一線を退いてテレビ番組制作の世界に入っていた作者が、ふたたびSF小説に帰ってきて、さらに高密度の描写を駆使して描き出す世界観は精巧に編み上がっている。国家が分裂し、水利争いが激しい中、テクノロジーとヒンドゥ文化が混ざり合って、革新と伝統、富と貧困、先端技術と呪術的思考など、たとえば日本であれば統制されてしまうであろう両極端が、何の疑問もなく混淆する不思議。ここに取り上げられている作品は、子どもや若者が主人公で、一つ一つに性的社会的な成長譚の要素がある。その息苦しい濃厚さが魅力である。 |
| なかむらるみ 『おじさん図鑑』(小学館) |
| おじさん予想診断によると、私は「哀愁漂うまじめなおじさん」である。「特に何も言われないタイプ」って、微妙に悲しい。とはいえ、おじさんのイラストで埋め尽くされた本書は、無視されるか嫌がられるモノとしてのおじさんひとりひとりに、興味と愛を注いでくれた、おじさんにとってはほのぼのとうれしい一冊である。イラストの楽しさに加えて、いろいろな取材やインタビューが面白く、飽きさせない構成。おじさんをはみ出して「おじさんにモテる女性たち」とか「おじさんぽい子供」とかも。イラスト的には私は「ぽっこりおなかのおじさん」ですかな。あとたまに「秋葉原のおじさん」になる。あこがれは「アート系のおじさん」だったんだけどな。せめて「何となく嫌なおじさん」ではないことを祈る。 |
| 直江清隆、越智貢編 『高校倫理からの哲学1 生きるとは』(岩波書店) |
| 哲学の第一線の研究者たちが集まって、高校生に、高校の『倫理』を入り口に、哲学への導きとなるものを与えたいという趣旨で作られた、意欲的なシリーズである。この第一巻「生きるとは」に続いて、「知るとは」「正義とは」「自由とは」で本編4巻、別巻として「災害に向きあう」の、合計5巻が出される。対話を用いたり、高度な内容を扱うコラム、高校倫理との対応表など、分かりやすくしたいという工夫や努力は、大学の研究者たちがこれまでなかなか果たせてこなかったものである。取り上げられている具体的な事例も、なるほどと思わせるものばかりである。ただ、途中から頼まれてアドバイザー的な形で編集会議に何度か出させていただいた立場からすると、「やはりちょっと難しいよね・・・」という感想はどうしても出てくる。それぞれの専門家であるがゆえの「正確さ」と、学者らしいちょっとした「ヒネリ」のようなものが、どうしてもひっかかるのである。「ヒネリ」という表現がどうか自信はないが、そもそもの出発点が「倫理、哲学って、あんがいいいもんなんだよ!」というところにあるから、折に触れて「ほら、気がついてみたらあんがいよかったでしょ?」という展開に持ち込むやりかたのことである。そこにある種の驚きを覚え、魅かれるかどうかというのは、これは単に学力の問題ではないと思う。私も倫理学を学び、高校倫理の教師をしてきたので、悪い感じはしないのだが、一般的な高校生たちのコミュニケーションのスタイルからすると、まだまだ説教臭く感じたり、もったいぶっているとかなんかよく分かんないけどだまされているみたいな?というような印象を与えてしまわないか、気になるのである。しかしとにかく、内容の充実度は申し分なく、高校倫理の先生方には、まず手に取ってもらいたい、ネタ満載の贅沢なシリーズではある。 |
| 井原西鶴 『本朝二十不孝』(小学館「現代語訳西鶴全集8」) |
| 先日、或る飲み会で、教育勅語や修身は素晴らしいと言いだす人と隣り合わせになって辟易した。所詮いわゆる「酒場談義」だから適当に相槌を打っていればいいようなものだが、私の職業もその人は知っているし、周りも面倒くさくなると私に振るしで、楽しい集まりのはずがとんだ興ざめだった。まあ自分としてはウヨクでもサヨクでもないつもりだが、経験上、これらを持ち上げる人というのはあまりにも無神経な人という印象が強い。このときだって、楽しい酒の席でこういう話を持ち出すということ自体ですでに・・・と思うのだが。この話は以前にもどこかで書いているので繰り返さないが、つまりそれらの「どこがどういうふうに」よいのか、ということが本来問題なのである。おおざっぱにいえば、一定の徳目や例話は、まあいいんじゃないの、というレベルなので(もちろん、少なからずこれはどうよ?というものもあるが)、丸ごとこれらを否定しようとするとサヨクだとか人間としてどうかというような非難を受けるのだが、内容的にはそんなに質の高いものとは思えないのと、拠って立つ臣民関係を基礎づけるにはあまりに雑な展開が目立つので、これを現代の教育に生かせと言われてもなあ、という程度の事に過ぎないのである。これをこのまま生かそうという原理主義であれば、天皇主権の革命を起こさなければ成り立たないし、(雑な言い方だがあえて)その精神を生かせということであれば、現在の学習指導要領で足りないところをどう変えるかという議論をすればよいのであり、別に勅語や修身を引き合いに出す必要はないのである。修身に関して言えば、今の道徳と同じで、現場の教師次第で、面白くてためになる授業もあったかもしれない。ただおそれおおくもかしこきところの権威に頼ってありがたやありがたやという授業でお茶を濁していたとすれば、「心のノート」書かせておけばいいやとホッとしている今の状況との差はそんなにないような気もする。繰り返さないとか言っておいてグダグダと書いてしまったが、まあ私は老子の「大道廃れて仁義あり」の一節に強烈に共感する者なので、この手の酒場談義はいつまでたっても平行線をたどるばかりである。さてさて前置き?はこれくらいにして。ちょっとした関心から「孝」について調べているのだが、『二十四孝』は修身好きの方には喜ばれそうな親孝行例話集である。日本でもこれに倣って『本朝孝子伝』がベストセラーになっている事実も、喜んでもらえるだろう。しかし、よほど無神経な人でない限り、「これはちょっとどうよ?」という話も少なくない。落語の『二十四孝』、三島由紀夫の『不道徳教育講座』序文や、福沢諭吉『学問のすすめ』八編などで、格好のネタになっているわけだが、何といっても西鶴の『本朝二十不孝』は念が入っている。いわば不孝を反面教師として孝行を勧めるように見せかけながら(ほんの短い序文ですら、そのひねりが効いている)、これ見よがしの孝行話を完膚なきまでに叩き潰す力がある。つまり、不孝話のほうがはるかに壮絶なリアリティをもっているのである。まさに「六親和せずして孝慈あり」、ではないか。まして少子高齢化社会では、修身の孝行は明らかになじまない。都合のよい美談を引き合いに出すのではなくて、もっと根本から考えたほうがよい。 |
| ロバート・チャールズ・ウィルスン『連関宇宙』(創元SF文庫) |
| 三部作の最後ということで、これも期待にたがわぬスケールの大きな物語だった。舞台としては近未来と遠未来が交錯し、そこから仮定体の正体というか真相が明かされる。今回はイメージを喚起させるガジェットも控えめな印象で、ラストに向けて収束するので破天荒な突き放し感がない分、興奮度は抑え目か。やはり前二作を復習してから読むべきかと思う。 |
| ハーモニー 『幻聴妄想かるた』(医学書院) |
| 世田谷区にある精神障害を持つ人のための生活支援施設ハーモニーで作られた、何とも不思議なカルタ。もともと手作りで作っていて評判になったもので、医学書院から正式な出版の運びとなった。集団精神療法士による解説や施設に通う人たちのコメント、かるたのいろいろな遊び方など満載の小冊子「露地」、紹介のDVD、そしてなんと、市原悦子による読み札音声CD(このCD流していると本当にシュールですよ)までついた豪華版になった。DVDと小冊子でずいぶんと幻聴・幻覚のある人たちに親しみが感じられる。カルタは、メンバーの幻覚、幻聴を、文章にしたものを、読み上げてメンバーが皆で絵にしていって作られた。その様子も、ハーモニーの日常やインタビューとともにDVDに収められている。この豪華セットを楽しむと、しばしば登場する「若松組」や外車に乗った美女たちのイメージが、自分の中にも生き生きと浮かんでくるのである。 |
| シャロン・ケイ、ポール・トムソン『中学生からの対話する哲学教室』(玉川大学出版会) |
|
「子どもの哲学」研究は、今やかなりの広がりを見せているというべきだろう。先日も、ある研究会で、韓国の小学校での実践の映像を見たし、私が事務局を担当している研究会でも、関係する研究者に講演してもらったりしている。大阪の前橋下知事が、韓国に伍する英語弁論力をつけるために、トフルか何かの点数を一定以上取れたら助成金を出すというようなプロジェクトを始めたものの、条件を満たすような学校はほとんどなかったという話を聞いて、さてそれでは韓国の小学校で「子どもの哲学」をやっているビデオを見たら、そこに力を入れさせようとするだろうか、とふと思った。前知事は弁護士だから、英語よりもまずこっちに力入れようとか考えたらよいのだが。 さて本書は、中学生以上を対象とした、哲学のテキストの翻訳である。対話があって、設問があって、解説がある。討論テーマ、練習問題、活動や社会へのステップがあり、ブックガイドがある。議論を喚起する構成はよくできているし、学習事項もなかなか深いのだが、さてこれをどのように使うのか、というところで、私は立ちすくんでしまうのだ。面白い本であることは確かだが、何かがかみ合っていない。われわれはおそらく、ここに示されたような実践を、繰り返してきている。対話形式のテキストも、討論すべきテーマも、少なくとも私の周りの多くの教員は手を変え品を変え取り組んできているのだ。しかし、学習指導要領や大学入試が変わらない限り、持続的で総合的なとりくみはほとんど手がつけられない。例えば、本書で「社会活動へのステップ」として示される事例は、「学校や地域の清掃に参加して、環境を美しくしましょう」「ボランティアとしてパラリンピックで働いてみましょう」など、ほとんど学校から手が離れた活動になっていくし、「活動」にしたところでヘッセの『シッダールタ』を読み、グループを作って討論をさせるなど、それだけで何時間かかるか?というものなど、少なくとも授業のヒントとしては、新鮮味はないし、現実的ではない。 そろそろ岩波書店からも、高校倫理を入り口にしたシリーズが出るはずだが、このような書物が出てくるのは、高校倫理がよほど腑抜けた授業をしていると思われているせいであろう。しかしながら、以前に書いたことがあったと思うが、『ソフィーの世界』がベストセラーになったとき、多くの倫理教師は、「この内容のほとんどは、授業でこの程度の工夫はして言っているんだけどな・・・」と思ったはずだし、本書では、「いろいろとこんなのもあんなのも出したことあるけど、反応薄かったよな・・・時間も足りないんだよな・・・」と思ったはずである。本書が内容豊富であり、一つ一つ取り上げれば参考になる事も多いのは間違いないのだが、総体としては、われわれが仕事をしている枠組みからかけはなれている。そして、本書を日本に紹介している、監訳者の河野哲也先生はじめ「子どもの哲学」研究者の方々が本当に求めていることは、その総体、大きな枠組みを変えることだと思うのである。このかみ合わなさはどこから手をつけてよいのか、どうにかなるものなのかは分からないにしても、とりあえずはいずれにしても高校倫理教師側からの発信がなくてはならないだろう。それが私たちの役目である。 |
| ウイリアム・パワーズ 『つながらない生活−「ネット世間」との距離のとり方』(プレジデント社) |
|
最近、なかなかサイトの更新ができない。CDを前ほど買わなくなった(買えなくなった)のは確かだが、本や映画から遠ざかっているわけでもないし、音楽や本や映画から得られる喜びや発想が薄まっているわけでもないと思う。要は、それをサイトで公開するという営みに、今一つ、乗り切れなくなっているのだと思う。 このサイトを始めたのが1996年だから、もう15年以上になる。最初のころは「リンク」はサイトの重要な要素だった。関係のあるサイトを見つけたときは、相互に連絡を取って、リンクを張った。当時は、個人でサイトを開設するというのはそれなりにハードルが高かったから、何となくちょっとした優越感の漂う連帯感が、個人サイトの運営に感じられていたように思う。そのうち、ホームページビルダーのようなソフトウェアが普及し、個人サイトが増えていくのと並行して、グーグルなどの検索が便利になってきたので、サイト同士のリンクや、ポータルサイトへの登録が、だんだん意味を失ってきた。つながりがひろがっていきながら、薄まっていった。荒らしやスパムと戦いながら掲示板で作り上げてきたコミュニケーションも含めて、ブログやSNSが、個人サイト運営のてこずりながら得られるちまちましたひそかな楽しみを、便利さと引き換えに奪い去っていった。 個人サイトをきっかけに知り合った人々との交流は続いているけれども、その場所はもはやサイトにはない。ほとんどがSNSである。サイトを訪れる人々の数は、減ってきたとはいえ一日100くらいのアクセスはあるものの、そのほとんどは検索でヒットした人たちだろう。用が済めば声もなく去って行ってしまう。トップページのアクセスカウンタが一向に上がらないのは、かつてのように「巡回」してくる人たちが確実に減ったことを意味する。正直なところ、観た映画、読んだ本の感想も、CDの紹介も、本当はもうブログにしてしまった方が楽である。タグをつければ整理も簡単だ。何よりも、面倒くさくて、ときどき間違えてぐちゃぐちゃにしてしまう、HTMLを手書きしなくてよいのだ。 サイトを通じてのコミュニケーションが激減してしまったことは、サイト更新の熱意を薄れさせるのには十分な理由であり、それはまた悪循環を産み出す。更新が滅れば、古き良き巡回リストからも抜け落ちていく。ブログなら更新はRSSで知らせてくれるのに。 まったくもって、憂慮すべき状況だ。けれど、自分はどうしてもこのサイトを続けたい。ブログやSNSではなくて、なぜサイトなのか。それはもう、良くも悪くも、ここが最後の、自分のペースを守れるネット上のスペースだからである。わずかなリンクは残してあるけれども、ブログやSNSのような横のつながりはない。それは孤高と言うよりは、さびしい辺土かもしれないけれど、ネット上ではちゃんと検索にヒットする。それだけでよいのだ。あくまでもマイペースの、自分のことばの置き場所である。そもそも、そういう趣旨でここを始めたのである。来たい人だけ来てくれればよい。私も、行きたいところだけに行きたいのだから。 かくして、SNSでも私の友人はあまり増えないし、増やさない。「お友達かもしれません!」と自動的に届くメールは、すべて無視している。私にとってSNSは、読んで楽しいことを書いてくれる、ごく限られた友人の日記やコメントに和むための場所だ。もっとも「新機能」が加わるたびに、そういう使い方の妨げになるいろいろな邪魔が入るのだが(たとえばちょっと気になるニュースに目を通そうと思うと、その記事を読んだどこかのだれかが書いた、雑で腹立たしいコメントを目にしてしまうことがあったりする)。ツイッターはまったく使わなくなった。ほんの少し絡んだところで、ツイッターに親和的な文化とは自分はまったく反りが合わないように感じて、すぐに遠ざかってしまった。四六時中、社長のつぶやきを聞いていなくてはならない会社もあるらしいが、自分にはとうていそこの社員は勤まらないだろう。 この本の導入や結論は、うまい文章を書くと感心はしたのだが、あまり面白く読んだわけではない。圧巻は明らかに第二部、プラトン、セネカ、グーテンベルク、シェークスピア、フランクリン、ソロー、マクルーハンから、「つながらない生活」の知恵を見出す部分である。プラトンやセネカは(私にとっては)なじみであるが、グーテンベルクの発想とか、シェークスピアの時代にはやった「書いては消せる手帳」とか、実はあんがい「つながって」もいたソローの生活など、新しい知見がひろがり、素直に面白かったし、そこからの知恵の引き出し方も納得させられた。本の感想がこれっぽっちでは、それこそたまにここを訪ねてくれた友人もあきれて足が遠のいてしまうかもしれないが、実は自分の今の心境にとてもぴったりくる本だったのである。ついでに、も一つぴったりきたのは、YUKIの『揺れるスカート』の歌いだしの歌詞である。知らない人たちの不平不満のつぶやきは、私には関係ない。 |
| ヤマザキマリ 『テルマエ・ロマエ(1)〜(4)』(エンターブレイン) |
|
このマンガの存在は、映画の宣伝で知った。映画の方も面白そうなので、既刊の4巻まとめて読んでみたらもう本当に面白くて止まらない。作者のヤマザキマリ、14歳でヨーロッパ一人旅、17歳でイタリアに学び、古代ローマおたくのイタリア人と結婚し、中東からポルトガル、シカゴに移り住むという経歴もすごいし、ネタの引き出しもたくさんあるみたいで、他の本もいくつかさっそく注文してしまった。 私も古典古代には歴史的な興味ももちろんあって、作品の中のうんちくも楽しいのだが、なにはともあれ、みんなで裸になってお風呂に入ってくつろいでいたのは古代ローマ人と日本人くらいではないか、えーいタイムスリップでつなげちゃえ!的な基本の発想が素晴らしい。さつきちゃんだって、編集長がこだわった温泉芸者と、古代ローマおたくのご主人をくっつけちゃった、むちゃくちゃな設定である。この思い切りの良さは、作者の経歴と相関していると思う。作者によればもう結末は決まっているそうな。早く続きが読みたいものである。 |
| 松下良平 『道徳教育はホントに道徳的か? −「生きづらさ」の背景を探る』(日本図書センター) |
|
私が専門としているのは高校倫理教育なのだが、昨今の教育改革の中で「倫理」は取り残されてきている。そこにはもちろん危機感を感じざるを得ないのだが、ここまで「御座敷に呼ばれない」のもまた、奇妙な潔さを感じないでもないのだ。というのは、学校教育の荒廃やら何やらが問題になって、「心の教育」が必要だと叫ばれ、東京や大阪の強引な教育改革なるものが進行し、道徳教育が求められているというのに、どういうわけか「倫理」にはさっぱりお声がかからないのである。 私は今、自分の教員生活もそろそろ「まとめ」の段階に入らないといけないと思い、コツコツと「講義録」を作りつつある。教員になりたての頃は、社会科でパソコンを使った授業をやったり、現代社会の文化学習を研究したり、カウンセリング心理学を学びに大学院に通ったり、いまでも教室でインターネットにつないだり、まあそれなりに新しい授業には取り組んでいるつもりだが、私がまとめたい「講義録」は、あくまでも「倫理の授業」のそれであり、あくまでも生徒に語る授業である。 で、改めて文章にしてみればよくわかるのだが、倫理を学ぶと、たとえば親孝行を説くにしても、ルーツに中国の儒教文化があることを学んじゃうし、サルトルが親孝行と国のための戦うのとどっちがいいか聞かれたら自由なんだから自分で決めな、と言っちゃったりする話なんかがちりばめられているので、たぶん(カッコつきの)「道徳教育」をさせたい立場からすると、むしろ「倫理教育」は邪魔ものなのである。だから必修から外して(厳密にいえば必修だったのは「倫理・社会」の時代なので「倫理」が必修だったことはないのだが)、大学受験から遠ざけておけば、自然消滅するだろうと高をくくっているのではないかと思う。そうでなければ、私なんか学会でも「倫理」しっかりやろう的な発表や提言をしているので、とっくに消されてしかるべきであろう(大げさな・・・)。要するに、なめられているのである。悔しいです。 さて本書は、普通に倫理や哲学を学んだ人間であれば、どう考えても(カッコつきの)「道徳教育」にはおかしさが潜んでいる(というよりは、かなり堂々と表れている)ことにすぐ気付くわけで、そのことを「心のノート」などを手がかりに、分かりやすく述べている。ウチの学生に「心のノート」がどの程度使われているのかいつも聞くのだが、だいたい中学を卒業して2年くらいですでに使ったかどうかはっきり覚えていないという学生がまず大半だったりするので、さっぱり参考にならない。本書で取り上げられている「手品師」なども、記憶しているというのはごくわずかだ。 この「手品師」、簡単にいえばさびしい少年に手品を見せてあげるという約束を守るために、大きなステージに立つチャンスを棒に振る、お人よしの話である・・・ってことでよいのかな。で、私はこの手品師の判断を、一つの考え方にすぎないと読むのだが、本書で紹介される作者のインタビューには、私からすればあっけにとられるほど明確に、手品師はこのように判断すべきであるという意図のもとに作られていることが断定されているのである。なるほどこれには参った。 かつて、コールバーグ理論がはやっていたころ、私もいわゆる「ハインツのジレンマ」を授業で取り上げたことがある。今でもたまに使うことがあるが、ここでは道徳性の発達が言われているから、ハインツの行動(妻を救うために薬を盗む)に対する複雑な思いがあふれ出てくるからこそ、授業も意味をもつのであり、生命倫理分野の授業などもさまざまな「答え」が学生たちからひねり出されるところに面白さがあるのである(ある学生が「あーなんか今日は授業をやりきった気がする!」と言ってくれてうれしかったが、それを聞いた別の学生が「なんかよく寝ちゃった・・・」とつぶやいたりもする)。要するに、「ハインツには諦めるか盗むかしかなかったのか?」とりあえずはそういう状況設定だから、と言っても、学生は様々な「答え」を思うのである。しかし、「手品師」の著者も、文部科学省の手引も、それをむしろ否定するのである。 そこには明らかに、本書の著者が指摘するような、「道徳的であること」についての異様に偏った考え方があって、教科書検定すら必要のない副読本で、それが学校道徳教育に押し付けられている(この手は東京では「江戸から東京へ」のテキストでちゃっかり使っている)。なので、著者の意図にしたがうにせよ、文部省の指導書に従うにせよ、このテキストを使って授業する教師は、「やっぱこの手品師みたいにしようねッ!」というオチをつけさせられるのであろう。しかし、実際の授業では、そんな風なオチを(たぶん、仕方なしに不本意に)教師が付けるにしても、子供は納得しないのである。 かつて私が珍しく道徳教育の論文を書いた時、引用した一つが『銀の匙』であったが、まさに同じ一節を本書も引いていて、我が意を得たりというところだった。そう、『修身』だって、多少とも考えようとする子供であれば、そのおかしさは分かったのである。自己実現と共感性に裏打ちされた、多少なりともまともな道徳観を支える教育を果たそうと思えば、私は高校生ぐらいで「倫理」を学ぶことは大いに役に立つのではないかと考えている。 |
| P. G. ウッドハウス 『ジーブスとねこさらい』(国書刊行会) |
| ついにウッドハウスコレクションは完結してしまった。1975年に93歳で没したウッドハウスが、その前年に刊行した最後の長編だが、90歳記念の前作よりも完成度が高いように思う。いつものようにバーティが叔母さんや若い女性たちに右往左往し、だいたいが間抜けだったり変わりものだったりする悪友たちに振り廻されるのを、ジーブスが巧みな手腕で切り抜けるという展開だが、今回はジーブスの活躍はやや控えめだ。ドタバタ騒ぎの拡大と収束の振幅も、さすがに40年代から60年代の長編に比べれば穏やかではある。でも何か少し、バーティが成長したのかもしれないな、と思うと、案外納得してしまったりもするのである。しかし繰り返すがこれでジーブスものは終わってしまった。巻末に全14冊の簡単な紹介が付いている。今後もアンソロジーを予定しているようだが、ブランディングズ城ものはもうないのだろうか。エムズワース卿が大好きなのだが。 |
| 斎藤環 『「社会的うつ病」の治し方』(新潮選書) |
| 思えばプロザックが登場した時は華々しかった。もうこれで、うつ病なんかこわくない、とでもいうような勢いだった。しかしそのうち新薬も従来の抗うつ剤とそれほど治療効果が変わらないということもわかってきて、一方で非定型うつ、双極?型などが取り上げられるようになり、むしろうつの治療の難しさが知られるようになってきている。おそらくわれわれ素人は、「画期的な何か」を強く期待してしまう。画期的な新薬だけではない。画期的なエネルギー、画期的なイノベーション、画期的な政治家、画期的な掃除機・・・分かってはいるけれども、その期待はやめられないのだ。新しいタイプのうつ病に対しても、スパッと切れ味のよい病因論や病理論が出て、スカッと効き目のよい新薬や療法が開発されることを期待してしまう。しかしそれはうまくいかない。そんなところに、著者は「人薬」という言葉を紹介する。それは自己愛の発達についての新しい視点である。しかしそれは決して、単純明快な治療論を指し示すわけではない。リハビリテーションや成長支援、セルフケアに関して述べられていることには、現状への鋭い警告があると共に、説得力のある内容がある。なおこれまでの音楽療法とは全く異なったところから立ち現れた声楽療法の紹介は、思い当るところもあって、大変興味深かった。 |
| ジュリアン・バッジーニ、ピーター・フォスル 『倫理学の道具箱』(共立出版) |
| 同著者で既刊の『哲学の道具箱』姉妹編というべき用語集。単なる用語集と異なるのは、著者の立場や意見が明確に示されるところにある。概して用語集が役に立たないのは、中立的で網羅的な無難さからくる。中立的といっても実際には執筆者の立場があるわけだし、網羅的といっても用語の用例は実際には同じ人が使っていても揺らぐものだから、つまるところ何を言っているのかわからない難解なものになりかねず、用語集を引く前よりも一層、混乱するのである。その点、本書ではときにはすっぱりと切って捨てるような記述もあって、個々の項目が読み物として成立しているから、面白いし、たとえその立場に必ずしも納得しなくても、考える道具として活用すればよいのだから、役に立つのである。参照項目や読書案内も親切で、楽しい用語集である。 |
| 久住昌之・作 谷口ジロー・絵 『孤独のグルメ』(扶桑社文庫) |
| 先にドラマ評を見て、面白そうだなと思って本を買って読んで、ドラマを見て、どっちも面白かったという、私にとって幸せなパターンを踏んだ一冊。主人公の、40代独身、実は体育会系、過去に女優との交際歴あり、個人経営の無店舗輸入雑貨商という設定は、ほとんど感情移入しがたいはずなのに(酒が飲めないということはあんがい重要な共通点かもしれないが)、昼飯にそのへんの店に入って、なんだうまかったじゃないか、でもちょっと失敗もしたけど・・・というあたりで話が終わるという展開なのに、毎回飽きさせずに面白い。ちょっと大げさかもしれないが、何か「生きる=とりあえず食うということについての普遍的なもの」を感じさせる。初回がいきなり職場の近所のなじみ(というほどでもないんだけど)の場所、あと四回目までの吉祥寺・浅草・赤羽もそれぞれ縁のあった場所だったのも、私にとって興味を引く展開だった。初めての土地で飯食う店探して右往左往する話のあとがきにも共感。勢いで初期作品なども読んでみたが、ここから始まってここを経過してここへ行きついたのか、と妙に納得した。それはそうと、連載の残りが中途半端なので、単行本になっていない話が残っている。今も不定期連載らしく、いつ本数がそろうのか知らないが、ぜひ読みたい。ドラマの方も最初の方は見逃しているから、再放送(ないかな)かDVDになったら、ぜひ見たいものである。 |


