

 最近の更新(10年11月〜11年5月)
最近の更新(10年11月〜11年5月)
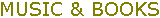
| >HOME >BOOKS |
| BOOKS |


 最近の更新(10年11月〜11年5月)
最近の更新(10年11月〜11年5月)
|
| 斎藤茂男 『生命かがやく日のために』(講談社+α文庫) |
|
日本のジャーナリズム史に残るいくつものルポルタージュを著した著者の、その中でもよく知られた一つで、生命倫理問題を取り上げた古典中の古典と言うべきもの。両親がダウン症で腸閉塞の新生児の手術を拒否していることに悩んでいる一人の看護師が、親の会に宛てた投書から始まる。それを知った斎藤は看護師を探し当て、取材を続けながら新聞に連載記事として取り上げる。反響は大きく、赤ちゃんの命を助けてほしいという声から、静かに死なせてあげるべきだという声、さまざまな声が届く。とりわけ、当事者でもない者が口出しすべきではない、医療関係者やマスコミにはとやかく言う資格はないという声を受けて、連載が終わってからも、斎藤は様々な立場や専門の人々に取材を続けていく。 手元にある文庫本は1996年発行だが、最初の出版は1985年で、今では法律や新生児医療などで当時とは異なる状況ももちろんあるが、斎藤が受け止めた問題意識は、実は何も変わっていないように思う。この当時はなかったコトバ、たとえば共生とか、バリアフリーとか、ユニバーサルデザインとかのコトバが響きよく繰り返されるようにはなったが、僕たちは生きやすくなったのだろうか。さまざまな障害の苦しみは和らいだのだろうか。授業で紹介するためにあらためて読み返してみて、四半世紀も前に出版されたこの本がまだ「現状について」語るために「使えてしまう」ということの意味を考え込んでしまった。 |
| エルヴィン・ヴァーゲンホーファー、マックス・アナス 『ありあまるごちそう』(武田ランダムハウスジャパン) |
| 副題「世界が飢えていくメカニズムがわかる」。日本でも公開されたドキュメンタリー映画の書籍版という位置づけ。単に食糧問題を扱ったというよりは、産業社会における人間の生の営みに踏み込んだ視点があると思う。著者たちはヨーロッパ在住なので、そこからの視点が特徴的だ。日常生活の中から、センセーショナリズムを求めることなく、現実に起こっていることを淡々と取材していくのみである。私は漠然と、アメリカよりはヨーロッパの方がよりましだろうというイメージを持っていたのだが、それは見事に打ち砕かれた。もはや農業や水産業、食品産業の大規模化、寡占化は、ヨーロッパでさえも避けられない。50の大企業が独占しているこの世界を「自由市場」と呼ぶことのとんでもない矛盾と欺瞞を認識しなければならない。その責任は私たち自身にあるということを気づかせてくれる。 |
| ダグラス・ウッド作 ジム・パーク絵 『よめたよ、リトル先生』(岩崎書店) |
| ADHDの診断を受けている作家である著者の、子供時代の経験を、やさしい絵柄で描いた絵本。発達障害を持つ大人は多いが、彼らの子供時代にはそのような診断名すらなかった。落ち着きのない子供だったり、乱暴な子供だったり、泣き虫だったり、「ダメな子」だったり、冷たくあしらわれた経験を持つものが多いはずだ。しかし、著者のように、根気強く付き合ってくれる先生や親、夢中になれる本や経験を持つことのできた人は、ちょっと変りものではあるけれど、ユニークな業績を挙げていたり、人に愛される大人になっているはずなのだ。今は発達障害の研究や臨床が進んでいるのに、結局そういう出会いがなく、恵まれない人々も少なくないのが現実だ。ところでこの著者は、ADHDに伴う発達性ディスレクシアかもしれない。そのサポートもまだまだこれからである。私はこの絵本を保健室に置いてもらった。保健室に来た子供たちが、何か自分のことに気づくきっかけになって、相談につながればよいと考えている。 |
| 西山雄二 『哲学への権利』(勁草書房) |
| これは貴重な本/映画である。著者/監督は、フランスの国際哲学コレージュを取材、関係者へのインタビューをドキュメンタリー映画に仕上げた。国際哲学コレージュは、1983年にデリダらによって創設された研究教育機関で、政府から運営費用は支出されるが、研究者たちは大学や高校の教育研究者などで、コレージュでは無償で研究教育活動に当たる。受講料も無料である。人文的なものの可能性をめぐって、さまざまな課題を抱えつつも存続している。だがそれでも、高校教員が研究のために与えられていたコレージュ参加の権利は脅かされ、難しくなった。日本の高校教員から研究のための権利が奪われたのと同様のことが、残念ながらフランスでも起こっている。そこには、工場の原理を人間生活の全てに及ぼそうとする、品質管理の思想、標準化の思想がある。そんなことを暗澹たる思いとして保持しつつも、付録と言うべきか本体と言うべきか、DVDを観、本を読みながら、人文知の奥行きと広がりにふれることの豊穣の喜びには抗いがたい。この権利は誰にも奪わせないし、奪われる事はない。 |
| 志茂田景樹 『蒼翼の獅子たち』(河出書房新社) |
| 維新期にアメリカに留学し、帰国後専修大学を開いた人々を描いた物語。『学校をつくろう』という題で映画化されたという話を聞いて、原作を読んでみた。仕事柄、学校という装置については関心を持たざるを得ないのだが、とにかく昨今の学校を取り巻く状況は、私にとってはどうにも救いがなく思えていて、とりわけ大学はどうなってしまうのだろう、という危機感がぬぐえない。そういう問題意識で読み始めたのだが、明治維新の時代に海を渡った若い留学生たち(津田梅子など6歳である)の群像を、読みやすい語り口でつづった内容に、すぐに没頭してしまった。それにしても、まず英語に堪能にならなくては学問ができない状況を何とかしようとして、彼らはテキストを翻訳し、日本語で学べる大学を作ったのである。今や小学校から大学まで、どこもかしこも「国際化」を口にして英語を学ばせようとしているのは、何とも皮肉なことである。 |
| 山地としてる 『ブタとおっちゃん』(フォイル) |
|
三重県で養豚業を営んでいたおっちゃんの日常を撮り続けた、モノクロの写真集。おっちゃんは宅地化の波に押されて養豚場を移転せざるを得なかった。市役所で農林水産行政に携わっていた著者は、おっちゃんが借金を背負って苦労していると耳にして、定年退職後に訪ねて行ったところ、そのあまりにも幸せそうな様子に、10年間写真を撮り続けることになったという。1200頭の豚はおっちゃんの手で大切に育てられ、味も良く何度も表彰されているそうだ。 食べられてしまう家畜を育てるというのは、どういうことなのだろう、という疑問がずっとあって、児童文学などでもそういうテーマのものを見かけるところからすると、そういう疑問は私たち外の人間には珍しくないのだろう。おっちゃんとブタたちの愉快な写真の数々を見ながら、その答えを確かめに写真展にも足を運んでみたが、もちろん答えは出なかった。でも、ふとギリシア哲学のアレテーのことを思い出した。アレテーは卓越性と訳す人もいるが、一般には徳の意味でつかわれる。アレテーとは、そのものの特性が最もよく発揮されていることである。馬のアレテーはよく走ること、刃物のアレテーはよく切れること、人間のアレテーはよく生きることである、といわれていた。ブタのアレテーは、おいしく食べられること、なのだろうか。ブタにとっては迷惑な、というか命がけの話なのだが、考えてみると私のような教師の仕事も、実はおっちゃんと同じような仕事なのかもしれない、と思えてきた。迷惑かもしれないが、学生たちを育てるのである。彼らを育てた結果、彼らはいわば現代の社会の養分となり、食われてしまうのだ。一所懸命に育てなければ、彼らは現代の社会では役に立たないから、食われることはないのかもしれない。それを幸せと見ることもあるだろう。老荘思想にはよく出てくる考え方だ。生命の尊重とかそういうことではなくて、教育と肥育に何か呼応するものを感じてしまったのは間違っているだろうか。私もおっちゃんのように肥育じゃなかった教育の仕事をしたいのかもしれない。迷惑かもしれないが、なんかその時はお互い幸せになれるんじゃないか。こんなことを考えているのは疲れているせいだろうか。 |
| 蔡志忠作画 和田武司訳 野末陳平監修『マンガ老荘の思想』(講談社+α文庫) |
| 「ブタとおっちゃん」↑を見ていてギリシア哲学やら老荘思想やらに考えが行ってしまったので、久々に老荘思想を読み直してみようと思った。これは文庫版なのでちょっと見難いのだが、達者な絵で楽しめる漫画版。どうして監修が野末陳平と思ったが、専門家だったのですね。「ブタとおっちゃん」を見ていて考えたことは、たとえば、「役に立たないゴンズイの木」などいくつかに登場する。もちろん、見方を変えればこれは負け惜しみの話になってしまう。それこそ相対主義の面白いところだ。儒家思想を相対化したというか茶化したようなところに道家思想の価値があるのだが、儒家思想がなければ老荘の相対化の値打ちがなくなってしまうとも言える。老荘のほうが深みがあるような印象を持っていたのだが、最近ちょっと見方が変わってきて、儒家思想の俗っぽいところに、かえって親しみを感じていたりする。それでもなお、老荘の話で好きなものはいくつもあるのだが。影から逃げ回る話とか。儒教的生き方に疲れたときは老荘思想、というのが、私のような俗人にとっての思想のユーザビリティというのが、この話の落ちだ。 |
| 高野秀行 『腰痛探検家』(集英社文庫) |
|
文庫あとがきで著者自ら、こう語っている。
本書の著者は頭がおかしい---。
腰痛治療を求めてさまよっていると、おそらくそういう状態になってしまうのだろう。自分自身、数か月前に、久しぶりに大きな一撃をくらって、ほぼ一週間動けなかったので、著者のようにかなり重篤で難治の腰痛に苦しんでいると、そうなるだろうということはよくわかる。まして、本職は探検ライターである。途方に暮れるのも無理はない。 |
|
今西乃子 『「ぼくの父さんは、自殺した。」ーその一言を、語れる今ー』(そうえん社)
自死遺児編集委員会・あしなが育英会編『自殺って言えなかった。』(サンマーク文庫) |
| 仕事柄、専門柄はもちろん、自分の身の回りを見ても、年間三万人を超える自殺者数は、他人事では全くない。私はNPO法人ライフリンクのシンポジウムに参加したことをきっかけに、さらに関心を深めることになったのだが、その代表である清水康之氏が、NHKを辞めてNPOの活動にまい進していく一つのきっかけが、あしなが育英会の自死遺児との出会いにあった。『「僕の父さんは、自殺した。」−その一言を、言える今−』は、著者によるインタビューをもとに構成されている。語るのは山口和浩氏。中学生の時に父親を自殺で失っている。あしなが育英会の活動からNPO法人ライフリンクにもかかわり、現在はみずからNPO法人自死遺族支援ネットワークReを立ち上げて活動している。『自殺って言えなかった』(サンマーク文庫)は、その山口氏たち11人の自死遺児が、あしなが育英会の活動から作成した手記『自殺って言えない』に由来するが、まさにそのタイトルこそが、自死遺児の苦しみと、その後の歩みとを物語っている。本書のあとがきで山口氏が語る内容は、仕事柄たいへん重く受け止めている。広い意味で子供たちにかかわる大人は、この二冊は読んでおくべきであると言いたい。 |
| 鈴木博之編著 『伊東忠太を知っていますか』(王国社) |
| 今年の夏は、儒教仏教神道キリスト教イスラム教と、東京近郊の宗教施設を見て回る集中講義を実施した。回っているうちに、伊東忠太つながりを見出すことになった。日本語としての「建築学」の名付け親であり、法隆寺の木造建築としての価値を発見した、著名な建築家であるが、とにかく個性的な天才であったことが知られる。もともと画家になりたかったというだけあって妖怪の意匠に凝りに凝っているのも面白い。築地本願寺は伊東にとっては不満の作品であったとは知らなかった。一方で会心の作という不忍池弁天堂は戦災でもうないが、この夏の講義で新しい弁天堂を訪れてはいるのである。わが母校の正門も伊東の手になるものであったとは、本書で知ったところである。対談を含む論集なので読みやすい本ではないのだが、図版も多数で想像力を刺激される。 |
| 小川仁志 『世界一わかりやすい哲学の授業』(PHP研究所) |
| 実際に街場で「哲学カフェ」も開催するだけあって、対話形式の記述が分かりやすく、引き込まれる。レヴィナスやノージックなど、なかなか難解な人物も取り上げつつ、厳選された15人の哲学者の思想で思想史もなぞれるのはすごい。おしまいは今をときめくサンデルである。帯には「サンデル本に挫折したあなたでも大丈夫」とあるが、たぶんこの本を先に読めば、サンデルの本もテレビも挫折せずに読んだり見たりできると思う。高校倫理の次にあるものが見える一冊である。 |
| 宮沢章夫 『アップルの人』(新潮文庫) |
| 妻が宮沢賢治を読みたいと言うので、仕事帰りに寄った書店の棚をアイウエオ順に見ていったら、宮沢賢治がなくて宮沢章夫があったので買ってしまった。読むのは久しぶりだが、あいかわらず面白い。ちょっとした気がかりやこだわりが、次々とあちこちに引っ掛かり、向きをかえたり飛んだり跳ねたりして広がっていくのが演劇的で楽しい。「アップルの人」をつけていく表題の一編や、なぜか例に出てくる住所が私の勤め先の近所だったりとか、ツボにはまって電車の中で読めない(読んじゃったけど)。 |
| 海堂尊 『ひかりの剣』(文春文庫) |
| 次男が子供の頃から剣道をやっているので、自分ではやらないのにどうも剣道、というか、剣道を続けている人たち、というか、その人たちの独特のフシギさ、が気になる。剣道ものの小説を読んだのは『武士道シックスティーン』以来か。この小説は、自身が剣道部だった海堂尊の、別々の医学サスペンス(読んでいないのだが)の登場人物たちが、医学生時代、剣道の宿敵どうしだったという設定で、おそらく実際の医学部リーグのようなモデルがあるのだろう(息子は芸術学部なので、通称芸リーグとかいうのがあるらしい。最初聞いたときはびっくりした)。外科の神様みたいな人がものすごい手練だったりなんて、いかにもありそうな設定で楽しい。解説は元警察庁長官・國松孝次で、これもまたおもしろい。東大法学部で剣道部だったおかげで、拳銃の弾を受けたくらいでは死なない体になったそうだ(笑)。 |
| 磯田道史 『武士の家計簿』(新潮選書) |
| この本は、歴史学者が願ってもない文献を手に入れた興奮がひしひしと伝わってくる、たいへんエキサイティングな一冊。金沢藩の御算用者を勤めた下級武士の親子三代の暮らしぶりがわかる。これを映画にしよう、と考えた人(脚本家か監督かわからないが)もすばらしいな、と思うのだが、実際に家計簿だけではなく手紙や日記も几帳面に保管されていたために、江戸末期から明治期という変動期の武士-士族の生活が、余計な解釈や演出なしに、ありのままに生き生きと描き出せる、この超一級の史料の価値ははかり知れないと思わされる。こうしてみると、やはり「数字」の力というのはたいへんなものだし、猪山家の人々からは、著者が言う通り、「恐れずにまっとうなことをすればよい」という生き方の力を学ぶことができる。ただそれだけに私は、この本を読んでしまうと、映画を見る必要は感じなくなってしまうのだが。 |
| 国立特別支援教育総合研究所 『発達障害のある学生支援ケースブック』(ジアース教育新社) |
| 発達障害はすっかり知られる言葉になって、一般向けの本もずいぶん出回るようになったので、図書館から選書を頼まれたときに迷ってしまったほどである。しかし、一般に大学や高専で教える教員が読んで役立てるとなると、日本学生支援機構や国立特別支援教育総合研究所の出版物をもっと活用したほうがよいと思う。こういったところの事業は、その時点での研究者を広く集めて行われるから、一人の著者や研究者が書いた本にくらべて偏りがないし、何よりもっとも現場に近い人たちの声が集まるから、実用的なアイデアが多くて「使える」本になっている。このケースブックでは大学高専の名前入りで実例が上がっているので、必要があればそこに問い合わせることもできるし、現場で使い勝手のよさそうな、シンプルなチェックリストも提案されていて、これから支援にあたろうというときに大いに役立つだろう。 |


