

 最近の更新(10年07月〜10月)
最近の更新(10年07月〜10月)
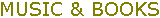
| >HOME >BOOKS |
| BOOKS |


 最近の更新(10年07月〜10月)
最近の更新(10年07月〜10月)
|
| 納富信留 『哲学者の誕生』(ちくま新書) |
| 副題は「ソクラテスをめぐる人々」。著者は国際プラトン学会の会長を務め、アジア発の大会を開催した、ギリシア哲学の研究者。高校の「倫理」ではソクラテス、プラトン、アリストテレスは定番中の定番であるし、倫理的内容がかなり削られた「現代社会」でもソクラテスは大体取り上げられるのではないだろうか。そして、ソクラテスの思想といえば「無知の知」である。ところが、ソクラテスは「自分の無知を知ること」とは一言も言っていないのである! はずかしながら、私もずっと「弁明」を読んでいて、そういえば確かにそういう言い回しはしていなかったのに気づいてはいたのだが、そこを深く読み込んで考えたことはなかったのである。ところでずっと気になっていた、ソクラテスが「罰金なら払うよ」という一瞬見せた日和見のような姿についても、著者は当然気づいていて、しかしそれは裁判上の手続き的な発言だったと解釈している。とにかくソクラテスを取り巻く人々や、対話編や裁判のいきさつなど、ギリシア哲学好きにとってはたいへん興味深い指摘に満ちている。残念ながら本書は現在品切れのようだが、ぜひ再版してほしいものである。 |
| ボブ・グリーン 『父からもうすぐ逝ってしまう君へ』(きこ書房) |
| さまざまな翻訳で読んできたボブ・グリーン、出先で「ちょっと読むもの」を探して立ち寄った書店で目に留まった本書を「新しいのが出たのか?!」とよく確かめずに買って(まあ副題の「心を揺さぶる37話」にひっかかりはあったのだが)、読み始めたら、ほとんど読んだ記憶がある。元がオリジナルのアンソロジーなのか、独自編集なのかは分からない。というか、その種の解説が一切ない。いずれにしても、今、こういうセレクションというのも釈然としないところがある。一つ一つは感動的な話なのに、こうして集められたときに妙に保守色が強く感じられるのである。副題にせよ、美しい装丁や挿絵(このヒラノトシユキという人の絵はスキです。どこかリサとガスパールを思わせるやわらかい感じ)にせよ、解説がない事にせよ、これまで彼のコラム集を読んだ事がない人をターゲットにしたのだろう。まあ父子モノなんかには何度読んでも結局泣かされるんですけど、読みなれている人にはかなりがっかりな一冊。こういう仕事に出会ってしまうと、『チーズバーガーズ』シリーズを編んだ訳者の井上一馬の目利きの良さに、今更ながら気づかされます。 |
| チャイナ・ミエヴィル 『ジェイクをさがして』(ハヤカワ文庫SF) |
| 現代イギリスSFの重要作家の短篇集。タイトル作といい、巻末の「鏡」といい、緩慢に崩壊する大英帝国の憂鬱を置換したような濃密な背景が、濃厚なイメージを喚起する。そこに、ゴシックホラーな物語が展開する。商標やチャリティについてのシニカルな小話を挟み込む構成も巧妙。イギリスSF、ホラーSF好きには楽しみの詰まった一冊。 |
| 大下智一 『山下りん 明治を生きたイコン画家』(北海道新聞社) |
| ニコライ堂の名でよく知られる、お茶の水の東京復活大聖堂は、火曜日から金曜日の午後に見学に訪れると、信徒の方が解説をしてくださるのだが、その方のご関心によって、お話しいただく内容はさまざまなので、訪れるたびに理解が深まってありがたい。先日、学生を連れて見学に伺ったときに案内していただいた男性信徒の方は、イコンについてたいへんくわしく、丁寧に教えてくださった。その時に知ったのが、この女性イコン画家、山下りんのことである。明治の初め、絵を学ぶために茨城から東京へ出て、浮世絵師や日本画家について、日本最初の美術教育機関である工部美術学校に入学。同窓生の山室政子の影響で正教会に入信し、ニコライの推薦でロシアに渡り、修道院でイコンを学ぶ。帰国後はひたすら、イコン制作に没頭する。あまり他人との接触を好まなかったという山下の日記を手がかりに、その人柄と労苦を偲ぶ。新書版ながらカラー33点、白黒27点の図版も美しい。 |
| 北野邦孝 『神経内科の外来診療』(医学書院) |
| 副題「医者と患者のクロストーク」。両親がかかっている関係で神経内科とはこのところ長い付き合いだ。神経内科外来専門の病院を松戸に開院している著者は、いわば「街の神経内科」として医療にどのように取り組むかを考えていて、その部分がまず非常に面白い。街医者には標榜にかかわらずいろいろな患者が来ることが、まず前提になるという考え方は、長い付き合いになる患者からすればじつにありがたいものではないか。疾患に関する部分は、患者の訴えに応えていく形式になっていて、一つ一つの症例を、実際の初診を想定した患者との対話ではじまり、解説から処方例のみならず、時には医療政策の課題まで話は展開する。神経難病や認知症について知りたくて読み始めると、神経内科を手がかりにした医療全般の問題点にも気づかされることになる。 |
| 水木しげる 『総員玉砕せよ!』(講談社文庫) |
| この夏は、集中講義で、東京周辺の宗教施設をあれこれ見学に行くというのをやっていて、靖国神社にも行ってきたのだが、遊就館にも特攻の若者たちの遺書などが展示されている。どれも読んで思うのは、こんな風に他人の命を捨て駒のようにした連中への怒り、死んでいった若者たちの哀れである。例年の夏の読書の二冊目が本書。もうだいぶ以前入院した時に、著者の『ほんまにオレはアホやろか』を読んで感動と慰めを得、病院の図書コーナーに置いてきたが、もう一度読みたいと思う事がある。そうこうしているうちに、テレビでは『ゲゲゲの女房』が始まって、なかなかの人気。ドラマの中で登場した本書を読んでみた。著者の作品にはヒネリがあって、マンガの内容そのものだけでなく、あとがきにあるように真実と違う部分を明らかにする事によって、より考えさせられるようになっている。それは、玉砕と言っても、実際には必ずしも全員が死んでいるわけではない、ということである。理不尽な死を強要されることだけでなく、玉砕ということばで死を美化しようとすることへの、二重の憤りが描かれているともいえるのである。貴重な「生き残り」の貴重な証言は重い。 |
| 秦郁彦 『昭和史の軍人たち』(文春文庫) |
| 恒例の夏の読書、今年は今まであまり興味がわかなかった、昭和軍人の実像に触れようと思った。年をとるにつれて組織があれこんなことで動いちゃうの?ということにずいぶんと驚きあきれることが増えたうえに、自民党政権も民主党政権もあの体たらくというのは、組織論以前の個人の問題にも、もっと重点を置かないとかなりやばいのではと思うことがあった。いったいどうしてあの時代の国はあんなふうに動いてしまったのか、そこに働いた(あるいは働かなかった)個人の側面を見たい、と思ったのである。古い本なのだが、陸軍・海軍それぞれ13人ずつを、緻密な史料考証をもとに描きだした本書の読みごたえはすばらしい。戦争に限らず歴史をいくら学校できちんと教えろと言われても、歴史を動かした(あるいは動かさなかった)個人について、十分に学校で学ぶことはとてもできない。もっと実用的なことをたくさん学ばなければならないからである(だいたいやれコンピュータをやれ英語をやれと言いながら、もっと歴史もやれったって無理なのはわかるだろうが。そういうことを言っているやつはどうせ偽装請負やらサービス残業を見て見ぬふりをする経営者とかに多そうだが)。ただ、個人のエピソードというのは、わりととっつきやすいことは確かなので、こういう本は勧めやすいことは確かだ。まあ実際に読む学生はほとんどいないだろうが・・・。世間の風潮や流行に動かされず、地道に徹底的に文献研究を貫く著者の著作は信頼でき、どれも迫力と説得力があると思う。 |
| テリー・ビッスン 『平ら山を越えて』(河出書房新社) |
| 中村融編訳の中短編集。傑作ぞろいなのは言うまでもない。私の大好きなロードノベル系はもちろんだが、処刑や安楽死といったシリアスな問題を真っ向から取り上げた作品にも、怒りとともに独特のシニカルな視点があって、近未来の設定のリアルさも手伝ってすぐに引き込まれてしまう。あっというまに読み終えてしまうこと請け合い。 |
| ウィリアム・R・ミラー、ステファン・ロルニック 『動機づけ面接法 基礎・実践編』(星和書店) |
| 動機づけ面接について学ぶと、大いに納得させられることがある。それは、著者たち自身が明確に認めるように、ロジャーズの業績の再確認である。ここのところ認知行動療法を主流とする「新しい」心理療法やカウンセリングが話題になることが多く、またその有効性も確かめられてきたところであるが、薬物療法を主とする医師(というと語弊があるのは承知であえて)よりも、はるかにセラピストの力量が問われるところがあると感じている。特に積極技法がとられるときにセラピストへの信頼感を作れているかどうかということになると、もっとも重要なのはクライアントセンタードもしくはパースンセンタードの態度であって、そこにはたしかに技法以前のものがある。ロジャーズはしかしそれを技法として定立したのである。著者たちは依存症治療の効果的な治療法の開発からスタートして、いまや幅広く「行動の変化」を生み出すための面接法としてこれを開発している。「動機づけ」というと、いきなりロジャーズとはなじみにくい行動主義をイメージするのだが、アンビバレントな感情から自ら変わろうとする意志をどのようにクライアント自身の中にはぐくませていくかというときに、まさに非審判的態度が有効になるのである。構造はいたってシンプルであり、それでいて有効性が高い。どのような技法・流派であれ、自らのセラピーなりカウンセリングを振り返りつつ向上させるのに役に立つ一冊であるし、これからカウンセリングを志す人にとって、学習法まで網羅した本書は最初に出会ってもよいテキストかもしれない。 |
| M.チクセントミハイ 『楽しみの社会学』(新思索社) |
| 全くどうでもよいことだと思うが、古今東西の私が知っている学者の名前の中で、一番好きなのがこのイタリア生まれのハンガリー人でシカゴ大学の教授、ミハイ・チクセントミハイである。さてチクセントミハイといえば「フロー体験」である。何かに熱中している時の状態であり、それは川の流れに乗って流れているようだということで、東洋的に言えば没我とも純粋経験とも通じるであろう。それ自体は、うまく名付けたなあという程度のことにも思えるが、この社会心理学者のたくらみは、生活の様々な局面、たとえば教育や仕事の場に、いかにフロー体験を生じさせるかにある。自身がかなりの楽しみ上手(絵は個展を開くほどの腕前、ロッククライミングもするそうで)というのは、重要なポイントだろう。この初期の研究では、統計的手法を用いたさまざまな調査や実験を通じて、フロー体験を明らかにする。以後のフロー体験研究の出発点。 |
| フレドリック・ブラウン 『さあ、気ちがいになりなさい』(早川書房) |
| 異色作家短編集、言わずと知れた星新一訳の復刊である。といっても、私はブラウンの短編は小中学生の頃、創元文庫版を全部読んでいるので、本書所収の短編のほとんどは、異なった翻訳で読んだはずであるが、しかし改めて読むと、読んだことのある短編はすべてよく覚えているのに驚いた。私の世代なら星新一や小松左京のショートショートに親しんだものは多いはずで、その原点がここにある。とにかくブラウンに参ったのは、「神ネタ」が多いことだった。解説で坂田靖子が『唯我論者』を暗記してしまったと述べているが、私もあれはお気に入りの一編だった(本書には所収されていないが)。唯一神という存在は、それ自体が絶対的なユーモアであり、同時にアイロニーである。ブラウンは推理作家でもあったから、SF小説では推理小説の禁じ手で思う存分遊びまくっているようにも思う。いまどきの読者にどの程度通用するかわからないが、落ちが分かっているのに繰り返し読む楽しさを与えてくれた作家との出会いなんて、今になって思えば、滅多になかった。本当に恵まれた出会いだったのだ。 |
| サイモン・シン&エツァート・エルンスト 『代替医療のトリック』(新潮社) |
|
ご多分に漏れず私は何回かぎっくり腰をやっていて、さらに腰痛持ちといってもよい状態である。かつては整形外科や整骨院に通ったが、最近では市販の湿布を貼ってできるだけおとなしくしている。経験的に、医者に行こうが整骨院に行こうがおとなしくしていようが、それほどの違いがないと判断したからである。しかしながら、地元で評判を聞きつけて行った整骨院で、きわめて不快な思いをしたことも大きい。 手首と足首に突起のついたゴムバンドを着けて、おなかに電気あんかのようなものを当ててベッドに横になるのだが、これはけっこう気持ちよかった。それだけだったら、私はその整骨院に通ったかもしれないのだが、あとがいけなかった。 そこの院長は、湿布をすることがいかによくないか、という話を始めたのである。まず、湿布を貼った私をまっすぐ立たせる。そして、胸を押すのである。当然、後ろにふらつく(腰痛で来ているのに何をやらせるんだ)。ここからがとんでもないのだが、湿布を剥がして、「さっきより強く押すよ!」とのたまったヤツは、胸を指ではじくのである。痛いのだが、押す力は当然弱い。だから、後ろにはふらつかない。「な? 痛かっただろ? 痛いくらい押してもふらつかなかっただろ?」 そして、今でもはやっているのかどうか知らないが、スパイラルテープなるものを貼られて、終わりである。 その整骨院にあふれる老人たちは、こんなトリックにだまされているのだろうか? 公平に言えば、はじめの部分で腰痛は少し楽になったので、一般的に整骨院の施療を否定するつもりはないのである。だが後半は明らかにトリック、イカサマである。同じやり方でもう一度押してみてくれませんか、と質問すべきところだが、ぎっくり腰でやってきた診察室でその勇気はさすがにないのである。それ以来、どうも整骨院というところには行くのがおっくうになっている。 本書では、鍼、ホメオパシー、カイロプラクティックなどに関する科学的な研究の歴史が丹念にたどられていて、代替医療の多くがプラセボ効果よりも有意に効果があるとはいえないという結論に至ることが示されている。明らかに害があったり、危険なものもあるし、明らかに金儲けの道具としかいえないものもあるが、控えめな効果があることを否定できないものもある。それは、腰痛の時に普通にマッサージしてくれれば、楽になるということなのである。だから、カイロプラクティックに行くのなら、その前にオステオパシーを試すことを勧めていたりする(より危険が少ないので)。どう考えてもホメオパシーは徹頭徹尾、理解不能であるが、しかしだからこそ、根強いのかもしれない。 著名なサイエンスライターと、自身で代替医療に関わっている科学者のコンビは強力である。分厚い本だが、取り上げられている研究エピソードがいちいち興味深いので、一気に読んでしまう。ナイチンゲールが統計学に詳しかったことや、壊血病の研究がどのように進んだかなどの、導入部のエピソードも、案外、興味深い。 |
| P.G.ウッドハウス 『がんばれ、ジーヴス』(国書刊行会) |
| いつも楽しみなウッドハウスもの、今回はちょっと変則的で、ウースターとジーブスのトトレイ・タワーズものの長編の後に、短編が3つ収録されている。で、この本編なのだが、例によって何組かの男女の恋愛ドタバタ喜劇を楽しく読み進めていくのだが、どうも最後のほうのジーブスの動きが、釈然としない。最初読んだときは、なんだか連載打ち切りになった新聞小説か何かのような気分になったほどだ。とはいえ、何らかの事情で無理にまとめてしまったのでないとすれば、その謎解きが別の作品にあるのかもしれない。何といっても、ジーヴスがこれからトトレイ・タワーズで何をどうするのかが、何も書かれていないからである。というわけで、ちょっと割り切れない読後感を、期待感で紛らわせることにしよう。 |


