

 最近の更新(09年08月〜12月)
最近の更新(09年08月〜12月)
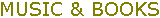
| >HOME >BOOKS |
| BOOKS |


 最近の更新(09年08月〜12月)
最近の更新(09年08月〜12月)
|
| 榊原憲 『死蔵特許』(一灯社) |
| 死蔵特許問題というと、そもそも言いがかりをつけて和解金を取るための会社があるという印象でいたが、本書を読むと、テレビ会議技術の会社が合従連衡やM&Aを繰り返しているうちに死蔵特許に気づいて、期限切れギリギリに動くまでのいきさつが詳しく述べられていて、アメリカの企業社会の仕組み全体から問題を眺める事ができる。こうしてみると企業社会における知的所有権の問題というのは、ナイーブな技術者の立場からはかなり手に負えないモノなのだということがよくわかる。職務発明問題もついエンジニア対企業のような単純な図式で見てしまうが、企業そのものが明日をも知れない状況を踏まえて注意していないと、職務発明がどこへ行ってしまったのか把握しそこないかねない。著者は経営工学の研究者で、ジャーナリスティックではなく客観的で分析的なレポートになっているところがよい。 |
| くさか里樹 『ヘルプマン! (11)・(12)』(講談社) |
| 日本認知症ケア学会の特別賞を取ったことから知ったコミックスで、読んで納得した。もともと介護をテーマにしたコミックスという、画期的な作品で、そうとう綿密な取材や調査によって成り立っていると思うが、この認知症編の2冊を読むと、認知症者から見た世界の描き方に、息苦しくなるほどの切迫感がある。人が認知症になったとき、誰が一番最初にそれに気づくのかというと、それは本人である。その不安や恐怖、否定したい現実を超えて、どのように周囲の世界との新しい関係をやりくりしていくのか、その過程が、たいへん丁寧に描かれていると感じる。 |
| スタニスワフ・レム 『泰平ヨンの航星日記〔改訳版〕』(ハヤカワ文庫SF) |
| オムニバス形式で、どの作品も文明批評なのだということはすぐわかるのだが、いったい何を俎板に載せているのかということが今ひとつハッキリせずに、まだるっこしい感じがすることも多いのだが、ミクシィのレムのコミュニティで、出版関係者の方や丁寧や読み手の方がいろいろと情報を書き込んでくださっているので、この作品のいろいろな謎が少し解けたりもして、ありがたい事である。そして、すでに初版から半世紀が過ぎて、社会情勢は大きく変わったはずなのだが、ユーモアと裏腹の饒舌な皮肉に満ちた物語の寓話性が未だに命脈を保っていること自体が、最大の皮肉と言うべきかも知れない。 |
| 岩崎夏海 『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら』(ダイヤモンド社) |
| ブログ発の小説やエッセイが出版されることが増えているようだが、本書もきっかけはブログということだ。著者は芸大の建築を出て作詞家の秋元康に師事、放送作家やプロデュースを経て、今は制作会社でマネージャーをしているという人。ドラッカーを読んだのも数年前とのことだが、おそらく主人公のみなみちゃんが読んだように、著者もドラッカーを読んだのであろう。ワタシは経営学には不案内なので、もし大きな誤解があったら申し訳ないのだが、ドラッカーの経営学が魅力的だったのは、経営学をあたかも人間学であるかのように、人々に捉えさせたところにあったと思うのだが、本書はまさにそのような読み方にそった入門編のようだ。もちろん、最終的には成果につながらなければならないので、物語もしかるべく展開していくのだが、たとえばみなみちゃんがドラッカーを読む代わりに、アドバイザー役の登場人物がいたとすると、ちょっとうまくいきすぎだけどこの表紙にこの挿絵のライトノベル的にはアリじゃない、というような、さらりと読める本という事になる。「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら、という設定とタイトルに、それらしいイラストを付けたら」どれくらい売れ本になるか、というマーケティングの勝利。さすがだ。 |
| ポール・トーディ『イエメンで鮭釣りを』(白水社) |
| これは面白かった。著者は会社勤めをしてきてこの59歳でものした処女作がベストセラーと言う変わり種。トビケラの研究をしている水産学者の主人公が、イエメンの富豪に依頼されて、砂漠のワディで鮭釣りを可能にするプロジェクトに巻き込まれていく。銀行で出世コースに乗る妻、研究所の上司や首相の取り巻き、富豪との間を取り次いだ魅力的な不動産管理会社の女性といった人物たちに、イギリスの政治情勢や中東問題が絡む。インタビュー形式が挟まったりシナリオが出てきたりという構成も凝っている。ただ、途中から聴聞になるので、ああ、どこかうまくいかなかったんだな、という方向が見えるのが、あえてこういう形式にする意味があったのかな、という疑問を抱かせるのも確かだ。人物像もやや紋切り型と言える。とはいえ、この主題の突拍子のなさが、あまりにも魅力的で、物語の快楽におぼれてあっという間に読み終えてしまうのがもったいない。映画化してもよさそうだ。 |
| ムハマド・ユヌス 『貧困のない世界を創る』(早川書房) |
| 先日、ドキュメンタリー番組を見ていたら、日本の若者にも「ソーシャル・ビジネス」を始める動きが出てきたというようなテーマだったので、どれどれと見ていたが、漫画家志望の若者に共同生活の家を貸し出すとか、そういう例が出て来て、ユヌスのグラミン銀行のケースとはだいぶ違った流れだがこれらを「ソーシャル・ビジネス」と呼ぶのか?という疑問を持った。調べてみれば、経済産業省のサイトには、わりと明確な定義が出ていて(http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g70925a03j.pdf)、第一の条件である「社会性」がポイントであることがわかる。しかしそれでも、ユヌスのビジネスの切実さを思うと、経産省の定義でもまだ範囲が広い気はする。なぜだろう。マイクロクレジットに続く、ダノンやグラミンフォンのビジネスは、バングラデシュの社会問題を根源から変えようというラジカルさがある。われわれの国で、これに匹敵するソーシャル・ビジネスがどのようなものになるのか、と考えてみるのは興味深い。それにしても、村人たちの合計たったの27ドルの借金を、単に施して終わるのではなく、適正なローンで貸し付けることで、かえって村の経済活動を、つまり貧しい人々の生活水準を、確実に引き上げることのアイデアにつなげたユヌスの発想は、貧しさへの確かな配慮から湧き上がっている。「社会性」ということばのそっけなさに欠けているのはそこだろう。 |
| 香川知晶 『命は誰のものか』(ディスカヴァー携書) |
| 生命倫理学者の著者が一般向けに書いた、新書版の概説書と言える。表題初め10の問題を、有名な事例を取り上げながら、コンパクトかつ要点をついた解説で論じている。どの問いにも私たち全部にあてはまる答えは出てこないのだが、考える手がかりとしての科学的事実や政治経済的背景がないと、思索そのものが果てしなく後退していく。そういう意味で、便利なハンドブックとしても使えそうな本書は、生命倫理学に興味があるものには、必携の一冊である。 |
| 三浦俊彦 『戦争論理学』(二見書房) |
| 原爆投下を主として、第二次世界大戦にまつわる倫理的諸問題を、論理学の手法を用いて分析するという、斬新な書。論理的思考のレッスンとしては、著者も言うように「歴史」の問題は膨大な事実の厚みがあるために、扱いは決して単純ではない。しかし、形式論理学の手法自体が適切に適用されていれば、仮に事実の間違いがのちに明らかになったとしても、思考の道筋はそのまま適用できるわけである。最近はやや下火の感のある歴史教育論争であるが、このような考え方の道筋についての自覚に立った論考がどの程度あったのかについては、再評価が必要だろうし、哲学者の役割もそこにあることがよくわかる。 |
| 末木文美士 『仏教vs.倫理』(ちくま新書) |
| 長らく高校倫理の教科研究をしてきて、問題に思うのは、内容更新の遅さである。もちろんこれは学習指導要領の改正と大学入試が絡む中で教科書更新が行われることからきていて、いわば教科書的な「公式」ができてしまっているせいである。最初に誰かが作った枠組みが踏襲されて、よほどのことがない限りは変えない方が安全(なぜなら、それで審議や検定を通っているので)というスタイルである。 例によって前置きが長くなったが、そんなわけで、高校倫理でも「鎌倉(新)仏教」という枠組みが長く使われていて、そこに禅宗・浄土宗・日蓮宗の三つが分類され、それぞれ只管打坐、専修念仏や悪人正機、法華経などがキーワードとしてセットされ、入試に対応するようになっている。いったん、このような図式化が行われると、入試にでるから教科書は変えない→教科書に載っているから入試に出す、という自家撞着に陥ることになる。この「鎌倉(新)仏教」という枠組みがいかにおかしいかを、わかりやすく説いた著者は、本書で「倫理」の枠組みと「仏教」の枠組みをあえて対峙させる。それは、高校倫理が、宗教を倫理を越えるものとしてほのめかしつつも、宗教教育に踏み込むことのためらいと、そもそも教科が「倫理」であり宗教をいわば「倫理ー内ー概念」とでもいうべきものとして扱わざるを得ないことへの、当然の刺激になり得る。そして、我が国の仏教が、それぞれにその当時の通俗的な道徳や常識に立ち向かってきた道筋をたどることができる。テーマは深いのに、いつもの分かりやすい語り口で、つい引き込まれるおもしろさである。 |
| 日本公民教育学会編 『公民教育事典』(第一学習社) |
| 私は2ページしか書いていないが、一応、宣伝である。事典といっても、原則として一テーマ見開き2ページで、ソフトカバーの手軽な読み物風である。手前味噌になるが、それ故にかえって、一つ一つの項目がきわめて中身の濃いものに仕上がっているし、授業にすぐ役立つ的なものではなく、一歩引いたところから公民教育について見つめ直す内容が特徴である。私が担当した項目も、従来あまり取り上げられてこなかったテーマで、調べているうちにかなりの分量になってしまい、泣く泣くかなり削ったのである。もったいないので、別の機会にさらに深めて論文にしちゃおうかなと思っている。というわけで、公民科教育に携わっている人には、大変便利なガイドブックとしておすすめできるものである。 |
| ロバート・チャールズ・ウィルソン 『無限記憶』(創元SF文庫) |
| 『時間封鎖』の続編。前作は「仮定体」の謎が壮大なスケールで提示され、読者は新たな物語に向けて放り出されたところだったが、本作ではそれを受け継いで、新世界で生じる異変に翻弄される登場人物と、特殊な能力を持った少年をめぐる展開となっている。前作があまりにも規模の大きな構成だったので、本作ではごくわずかな時間の経過があるのみというのがちょっと肩すかしではあったのだが、比較するからそうなるので、本作にもあっけにとられるネタがあれこれと詰まっている。不思議な降灰はイメージするのにわくわくする。仮定体の正体は仄めかされたままに終わるが、さて完結編と言われる次作が読めるのはいつか。 |
| 田辺鶴瑛 『ふまじめ介護』(主婦と生活社) |
| 副題が「涙と笑いの修羅場講談」。講談師の著者が実母、義母、義父の介護経験をつづった本。実母が脳障害で植物状態になった時、著者は18歳。結婚してからは義母をみとった後、講談師修業を始め、介護経験を講談に仕立て、現在は認知症の義父を介護中。介護は大変なことであるけれども、それをどう乗り切るかについて、経験と交流に基づいたお話はとても参考になる。家族の在り方についても、さらりとした書きぶりの中にたくさんのメッセージがある。認知症で寝たきりの人にリハビリやって機能回復したらかえってひどいことになるということなど、言われてみないとわからなかったし、考えさせられる内容だ。介護に当たっていない人も、いずれいつどうやって訪れるかわからないその時のために、一読しておくとよいのでは。 |
| 内田樹 『下流志向』(講談社文庫) |
| 2005年の講演をまとめた本が2009年に文庫化されたわけだが、あとがきにもあるように、内容が全然古くなっていない(だからこその文庫化だが)のは喜ぶべき事とは思えない。なぜ若者は学ばず、働かないのか、という問題を明快に解きほぐす論考として、これ以上のものが出ていないというのが現実だろう。教育の仕事をしていると、当然のようにこうまで勉強をしないでこうまで平気な子どもたちが増えてきて、そのための対策をあれこれ立ててやればやるほど、どうもこれは全く方向を誤っているという不安が確信に変わってくる。勉強をしないというだけでなく、勉強をしない、出来ないことに全く不安がないことに、こちらが不安になるのである。最初から最後まで、そうそう、その通り、ということばかりだが、この先に何が見えるのかを考えると、多少の行き過ぎはあっても巧い具合に振り子が揺れ戻っていくのかどうか、まだ心もとない気はする。 |
| グリンダル・シン・マン 『シク教』(春秋社) |
| 一般にはシーク教と呼んでいるが、インドのパンジャブ地方で16世紀に成立したこの宗教、髪の毛を切らずにターバンでまとめたインド人の典型がシク教徒のように思われているが、実際には二千万人ほどの少数宗教である。開祖ナーナクはグル(教主)、その弟子たちをシクと呼ぶことから、この名がついた。ヒンドゥーとイスラムの文化の交わりの中に存在する一神教で、ムガル帝国、イギリス、インドとの対立を経ながらも、今日の宗教的地位を形作ってきたプロセスが本書でよくわかるのみならず、仏教も含めて、多様な民族と文化と宗教が入り混じるインドの一面も見える。 |
| 釈徹宗 『不干斎ハビアン』(新潮選書) |
| 16世紀後半、禅僧からイエズス会士に改宗し、仏教・儒教・道教・神道・キリスト教を比較して、キリスト教の優越を説いた『妙貞問答』を著しながら、棄教してキリシタン批判に転じ『破提宇子(はだいうす)』を著した、類のない人物の研究。林羅山との対決もあった。これまでも学者や文学者によって取り上げられ、それぞれに毀誉褒貶されてきた。本書の著者は浄土真宗本願寺派の僧侶で、解説も丁寧で文章も読みやすくて、ハビアンという人物のイメージがつかみやすい。先人の様々なハビアン像を検討しつつ、「宗教」を捨てた宗教者としてのハビアンにたどりつく。ハビアンに合理主義的人間の宗教に対する態度や、現代日本人の宗教観を見出すなどの諸説を超えて、より普遍的なあり方として、「宗教」を捨てた宗教者としてのハビアンにたどりつく。 |
| 山口二郎 『若者のための政治マニュアル』(講談社現代新書) |
| これを書いているのは2009年8月31日、民主党が歴史的勝利をおさめた総選挙の翌日である。郵政民営化選挙につづいて政権選択選挙、争点があまりにも単純化されていて、実際にはほとんど選択の余地がなくなってしまう選挙構造と、その中で雪崩を打って極端な結果が出る投票行動は、まるでこの日本は変わっていないという恐ろしさに震えるばかりだが、これからの政治の動きには目が離せないという意味では、われわれ自身が試されつつ政治にかかわっていく最後のチャンスかもしれない。 そんなときに、本書を読むのは、新鮮な思いがある。書かれたのは一年近く前だが、状況的にはまったく古くなっていない。ルール1から10という形式で、具体的な例をもってわかりやすく政治の仕組みについて説いている。私が特にこの本を読んだのはルール7「権利を使わない人は政治家からも無視される」の中で、政治教育の不毛について述べられていたからであるが、普段の政治行動を避ける(ように教育されている、のかもしれないが)ことで、投票行動において一気に雪崩現象が起こるのではないか、という気もしてきた。選挙やって決めよう、というのは実はいかにも乱暴なことで、本当は郵政事業であれ、子育て支援であれ、日常の政治的議論として盛り上がっているべきものだ。ガタガタの自民か、ゴチャゴチャの民主か、どちらを選ぶといわれても困るのだ。どちらを選ぶにせよ、選んだあとに何が起こるかを見ているだけではなく、日常的な政治参加が必要なのだ。 |


