

 バックナンバー(08年01月〜6月)
バックナンバー(08年01月〜6月)
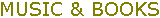
| >HOME >BOOKS |
| P. G. ウッドハウス 『エッグ氏、ビーン氏、クランペット氏』(国書刊行会) |
| 毎回楽しみなウッドハウスの翻訳、今回は短篇集。ドローンズ・クラブに集うちょっと困った男たちのエピソードが綴られる。主人公が入れ替わるのでちょっとあわただしく、ウッドハウス初心者にはあまり勧められない。ワタシにとってもいまひとつのめりこめないのが残念だが、どんどんもつれていくドタバタ劇はあいかわらずの楽しさである。しかし現実にユークリッジみたいな友達がいたら、かなりうっとうしいだろう。 |
| ジョン・エリス 『機関銃の社会史』(平凡社ライブラリー) |
|
戦争が科学技術を発展させる、というような言葉はよく聞くのだが、本書を読むと、ことはそれほど単純ではないようである。軍人階級の保守性は、新しい兵器が登場した時に、それがもたらす戦術の根本的な変化を想像できないし、自らが身につけた行動様式を変えること、あるいは自らの存在理由を破棄することは受け入れがたく、さらにさまざまな利権や武器を売る側の営業力もからんで、すぐれた兵器だからだれもが飛びつくということにはなかなかならないようである。 最初の機関銃が登場してから100年余り経った1975年に出版された本書は、社会史の視点でこの画期的な兵器の黎明から、戦車があらわれさらに電子戦への移行で陰りを見せるまでをたどる。軍人階級は最初なかなか機関銃を受け入れず、彼らの部下である膨大な数の兵士たちに無駄死にを強いる。機関銃が最初に活躍するのは、労働争議であり、また人間扱いをする必要がない異民族・異教徒との戦いである。それがよいということではないかもしれないが、いかに犠牲者を少なく抑え、早く終わらせるかというような、合理的な発想で戦争が遂行されているわけではないということを、機関銃という兵器の歴史を通じて再認識させられる。 |
| チェスタトン 『木曜日だった男』(光文社古典新訳文庫) |
| 私はチェスタトンというとブラウン神父シリーズってのがあったなあという程度の認識しかなかったから、たまたま書店で見かけてあとがきで経歴を読んで興味を持ち、ちょうど100年前に発表された本書を楽しんだ。曜日の名で呼ばれる正体の分からない男たちの集会は、無政府主義の集まりかと思いきや・・・。リーダーである日曜日は何者か・・・。話の流れはだんだん見えてくるし、落ちはコレかい、といったところではあるのだが、そこは突拍子もない出来事の連続にジャーナリスティックな見方のヒネリが一貫していて、ひきこまれて一気に読んでしまった。このころの霧深いロンドンでは、何が起こってもおかしくないのだ。 |
| ケリー・リンク 『マジック・フォー・ビギナーズ』(早川書房) |
| うーんこれはちょっと悩んだ。なかなか感想を書けなかったが、ここで中途半端でも書ききってしまうことにした。話題になった短編集なので、かなり期待して読み始めたのだが、意外に入り込めない自分がいて、どう考えてよいのかというか、考え込んで止まってしまうのがつらい感じだった。普通に過ぎ去っていく日常の生活が書き込まれていて、そのすぐ傍で異空間が口をあけている。簡単に言ってしまえば、どの作品にもそういう構成が見えている。状況は様々で、読み始めはどれも期待させるのだが、途中から付いていけなくなる、そんな展開だ。不条理な設定は嫌いではないのだが、私が楽しめるのはそういう世界に自分も一緒に迷い込んでいるような感覚なのだと思う。それなのに、この作品群では、登場人物たちがそういう状況の中にいともすんなりと居場所を見つけているのに、読み手である自分がそこに入り込む余地がないままに物語がどんどん流れて行ってしまって、まるでハンカチ落としの鬼になったまま椅子に座れずにぐるぐる回り続けて焦っているような感じがする。というわけで私はこの著者の本は苦手みたいだ。 |
| 杉山登志郎 『発達障害の子どもたち』(講談社現代新書) |
| 発達障害に関する知見は、ここ数年で大きく変化している。「落ち着きのない子はADHDの可能性が高い」「発達障害は治らない」「できるだけ通常学級で生活させることが発達障害児によい」「不登校児には登校刺激を与えない」などがまだ常識だと思っていたら、この本を読んだほうがよい。また数年経ったら、この本に代わる新しい本が、同じ著者によって書かれることを期待したい。発達障害そのものがほんの数年前にはほとんど学校でも知られていなかったのに比べると、学習障害、ADHD、アスペルガー症候群などの診断名は、マスコミでもよく見かけるようになってきた。しかし、たとえば一時期ADHDが広く話題になると、小学校低学年での落ち着きのなさから安易にADHDの疑いをもたれることになったが、手のつけられない多動は広汎性発達障害であるケースが実は多かったことが分かってきた。特別支援教育も適切に行われれば発達障害児に社会適応を高める上で有効である。現状の問題点も山積でありその指摘も容赦ない。ただ諸外国と比べると、もともと教員定数で圧倒的に不利な中で働かされている日本の教師や学校は、全体としてはかなりよく頑張っていることも、データを見れば事実である。少なくとも、これからの発達障害児は、これまでの発達障害児よりもよりいっそう恵まれた教育を受けられるのでなければ、特別支援教育の意味がない。ぜひ制度整備や人材確保を実現させたい。 |
| 福岡伸一 『生物と無生物のあいだ』(講談社現代新書) |
| かなり話題になった本なので、感想もいまさらという気もするが、確かにこれは面白いし、ためになる。著者の文学的な表現が、われわれ文科系の読み手にも親しみを感じさせるし、科学者の人物像に焦点を当てた展開も興味深い。何よりも、生命科学の世界の驚くべき様相が、どこを取り出してもわかりやすく説明されていてありがたい。生命が動的平衡にある流れであることに納得がいくし、機械論的な生命観の不完全さを克服する視点が見えてくる。いやまったく、生命という現象はすばらしい。 |
| ロバート・トゥーイ 『物しか書けなかった物書き』(河出書房新社) |
| ぐだぐだした現実とやらに絡め取られているなあという気分の時は、とにかくナンダコレは!とんでもないぞ!という本を読むとイイ。これ、ミステリーともホラーともファンタジーともSFともつかない、奇想と緻密なストーリーが絶妙に交わったところに成立する、絶対にありえないのに引き込まれざるをえない傑作短篇集。タイトル作は、「書いた物」が実際に「物」になってしまう作家の話なのだが、その設定の下にミステリー仕立ての落ちが待っている。そういうとんでもない話の中に、例えば「そこは空気も澄んで」のような皮肉で悲しいドラマも挟み込まれていたり。編者の法月綸太郎のお手並みも見事。こういう物語を書いてくれる人が世の中にいるから生きていられるんだよ。 |
| 内田樹 『ためらいの倫理学』(角川文庫) |
| 内田樹の本は最近良く出ているようだし、そういえば私も何冊か読んでいてここでも感想を書いたこともあったのだが、2001年発行の本書はその原点のような一冊なので、改めて読み返してみて、なんだこんなに共感できる本だったのかと、再認識した次第。例えば小学校以来の親友平川君との歴史的出会いのエピソードから歴史教育論争をきっぱりと切ったり、「女子高校生の生態に詳しいくらいのことで、なんでこの男はこんな威張っているのか、私にはよく分からない。」(この男が誰だかこれだけで判ってしまうかもしれないが、気になる方は188ページを読んでください)と断じたり、ヴォネガットの「ハイホー」からポストモダニストの不自由を論じたり、一つ一つ笑っているうちに「ためらいの倫理学」が読めてくる。私には現代倫理学の立脚点は内田の論点ーーーそれもとてもつかみやすい形で語られているーーーあたりに置くのがもっとも実りがありそうだと思っている。 |
|
島田裕巳 『日本の10大新宗教』(幻冬舎新書)
|
| 新宗教を概観するのにたいへん便利な本。私の場合手元には大部の弘文堂版『新宗教事典』があるにはあるが、さすがに平成2年の発行でその後の変化を追うには他の資料が必要である。宗教学者がそつなくダイジェストした解説書というだけでなく、よく取材された読める事典として、重宝する。オウムの事件が転機となったのはもちろんだが、現代において新宗教が教勢を伸ばすのは難しい局面を迎えていることも、よく分かる。 |
| 春日武彦 『問題は、躁なんです』(光文社新書) |
|
精神科医の書くものでは春日のものはハズレがないと思う。「軽躁的な資質は、おそらく政治家には必須である。ただしそれを上回る腹黒さや計算高さも備わっていなければ人の上に立つ人物の資格はなく、ただのお調子者でしかない。」(p.133)なんて、さらりとステキな文が出てくる。 おかしな話だが、最近は「躁」がブームになっているのではないか、と感じる。「うつ」がすっかり定着し、抗うつ剤の効果についての知見も安定してみると、治りにくい「うつ」がちょっと良くなった状態と思われていた中に「軽躁」が隠れていることも分かってきて、おそらく診断的にはよりよくなってきたのだろうが、振り返ってみればやはりブームになっていた発達障害や人格障害にもまたこれがかなり紛れ込んでいたのではないかというわけだから、例えば犯罪と結び付けられた発達障害等は、それに苦しむ人たちにとってはかなりのとばっちりを受けてしまったともいえる。犯罪や文学に広く目配りした考察はいつもながら痛快なのだが、一番考えさせられたのはそういうことである。 |
| 山崎正和 『文明としての教育』(新潮新書) |
|
「道徳」の教科化をめぐって、ナントカ国民会議に対して中教審会長として反対の立場をとったことが記憶に新しいが、それは山崎が単にどっち側の立場についたのつかないのというほど、学校教育に対するスタンスとしては単純な理由によってのことではない。 山崎は敗戦後の満州で不安定な立場の居留民の手で維持された学校で小学校から中学に上がる。通学途上で野犬が赤ん坊を咥えて通り過ぎ、レンガの壁しかない教室には凍りついた首吊り死体がぶら下がっている。そんな状況の中で、残った大人がボランティアのにわか教師となり、学校教育を維持している。危険な異国の地に閉じ込められながら、勉強を通じて世界とつながり、日本語を学ぶことで日本とつながる。国家主義の過ちを棄てたところに、国家が自分たちを守るのではなく、自分たちが国家を守っていかなければならないという自覚が生じる。 「ひと言で言えば、あのときの私は、いっさいの強制的な権力を失い、しかし普遍的な文明の装置として、純粋な制度として残った国家の教育を受けていたといえるでしょう。」という一文は、山崎の主張を端的に言いあらわしていると感じる。 そのような原体験に基礎付けられた上で、ヨーロッパ、アメリカ、中国の教育史を俯瞰しながら、文明論から日本の学校教育を方向付ける発想は、素直で分かりやすいが、メディアを通じて伝わってくる教育改革論議は相変わらずのその場しのぎだ。それが審議会というものなのか、メディアの側の問題なのかは分からない。そして、山崎の主張も一つの立場に過ぎないといえばその通りではある。それでもなお、こうした根本から一貫性のある議論を提示されることがなさ過ぎたし、必要であると思う。いずれにせよ学校教育を権威や権力の関係の中において考えないと、威勢ばかりの空論になることは間違いない。 |
| P.G.ウッドハウス 『ジーヴスと恋の季節』(国書刊行会) |
|
またまたウッドハウスでごめんなさい。最近翻訳が増えてうれしい限り。しかもあとがきによるとなんと女性コミック誌で漫画化されるとか! しかし白泉社「メロディ」・・・くれぐれも近所で立ち読みしないようにと妻に釘差されました。そういえば、英国独身貴族を主人公にした漫画といえば坂田靖子のバジル氏、おもしろかったですな。今思えば、もしかすると坂田靖子もウッドハウス・ファンだったかもしれません。 さて本作は典型的なジーブスモノ長編、コーキーとエズモンド・ハドック、ガートルードとキャッツミート、マデラインとガッシー、さらにメイドのクウィニーとドブズ巡査という恋仲の4組の男女が、バーティを巻き込んでドタバタを繰り広げる。今回は、バーティのアガサ伯母さんに加えて、エズモンドの5人のおばさんが登場するが、ウッドハウス自身が子供の頃たくさんのおばさんに囲まれていた生い立ちから来ているらしく、まあなんとも強烈な脇役である。脇役と言えば、そのエズモンドと「初期ヴィクトリア朝のヴィンテージ物の」5人の伯母さんが住むデヴリル・ホールの執事のシルヴァースミス、なんとジーヴスの叔父という設定である。もちろん、この複雑にもつれ合った赤い糸を解きほぐすのがジーヴスのお手並みである。 前にも書いたが、これ、丁寧に映画化したら本当に面白いと思うのだが。実際、読んでいても登場人物が多いので、頭の中で知っている俳優で配役しながら読んでいるほどだ(コーキーやマデラインにピッタリの役者というのが浮かばないのだが、イメージさえ浮かべばよいので、かなりテキトー)。はじめて読む人には短編集を勧めるけれど、配役さえ叩き込んでおけばいきなり読んでもこの長編は十分楽しめるだろう。 |
| 最相葉月 『絶対音感』(新潮文庫) |
| この本は単行本で出たときにベストセラーになり、小学館文庫に続いて新潮文庫で再文庫化という息の長い一冊。ライターとして当たり前なのかもしれないが、興味を持ったテーマの取材は徹底している。100人にアンケートをとり、回答のあった人には直接取材を試みる。絶対音感教育の歴史と現状に関する内容は面白かった。戦時中は敵機や敵艦を聞き分けるために重視され、戦後はおそらく色々な分野でブームになった才能発見の音楽版だったのだろう。学校音楽の移動ドと音楽の専門教育の固定ドの常識の違いも興味深かった。音楽教育に続いて、脳科学や心理学における絶対音感の研究が紹介される。嗅覚や味覚が特別に鋭敏な人がいたり、動体視力が優秀な人というのもいるから、おそらく絶対音感というのも、それほど特殊な能力ではないのかもしれない。圧巻は五嶋ファミリーの取材。音楽一家のドキュメンタリーとしての読み応えがあるが、絶対音感というテーマからはやや離れているかも知れない。とはいえ、読後感の手ごたえは申し分なし。同著者のほかの仕事も読みたくなるし、反面最近増えてきた新書シリーズあたりに多い同じテーマを使いまわしたり引用だらけで他人のふんどしを洗濯もせずに盗み穿いて相撲をとっているような有象無象が許せなくなる。余計なお世話だが。 |
|
カント 『永遠平和のために』(集英社)
カント 『永遠平和のために/啓蒙とは何か 他3編』(光文社古典新訳文庫) |
| 中公クラシックスなど古典再読のシリーズが増えてきたのは退職した団塊世代あたりがターゲットなのだろうか。本当は、高校生あたりの世代が読みやすい古典翻訳がこれまで少なかったのはちょっと手遅れ感がある。倫理の授業などで読みやすいテキストが少なかったのだ。集英社から出たのは池内紀の翻訳で、藤原新也、野町和嘉、江成常夫のすばらしい写真に引用句をレイアウトしたイントロダクションがついている。帯にある「16歳からの平和論」の副題は、この時代に是非この書を紐解いて欲しいという、編集者と訳者の願いがある。とはいえじっくりと読み解きたい向きには中山元訳の光文社文庫版がお勧めである。『永遠平和のために』の驚異的な普遍性に比べると、歴史的背景の理解は必要ながら、短い『啓蒙とは何か』にこめられた含蓄は深い。他の著作も再読に値する。 |


