

 バックナンバー(07年10月〜12月)
バックナンバー(07年10月〜12月)
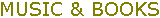
| >HOME >BOOKS |
| チャールズ・ストロス 『残虐行為記録保管所』(早川書房) |
| 書店で見かけた瞬間、バラードの『残虐行為博覧会』の再版かと思った。原題は確か "The Atrocity Exhibition" に対して "The Atrocity Archives" だ。だが内容は私があまり読まないラブクラフトの世界を、現代の数学や物理学の理論と絡めて現前させるというもののようだ。ラブクラフトは良く知らないのだが、それでもかなり面白くて一気読みしてしまった。ランドリーとよばれる外見上は古臭いイギリスの役所に勤めるハッカーが主人公だが、ランドリーは数学や物理学、情報理論などなどの研究動向に目を光らせていて、かつてナチスが試みたように魔界との扉を開いてこの世を破滅に導く真理に近づきそうになると、それを防ぐのが本当の仕事なのだ。主人公もそれでスカウトされた。官僚制と自由なハッカーの軋轢といういたってありふれた日常の出来事と、異界との接点が開き一瞬の後に破滅が訪れかねない出来事とのギャップが絶妙である。こんな小説読んだことない。短編の『コンクリート・ジャングル』も収録。 |
| マーティン・コーエン 『倫理問題101』(ちくま学芸文庫) |
| 私の勤務先は、航空に関係のある学校なので、新校舎は「三枚羽のプロペラを模った」といわれる、中央にエレベータホールがあって三方向に廊下が伸びる形になっているものが、コンペで選ばれて作られた。そのデザインを見て、私の頭に最初に浮かんだのが、ベンサムが考え出し、フーコーによってさらに知られるようになったパノプティコン(一望監視監獄)の基本構造だったわけだが、もちろん私にはデザインを選ぶ権限はなかったから黙っていた。もし各フロアに監視カメラを取り付けるとすれば、エレベータホールに一基で済むので、効率的な構造であることは間違いない。特徴的な建物には違いないが、数年後に新築なった東京拘置所の新舎房が、外見上非常に似たものになったのは、ある程度やむを得ない結果であろう(向こうは4枚羽らしい。Xウィングともいえる)。私の妻は首都高を運転していて「あなたの学校が見えてきたら、だいぶ家に近づいてきたとほっとする」と言っていたが、後日同乗していてそれが私の勤務校ではなく、東京拘置所であるのがわかったというのは笑えない笑い話である。本書にもパノプティコンが図入りで紹介され、ベンサムの思考が現代の監視社会の状況に重ね合わせて論じられている。 本書は、現代的な、あるいは時代を問わない、倫理的なジレンマを最初に101題提示し、後半それを受けて、倫理学の諸理論からそれらのジレンマを分析する、という構造になっている。素材は楽しく、分析もわかりやすい。量的には多いが、どこから拾い読みしても面白い。倫理教育に倫理思想史からの脱却が求められて久しいが、本書を高校生自身に読ませることが無理であるにせよ、教師のネタ本には十分になり得ると思う。 倫理学の存在意義を否定する人は多いが、人が生きていく上で少しでも「よりよい」選択をしようと思うのであれば、それがどのような学問的な形態をとるとしても、倫理学は存在するというのが私の立場である(私にとって納得のいく枠組みはまだ見つかってはいないにせよ)。だから、それは心理学や生理学の領域に踏み込むかもしれないし(私が大学院で心理学を学んだのもそのためである)、思料よりは現実のケースワークが必要かもしれない(私が教育や臨床のフィールドを重視するのもそのためである)。そういう倫理学の可能性の大きさを知るために、本書が格好のテキストであることは疑いない。 |
| 誉田哲也 『武士道シックスティーン』(文芸春秋) |
| ウチの高2の次男が、剣道部の副部長である。ヘナチョコだったので、小学校低学年のころ母親が地元の剣友会に連れて行って以来、その母親のプレッシャーからやめるにやめられず、ココまで来てしまった。なぜ副部長か。高2の部員が二人しかいないからである。部長のH君は、学業優秀で、剣道の腕前も抜群である。彼のお父さんはある中央官庁のエリートで、剣道7段。そんな父親にも、H君は物怖じするどころか、お父さんの剣道はココが悪い、とか意見するそうである。一方、ウチの次男は剣道は弱いし、学業は・・・。父親は・・・。と、まあ、そんな息子だが(親も親だが)、先日は二人で昇段審査に出かけて、揃って3段を取ってきた帰りに、「オマエが副部長だったからやってこれたよ。ありがとうな」とかいわれたらしい。自分が弱いことはコンプレックスになりそうなものだが、下級生の指導や、部室や道場の掃除など熱心にやっていたようだ。迷コンビは、今日も下級生に気合を入れていたのだろうか。 長々と息子の話をしてしまったが、この小説、女子高校生二人の剣道小説で、剣道のルールやら細かな描写が、自分ではやらないけれども息子がらみで剣道と付き合ってきた自分の目から見て、本当にすんなりと楽しめてしまって、一つ一つのエピソードが、息子や周りの子どもたちの色々な出来事の思い出につながって、楽しかった。強かったけれどもやめてしまった子たちが存外に多いので、息子が続いたのも勝ち負けで言えば圧倒的に負けがこんでいたにもかかわらず、(母親のプレッシャーはあったにせよ)周りの大人たちや先輩、先生方のおかげだと思う。そういうことが見えてくる展開が、ピタッと来るので、まあちょっと、ジーンとしちゃうわけですね。 装丁もとても良いです。剣道具のイラストもかわいらしく、しおり紐がなぜ赤白二本? と思ったが、たぶんこれは試合の時につける襷のイメージなんでしょうね。あとコレは是非映画化して、少し剣道人気をアップさせて欲しいですね。西荻は成海璃子がいいな。磯山は香椎由宇どうかな。 |
| G.A.コーエン 『あなたが平等主義者なら、どうしてそんなにお金持ちなのですか』(こぶし書房) |
|
ひょんなことから、労働組合関係の役割を分担することになってしまいました。もともと、こういうことはすごく苦手です。特に、私が所属する職場では、組合の路線問題(というのかどうかも正確には知らないが)でモメやすいのと、そもそも組合やら労使関係やらにまるきり疎い人も多いので、なかなかコトをまとめたり収めたりするのがやっかいです。ああめんどくさい。でも自分の権利は自分で守らなくちゃね。だからいやだいやだといいながらもコツコツがんばっているところです。はい。 まあワタシなどが言うのもおこがましいですが、組合というヤツは、あまり活動がユルいともともとダサイ上に何のために組合費払ってるんだ的なカンジで加入者が減るし、かといってあまり活動が濃いとついていけない感で抜けたり割れたりするしで、ほどほどが難しいです。基本的に、共通の利益を追求できればいいので、立場の違いや意見の違いはできるだけ先鋭化させたくない。でもこれが難しいんだな。そういえばむかーし若い頃、役員選挙の時に知り合いの人の推薦人にちっちゃく名前を連ねただけで、ワタシは親○○派=反××派とレッテル貼られたりしましたし。おれはどっちでもないよ(あえていえばどっちも嫌い・・・ああ言っちゃった)。ああ胃が痛い。 で、この本です。実はタイトル買い。ちょっとムチャではありました。著者はオックスフォードで政治学を講ずる学者ですが、ずばり言えば、信念形成の問題を扱った第一講「確信のパラドックス」、ワタシなどにはちょっと想像もつかない生い立ちである第二講「モントリオールのユダヤ人共産主義者の幼年期」がいちばん面白かったです。わが国の言論界や教育界で影響力のある人たちでも、ガチで右寄りのX氏とか、さりげなく右のZ氏などの有名人が、かつてはバリバリの共産党員だったことは、本人たちも語っていたりしますが、反体制の立ち位置で集団を動かしていた人というのは、ポジションが変わっても相変わらず強いというか、敵をよく知っているだけに怖いものがないな、といつも思わされます。敵も多いし風当たりも強いが、味方はしっかりしていますし風当たりなんてどこ吹く風です。強いです。この人も、後半は迫力あるマルクス、エンゲルス批判を展開しますが(正直なところここまで来るとほとんどついていけてない)、かといってロールズの正義論の限界に切り込むあたりからも、徹底した平等主義者の旗色鮮明で、ネオリベラルへの重厚な攻撃になっています。結局、なぜこの本を、ほとんど理解できない理論の深みにはまる(正確には、はまりそうになるところは飛び越えてしまうのだが)のに読んでしまうのかというと、第一講と第二講の人間的魅力に尽きるわけです。解説のような論理的な批判への論理的な反論は、たぶんマルクス主義の洗礼を受けていない私のような宙ぶらりんの読者には、ほとんど興味は持てません。そこが一番大事な箇所なのかもしれませんが。 |
| P.G.ウッドハウス 『ブランディングズ城の夏の稲妻』(国書刊行会) |
| 国書刊行会からウッドハウスの新しいシリーズが始まって、これで執事ジーブズものと並んで大傑作のシリーズのエムズワース伯爵ものを堪能できることになった。こんなにうれしいことはない。短編集が文藝春秋から出ていたが、こちらは待望の長編である。さて今回もお嬢様方がたいそう魅力的で、スーとミリセントは完全にロニーとヒューゴを手玉に取っているが、ほかにも私立探偵やら元秘書やらはさんざんな目に遭い、頑固なコンスタンス伯母と破天荒なギャラハド卿の軋轢も気の利いた展開になって、結局、豚にしか興味がないエムズワース卿にとってなにもかも丸く収まる、という成り行きである。巻末の解説も充実していて、ウッドハウス研究者がついに豚のモデルを特定し、なんとその写真まで発見する件りも、またもう一つの愉快さを与えてくれる。 |
| ペンギン基金 『ペンギンのABC』(河出書房新社) |
| 南極観測隊でペンギン研究に打ち込んだ故青柳昌弘によって設立されたNGO、ペンギン基金による、ペンギンのエピソードをABC順に詰め込んだ、ペンギンマニア、ペンギンファンにはもうたまらない一冊。表紙はもちろん坂崎千春ですし、絵も写真も満載、研究家や音楽家などが各項目で蘊蓄を傾けてくれています。各種ペンギンの生態はもちろんですが、さまざまなキャラクター、レアなペンギングッズの数々、ペンギンの巣箱の設計図から、ちょっとブラック?なものとしてはペンギンの値段や、卵料理のレシピなんかもあります。この一冊があれば、ペンギンファンのワタシは、パラパラめくるたびにちょっとシアワセになれます。 |
| 清野由美 『セーラが町にやってきた』(プレジデント社) |
| 関西外語大に交換留学生でやってきて以来、日米の懸け橋となる生き方を目指した一人のアメリカ人が、長野冬季五輪のボランティアをきっかけに小布施堂と出会い、その社員として会社を変え、街づくりを担っていく。何せ、造り酒屋などというとんでもなく伝統的な世界に入り込み、木桶醸造まで再開させてしまうというのみならず、世界を駆け巡って葛飾北斎の学術会議を招致するなど小布施の町まで変えてしまうのだ。アメリカの婚約者を振ってまで日本に入れ込む彼女の活動はすごい。しかしこの計算のない行動力は、並の社会ではあまりの勢いに弾き飛ばされてしまうだろう。まさにそういう意味では、小布施堂の経営者や、桝一の杜氏をはじめとするこだわりの職人たちの世界との出会いが、彼女の活動性とこれ以上ないほどにかみ合ったのだろう。日経のウーマンオブジイヤー2002まで受賞。今も小布施の町に活気を与え続けているようです。 |
| ルチャーノ・デ・クレシェンツォ 『秩序系と無秩序系』(文芸春秋) |
| 中学生か高校生ぐらいの時に、映画『嘆きの天使』を見た。当時から真面目なワタシは、教師になりたいと思っていたこともあって、こりゃーなんてヒドイ映画だ、というショックを受けたとともに、いやいやいや、真面目な自分が真面目な教師になって、こんな風に身を持ち崩してしまったらヤバイヤバイ、これは教訓とすべき映画だ、とまたこれがクソ真面目に思ったことであった。さてその教訓は生きているのか? 本書を読むと、「映画」の章の結びに『嘆きの天使』が使われるのだが、これが現代イタリアバージョンになると「無秩序のシャワー」の話になるわけだ。『嘆きの天使』を見る代わりにこれを読んでいたとしたら、教師志望の青年はどんな人生を歩むことになったのか? 最高におかしいのはもっともナポリ的な「宝くじ」だろうか。もちろん、哲学ネタも満載だが、シニカルな「ゴミ」などは、案外、日本にあてはめても同じように読めてしまう。そういえば、哲学史シリーズのレオナルド・ダ・ビンチの章で、ミス・イタリアの選考でレオナルド・ダ・ビンチについて質問したら、かわいいお嬢さんの答えは「空港の名前ですよね?」だったというのを読んで、まあそういう事情はどこでも同じか、と妙に感心した覚えもある。ナポリと対照的に描かれるのがミラノというのはお約束だが、その描かれ方がまるで東京のようなのだが、さて実際は同なのだろう。ますますイタリアへの興味を募らせる、楽しい一冊である。 |
| ジェーン・グドール 『森の旅人』(角川書店) |
| グドールが京都大学の名誉博士号を授与されたとのニュースを聞いた。チンパンジーといえばワタシはグドールと松沢哲郎をすぐ思い出すが、霊長類研究で優れた業績を誇る京都大学とグドールとの結びつきが、なんともうれしいニュースだった。さてこの自伝、実はかなり「スピリチュアル」なのだ(そもそも原題が "Reason For Hope - A Spiritual Journey")。だから2000年の発行当時はともかく、2007年の今はわが国ではこの「スピリチュアル」は両刃の剣かもしれない。とはいえ、改めてじっくり味わうのにふさわしい内容である。まずなんとなく「チンパンジー研究に生涯をささげた女性研究者」というと何かしら現実離れした聖女のような思い込みを持つ人も多いのではないかと思うが(知らないうちはワタシがそうだったので)、これがとんでもない行動力を持つヒトなのだ。結婚にも一回失敗し、二度目は死別しているが、夫や子どもとの関係なども率直に語られている。子ども時代から一貫してチンパンジーに抱き続けた興味を、経済的にも世界情勢からしても普通は実現できない研究者への道につなげ、切り開いていってしまう彼女の人間性と行動力にはただ圧倒される。そして、そこから信仰や愛や希望といった、本来の意味で「スピリチュアル」な観念が、動物の保護や、人類の平和への行動に結実していくのだ。是非この機会に一読を。 |
| R.A.ラファティ 『宇宙舟歌』(国書刊行会) |
| オデュッセイアの宇宙版で、オムニバス形式の、まあとんでもない宇宙船の船長によるホラ話である。ワタシはラファティはとにかく短編が好きで、「せまい谷」とか「うちの町内」のような、SFモチーフで酒場のヨタ話を作っちまいました感あふれる作品は何度読んでも笑ってしまう。オチが分かっていても笑ってしまうというのは、やはりこれは落語のような話芸に近いものがあるのだろうか。それに対して長編は、おそらく翻訳の困難さもあってか、いま一つ入り込めないこともあるのだが、本書はオムニバス形式ということもあって、ラファティの破天荒さがうまい具合にちりばめられて、飽きさせない流れになっている。ところでスティーブヒレッジのバンド、カーンの "Space Shanty" は、この "Space Chantey" とは無関係なのだろうか。歌詞を見ただけではわからないが、少なくともインスパイアされたのではないか、と思うのは、このアルバムの曲名のいくつかはSF小説に似たものがあるからであるが。 |
| 村上宣寛 『IQってホントは何なんだ?』(日経BP社) |
| 『「心理テスト」はウソでした』に続く著者の一般向け心理学解説書。現代のIQテストが標準得点化されていることを心理学の教科書が触れていないのはなぜか。そこには、「知能」研究における我が国の遅れというか学界の敬遠があらわれている。我が国で使われてきた知能テストのあやしさについては、前著と同様に明快である。おそらく、こういう事実がこの国の学界ではタブーなのだろう。知能研究の歴史も丹念にたどられているし、統計学の入門的な要素もある。一般向けというにはやや難解な部分もあるが、このテーマを誠実に論じようとすれば、むしろここまでわかりやすく、必要十分な中身を盛り込んだというのは、学者の仕事としてはすごいことだと思う。 |
| ルチャーノ・デ・クレシェンツォ 『物語 中世哲学史』(而立書房) |
| 中世哲学の再評価が進んでいるいっぽうで、高校倫理で扱われる中世哲学はごく限られている。もともと、ルネサンスとの対比で暗黒時代とされていた頃の中世像を引きずったまま、デファクトスタンダート的な教科書が扱ってきたごくわずかの例外、すなわちアウグスティヌスとトマス・アキナスに加えて、若干の追補が見られるにすぎない。かといって、中世哲学をどこまで取り扱い得るかというと、それこそ本書の中にも「哲学には、恐ろしい言葉、すべての高校生をおののかせる言葉、”存在論”がある」(p.114)と、かの国においてすら高校生が恐れおののくほどらしいから、まあ一言でいえばムリ。実際、教える立場の教師にしても、中世哲学を教えられるかと言えば、私も含めてほとんどがはなはだ心もとないのが実情だろう。では本書を読めば、中世哲学について最低限の知識を得ることができるだろうか? 正直なところ、まったくの哲学の初心者にとっては、それは少し難しいかもしれない。しかし若干の予備知識がある読み手、それこそ高校倫理は学んだけれども中世哲学はやらなかったかも、という人にとっては、本書は抱腹絶倒、たぶん(私はそうだったが)一日で読み切ってしまう、たいへんおもしろい読み物であるといえる。まずはサッカーの試合で始まり、妻との馴れ初めとテレビ出演のネタでおわる13章などをお楽しみになれば、本書のユニークさがお分かりいただけるだろう。十字軍とサラディンのことを学びながら、イタリアの子供もレアカード収集に熱中するんだ、という雑学も身につくので、お茶の間の話題にもできる。こんな哲学書はほかにない。同じ著者によるシリーズのギリシア哲学史や近代哲学史もお勧めである。 |
| フィリップ・ブルマン 『黄金の羅針盤』ほか・「ライラの冒険」シリーズ (新潮文庫) |
| 『黄金の羅針盤』『神秘の短剣』『琥珀の望遠鏡』の3話、各上下合計6巻からなる、ファンタジーシリーズ。すでに既刊だったからかもしれないが、ファンタジーが苦手なワタシにしては珍しく、一日一冊で一気読みだった。確かにこれは面白いや。パラレルワールドを行き来する少女を主人公に、親子や夫婦の葛藤、愛の目覚め、水上生活者や魔女やクマや、さまざまな部族の軋轢、ダイモンや天使やファントムといった抽象性の高い存在が、縦横無尽に描かれる。しかも大きな背景に神学論争と素粒子論や量子論が絡まるのがミソ。つまりテーマはかなり大人向きなのである。すでに映画化され公開予定ということだが、非キリスト教圏でもわかりやすい脚本になっているのかどうかもちょっと興味がある。 |
| ジェニファー・ウーレット 『黒体と量子猫1・2』(ハヤカワ文庫NF) |
| 副題「ワンダフルな物理史」古典編・現代編の2巻からなる、物理学の発明や発見のエピソード集。著者は科学ライターで、アメリカ物理学会のニューズレターに連載したコラムが人気となり、それをもとにまとめられたのが本書。一つ一つの話題や人物を丹念に取り上げている上に、よく知られた小説や映画などとの比較やたとえが楽しい。もともとのエピソード自体が面白いのはもちろんで、「レンズに似ているからレンズ豆なのではなく、レンズ豆に似ているからレンズだったのか!」というような単純な驚きから、テスラのようにとびきり興味深い人物とエジソンやマルコーニの俗っぽさとの対比など、なかなか考えさせられるものもある。現代編の最後はやはり超ひもだ。そこにはまだまだこの先に「そうだったのか!」と驚かされるような未来への期待でワクワクさせられるものがある。 |


