|
テレビドラマの感想を久しぶりに書いている。BONESは日本のテレビ放映時にはあまり興味がなかった、というかやはり死体のグロテスクさにいくらなんでも無理・・・という印象だったのだが、音楽番組目的で契約した光テレビで海外ドラマをいろいろと見ているうちに、アメリカ製作のドラマでは結局これとNCISが抜群に面白い、という結論に至った。さらにアマゾンのfireTVstickを、4980円という価格につられて購入したところが、プライム会員だと追加料金なしで見られる番組になんとBONESがシーズン9まで入っていたわけである。最初はやはりグロテスクと敬遠していたはずの妻がこれにはまってしまい、シーズン1の第一話から見ているほどで、最近では「どんな死体が出るかな!」とか言いながら、食事しながらでも見ている。慣れは怖い。
BONESに限らないがアメリカのドラマにはまるのは、基本的に45分程度の一話完結にこれでもかと詰め込まれた、本筋にサイドストーリーのスピード感である。正直なところ、私は最近ではほとんどの日本のテレビドラマ、特にミステリーやサスペンスにはもう退屈でリズムが合わなくなってしまった。本筋に関しても、サイドストーリーに関しても、どうしてこんな話を思いつくのだろう!という気持ちに、毎回されてしまい、楽しみながら舌を巻いている。
そのような基本的な魅力と言うか中毒性をさらにこれでもかと高めるのが、登場人物たちのとんでもない性格づけと、毎回趣向を凝らした死体である。
その死体、ものすごくグロい。埋まっているのは普通で、散らばっていたり、浮かんできたり、落ちてきたり、吹っ飛んできたり、ゴロゴロと転がってきたりするから、なんとも油断ならない。我が家では巨大チョコレートから溶け出てくるやつや、ボーリングのピンになって出てくるやつ、給食のシチューになってるやつ等の人気が高い。私はお父さんに無理やりキャンプに連れてこられた家族の上に落ちてくるやつや、離婚調停中の父親が子供を遊ばせに来る公園で遊具から頭がい骨が転がり出るやつなんかが、なかなか気にいっている。作りものと分かっていても、あまりにもよくできているので、最初の内はとても見続けられないだろうと思っているのだが、どうもこういうものは思わせぶりに隠すよりも、バーン!とさらされてしまった方が慣れてくるようである。
さらに主人公始め主要な登場人物がほとんど、普通じゃない。FBI捜査官のブースがスクインツと呼ぶ研究所のメンバーは、自分が天才であると自負している者が多いし、実際にそうなので、台詞がとにかく面白い。入れ替わり立ち替わりやってくるインターンは曲者ぞろいだが、みなボーンズにはかなわない。一方で、ボーンズの生い立ちなどにも深い傷があり、ブースだってギャンブル依存症である。ずっと見てきて思うのは、ほとんどの場合、殺人犯の方がよほど普通の人である、ということだ。あんがい、現実もそんなものかもしれないが。
難病や障害が重要なモチーフになることも多いし、セックスに関してもタブーがない。NCISではギブスのルールに職場恋愛禁止があったが、こちらはもうとっかえひっかえである(とはちょっと言い過ぎだが)。親子関係もやたらと複雑である。ブースとボーンズの宗教論争は、これでどうして二人が結婚できるのか不思議なほどだが、二人の子供が誕生する時のとんでもないドタバタで昇華するのには度肝を抜かれた。まさか最初から考えていたわけではないだろうな。
NCISと共通するのは、チームの仲の良さだ。親子関係や恋愛関係などにみんなが傷を負っていて、それが研究所で働く中で実際に家族と呼んでしまうほどの結びつきを形作っている。おそらく、アメリカ社会ではこういう人間関係が職場で形作られていく事に、強い魅力があるだけでなく、驚異すら感じられるのではないのだろうか。それだけに、チームが解散したり、メンバーのだれかが死んでしまったりすることが、見ていても非常にショックだったりする。ビンセントもショックだったが、何と言ってもスイーツはかわいそうだった。デイジーは妊娠しているし。ボーンズもデイジーも、実際に女優さんの妊娠に合わせてストーリーを作ってしまうのだから、これもまた驚くべき臨機応変、しかもそれが外れなく魅力のある話になっていくのだ。
原作者であるボーンズのモデルの法人類学者以外にも、やはりスタッフには関心を持たずにはいられない。このとんでもない死体をどのようにして作っているのだろうか。セットも含めて、キャストの出演料を除いた一回の製作費はいくらかかっているのだろうか。興味は尽きない。噂ではそろそろのようだが、終わってほしくないドラマシリーズである。
ページの先頭へ
|

 最近の更新(15年7月〜)
最近の更新(15年7月〜)
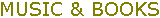

 最近の更新(15年7月〜)
最近の更新(15年7月〜)
 月刊「根本宗子」第14号 『スーパーストライク』作・演出 根本宗子
2017年10月16日(木)@下北沢ザ・スズナリ
魚釣りの話ではないが・・・釣りと言えなくもない
月刊「根本宗子」第14号 『スーパーストライク』作・演出 根本宗子
2017年10月16日(木)@下北沢ザ・スズナリ
魚釣りの話ではないが・・・釣りと言えなくもない
 プリズン・エクスペリメント('15 アメリカ)
「善い人間」がどのようにして悪魔にかわるのか
プリズン・エクスペリメント('15 アメリカ)
「善い人間」がどのようにして悪魔にかわるのか
 『メッセージ』('16 アメリカ)
子育てについて考えさせられるドラマでもある
『メッセージ』('16 アメリカ)
子育てについて考えさせられるドラマでもある
 『ドリーム』('17 アメリカ)
それはそうとジャネール・モネイはとにかくかっこいい
『ドリーム』('17 アメリカ)
それはそうとジャネール・モネイはとにかくかっこいい
 『花戦さ』('17 日本)
芸能の異種格闘技
『花戦さ』('17 日本)
芸能の異種格闘技
 『チャッピー』('15 アメリカ)
電池切れたら使い捨て?・・・そういう商売か
『チャッピー』('15 アメリカ)
電池切れたら使い捨て?・・・そういう商売か
 『BONES 10』('15 アメリカ)
慣れてしまうのは怖いことだけれど
『BONES 10』('15 アメリカ)
慣れてしまうのは怖いことだけれど
 『マエストロ!』('15 日本)
miwaはかわいい、けど、そこじゃない
『マエストロ!』('15 日本)
miwaはかわいい、けど、そこじゃない
 『日々ロック』('14 日本)
二階堂ふみはかわいい、だけじゃない。
『日々ロック』('14 日本)
二階堂ふみはかわいい、だけじゃない。
 『ストレイヤーズ・クロニクル』('15 日本)
背景が見通せないもどかしさ
『ストレイヤーズ・クロニクル』('15 日本)
背景が見通せないもどかしさ

